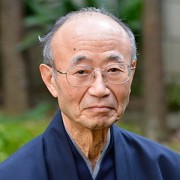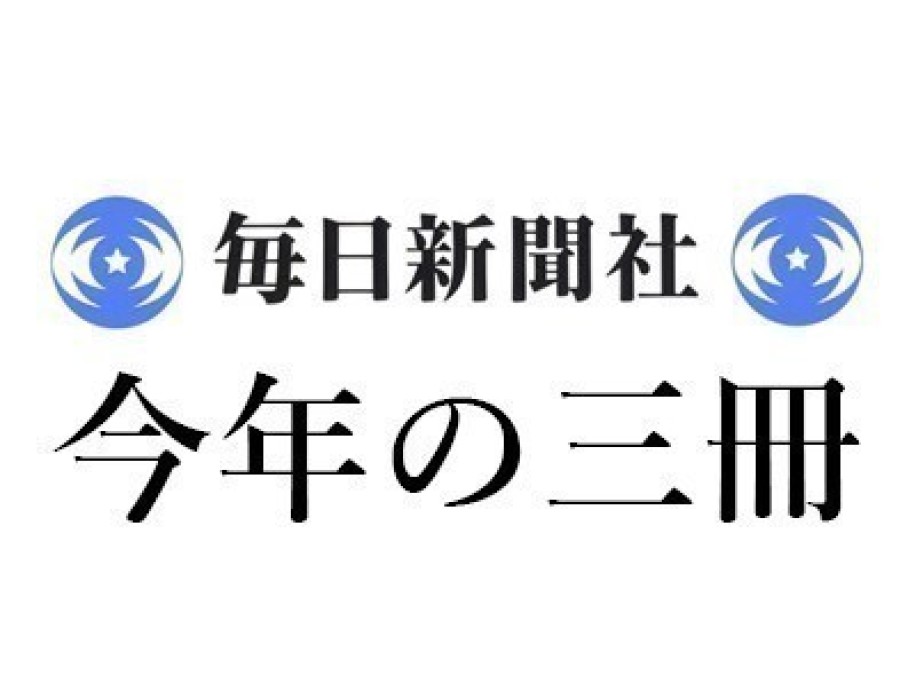書評
『騎馬民族は来なかった』(日本放送出版協会)
畜産民的文化の希薄さ立証
佐原さん、とうとうやりましたね。騎馬民族説という壮大なヴィジョンを戦後の日本人に提供した江上波夫さんの仮説を、こんどこそ正面からひっくり返そうとされたのですから。おっしゃるようにこの学説は、一九四八年に提唱されてから歴史好きの日本人を魅了してきました。それだけではありません。古代史や考古学、比較神話学や人類学のほとんどの専門家がこぞって反対したにもかかわらず、この学説は威風堂々と生きのびてきたのです。江上さんとはいくども対論をくり返し、呉越同舟の共著まで出されてきた佐原さんにとってはさぞかし無念のきわみであったにちがいありません。世にいう騎馬民族説というのは、四、五世紀のころ大陸の騎馬民族がわが国に侵入してきて征服王朝をつくったのだという学説です。さらにいえば崇神大王が朝鮮半島南部から北部九州に渡り、応神大王が九州から畿内を征服したという仮説です。江上さんはこの大胆きわまる構想を証明しようとして、わが国はもとよりユーラシア大陸にまたがる考古資料を総動員し、騎馬軍団のかつての栄光の姿を再現しようとしました。
それにたいする佐原さんの反撃は、むろん事実を一つひとつ積みあげていく用意周到なものです。まず、騎馬民族とは遊牧民がウマにのってはじめて成立する民族であり、そこに固有の文化が形成されたはずだといいます。たとえば血と内臓の知識、去勢と解剖の歴史、犠牲と祭りにかんする独特の習俗をとりあげて東西比較をおこない、日本にはこの種の畜産民的な文化がきわめて希薄であったことを明らかにしていきます。その佐原さんのとどまるところを知らないウンチクにはただ目を見張るばかりなのですが、ただ一言だけ申せば、たとえ学説の虚妄性を証明しえたとしても、その学説の人気や浸透力までをくつがえすことはかなり難しいのではないかという疑問はのこります。その理不尽な課題にどのように立ちむかっていったらよいのか、佐原さんにはまだまだ期待するところが大きいのです。
ALL REVIEWSをフォローする