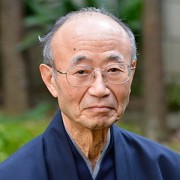書評
『父殺しの精神史』(法蔵館)
「師殺し」はなぜ失敗したか
オイディプス王の父殺しは、いまでもにぎやかな話の種だ。父殺しとは、そもそも偶然のなせるいたずらなのか、それともわれわれの遺伝子に組みこまれた欲望なのか。このフロイトによって発見された「父殺し」は、フレーザーの王殺しやニイチェの神殺しと連動し重層して、われわれの思考や想像力をガンジガラメに縛りつけてきた。
だが、よく考えてみよう。この父殺し幻想は、ユダヤ・キリスト教社会がつくりあげたフィクション(仮説)だったのではないか。つまりそれは、ヨーロッパが近代(もしくは近代人)を生みおとすために支払わなければならなかった負債であり、犠牲であった。かれらは父や王や神を殺すことによって自己を発見し、自己の存在証明を手にしようとしたのである。ここまでが学問の流儀において常識化されてきたアウトライン、といってよいだろう。
むろんそんな話の筋は、本書においては百も承知のことだ。重要なのは、著者がその先までふみこんで立てている二つの議論である。第一は「父殺し」論の先駆者たちのあいだでは、父や王や神を殺したあとその犯人の内面に、死と再生というもう一つのドラマが進行していることについての洞察が不十分だったということだ。このテーマを人類史の全体に拡大して論じたのが宗教学者エリアーデであった。
第二が、著者自身の「師殺し」体験を爼上(そじょう)にのせて、それが父殺しとしていかに不徹底なものであったかを描き出している点だ。ここでいう著者の師は同じ宗教学者の柳川啓一のことだが、その師殺しが不発に終わらざるをえなかったのはひとえに父の存在が微弱であった日本社会の圧力によるという。
はたしてそうか。その結語の背後にも、キリスト教的思考が見え隠れしてはいないか。真相はむしろ、著者の側に師を殺そうとする意図や動機がそもそも存在してはいなかったところにあるように評者にはみえるのである。
ALL REVIEWSをフォローする