書評
『宗教者ウィトゲンシュタイン』(法蔵館)
小ぶりの造本ながら、身がしまっている。十指にあまる材料を丁寧に読みこなして練りあげた、手応えのある一冊だ。
題名を見て、はて、ヴィトゲンシュタインが宗教に関わりをもっていたろうか、と疑問に思う向きもあろう。無理もない。彼が普通の意味で、ある宗教を信じていたとか、どこかの教会に所属していたとかいうことはないからだ。本書にもこうのべてある、《ヴィトゲンシュタインが「制度としての宗教」を否定的に考えていたこと》(一一六頁)は明らかである、と。にもかかわらず、ヴィトゲンシュタインその人の思想と生活は、終生、強固な宗教的動機に貫かれていた、と著者は主張する。
それでは、ヴィトゲンシュタインが《宗教者》であるとは、どういうことなのだろう。
著者星川氏はまず、ヴィトゲンシュタインと論理実証主義者たちとの相違に、われわれの注意をうながす。
たとえば『論理哲学論考』の、あの有名な結句「語りえぬものについては、沈黙しなければならない」を、どう考えるか。両者は、表面上類似したことを言っているみたいだが、《根本的なところでは全く対立する見解をいだいている》(一一五頁)。
論理実証主義の人々とはそもそも、《「語りえぬもの」の存在を否定する》(一一七頁)。《そうしたものは存在しえないし、それに何らかの価値もない》が彼らの信念なのである。それに対してヴィトゲンシュタインは、《「語りえないもの」……「倫理」「宗教」「神秘的なもの」などを価値あるものとして、積極的》に《位置づけ……ている》(一一六頁)。
このような彼の立場からすれば当然、論理実証主義者の行き方は、不満なものに写る。《論理実証主義のごとく、後者(=学問や科学の領域)にしか適用できない手法を前者(=宗教や倫理の領域)にも適用しようなどというのは、愚の骨頂》(一二二頁)だ。
結局、『論考』は、語りうることは何かを残らず示してしまうことによって、逆に、語りえないことの広がり、大きさを示すところに、その本当のねらいがあった。著者は面白い比喩を使っている。《大洋に浮ぶ島にたとえれば……島の内側から……海岸線を明確にしても、大洋の本当の巨大さは理解できない。視点を変えて、大洋の方から、それもその上空から島を見れば、その島がいかに小さなものであるかが理解できる》(一四〇頁)
ヴィトゲンシュタインの目ざしたところがこのようであったとして、それでは、ヴィトゲンシュタインを導いた、この逆説的な(=語りうることを語ることによって、語りえないことに近づこうという)熱情は何に由来するのか。
星川氏は、いくつかの補助線を引く。まず、ユダヤ系ドイツ人としての彼の、家庭的・宗教的背景。ユダヤ教の影は、ヴィトゲンシュタインが意識しないところにも表われている。たとえば彼の設計したストロンボウ邸が、垂直線や比例関係を強調し、内部装飾を徹底的に排除していること(=偶像崇拝の禁止)。つぎに、トルストイ(特に彼の『要約福音書』)への傾倒。すなわち、教会や一切の制度を介せず、富や虚飾を捨て去って、人生の真実のために己れの全身全霊を捧げつくす態度。さらに、生涯彼を苦しめた同性愛への傾向。はっきりした証拠はないのだが、彼が《粗暴な若い男と関係を持ちたがっていた》(一四二頁)とする評伝(W・バートリー『ウィトゲンシュタイン』一九七三)が話題となった。確かにこう考えると、符号するところも多い。たとえば、人里離れた小屋を好んだのは、そういう男性と接触するチャンスを自ら断ち切ろうとする努力であった、という具合に。こうした罪責感から逃れようとしたため、彼の哲学はなおさらストイックなものとなったのかもしれない。
《宗教者》であるとは、それゆえ、「語りえぬもの」への畏怖・畏敬を片時も忘れず、思想(思うこと)、行動(なすこと)を一元的に統合しようと歩みつづけることにほかならない。これは、ふつうの意味での宗教よりも、はるかに単純で、徹底した生き方である。
人生に躓き、宗教に心の糧を求めようとする読者にとって、ヴィトゲンシュタインの生涯をつぶさに知ることから、直接に得るところがどれだけあるものなのか、私にはわからない。しかし少なくとも、ここに描かれているのは、ユダヤ=キリスト教文化圏からなら現れても不思議でないタイプの、硬質で透明な知的人間の物語なのである。“神を知らない”わが国の読者たちにとって、恐らくこれは驚きであろう。
著者は、ヴィトゲンシュタインを知る人々の証言や、ヴィトゲンシュタイン自身の著作・遺稿・書簡からの引用など、関係するテキストを丹念につなぎ合わせ、《宗教者》としての彼の生きざまを浮きぼりにした。しかも、ヴィトゲンシュタインが語っていないことがらについて、推測をまじえて不必要に語りすぎてしまうという危険を、賢明にも避けている。類書を読破したうえでの、要領のよいまとめとも見えようが、適度に抑制された筆致が、かえってヴィトゲンシュタインの非凡で身近な実像を照らし出すことに成功している。
なお、ヴィトゲンシュタインと神学との結びつきについて、著者星川氏の手になる翻訳(A・キートリー『ウィトゲンシュタイン・文法・神』法蔵館)があることを、付言しておく。
【この書評が収録されている書籍】
題名を見て、はて、ヴィトゲンシュタインが宗教に関わりをもっていたろうか、と疑問に思う向きもあろう。無理もない。彼が普通の意味で、ある宗教を信じていたとか、どこかの教会に所属していたとかいうことはないからだ。本書にもこうのべてある、《ヴィトゲンシュタインが「制度としての宗教」を否定的に考えていたこと》(一一六頁)は明らかである、と。にもかかわらず、ヴィトゲンシュタインその人の思想と生活は、終生、強固な宗教的動機に貫かれていた、と著者は主張する。
それでは、ヴィトゲンシュタインが《宗教者》であるとは、どういうことなのだろう。
著者星川氏はまず、ヴィトゲンシュタインと論理実証主義者たちとの相違に、われわれの注意をうながす。
たとえば『論理哲学論考』の、あの有名な結句「語りえぬものについては、沈黙しなければならない」を、どう考えるか。両者は、表面上類似したことを言っているみたいだが、《根本的なところでは全く対立する見解をいだいている》(一一五頁)。
論理実証主義の人々とはそもそも、《「語りえぬもの」の存在を否定する》(一一七頁)。《そうしたものは存在しえないし、それに何らかの価値もない》が彼らの信念なのである。それに対してヴィトゲンシュタインは、《「語りえないもの」……「倫理」「宗教」「神秘的なもの」などを価値あるものとして、積極的》に《位置づけ……ている》(一一六頁)。
このような彼の立場からすれば当然、論理実証主義者の行き方は、不満なものに写る。《論理実証主義のごとく、後者(=学問や科学の領域)にしか適用できない手法を前者(=宗教や倫理の領域)にも適用しようなどというのは、愚の骨頂》(一二二頁)だ。
結局、『論考』は、語りうることは何かを残らず示してしまうことによって、逆に、語りえないことの広がり、大きさを示すところに、その本当のねらいがあった。著者は面白い比喩を使っている。《大洋に浮ぶ島にたとえれば……島の内側から……海岸線を明確にしても、大洋の本当の巨大さは理解できない。視点を変えて、大洋の方から、それもその上空から島を見れば、その島がいかに小さなものであるかが理解できる》(一四〇頁)
ヴィトゲンシュタインの目ざしたところがこのようであったとして、それでは、ヴィトゲンシュタインを導いた、この逆説的な(=語りうることを語ることによって、語りえないことに近づこうという)熱情は何に由来するのか。
星川氏は、いくつかの補助線を引く。まず、ユダヤ系ドイツ人としての彼の、家庭的・宗教的背景。ユダヤ教の影は、ヴィトゲンシュタインが意識しないところにも表われている。たとえば彼の設計したストロンボウ邸が、垂直線や比例関係を強調し、内部装飾を徹底的に排除していること(=偶像崇拝の禁止)。つぎに、トルストイ(特に彼の『要約福音書』)への傾倒。すなわち、教会や一切の制度を介せず、富や虚飾を捨て去って、人生の真実のために己れの全身全霊を捧げつくす態度。さらに、生涯彼を苦しめた同性愛への傾向。はっきりした証拠はないのだが、彼が《粗暴な若い男と関係を持ちたがっていた》(一四二頁)とする評伝(W・バートリー『ウィトゲンシュタイン』一九七三)が話題となった。確かにこう考えると、符号するところも多い。たとえば、人里離れた小屋を好んだのは、そういう男性と接触するチャンスを自ら断ち切ろうとする努力であった、という具合に。こうした罪責感から逃れようとしたため、彼の哲学はなおさらストイックなものとなったのかもしれない。
《宗教者》であるとは、それゆえ、「語りえぬもの」への畏怖・畏敬を片時も忘れず、思想(思うこと)、行動(なすこと)を一元的に統合しようと歩みつづけることにほかならない。これは、ふつうの意味での宗教よりも、はるかに単純で、徹底した生き方である。
人生に躓き、宗教に心の糧を求めようとする読者にとって、ヴィトゲンシュタインの生涯をつぶさに知ることから、直接に得るところがどれだけあるものなのか、私にはわからない。しかし少なくとも、ここに描かれているのは、ユダヤ=キリスト教文化圏からなら現れても不思議でないタイプの、硬質で透明な知的人間の物語なのである。“神を知らない”わが国の読者たちにとって、恐らくこれは驚きであろう。
著者は、ヴィトゲンシュタインを知る人々の証言や、ヴィトゲンシュタイン自身の著作・遺稿・書簡からの引用など、関係するテキストを丹念につなぎ合わせ、《宗教者》としての彼の生きざまを浮きぼりにした。しかも、ヴィトゲンシュタインが語っていないことがらについて、推測をまじえて不必要に語りすぎてしまうという危険を、賢明にも避けている。類書を読破したうえでの、要領のよいまとめとも見えようが、適度に抑制された筆致が、かえってヴィトゲンシュタインの非凡で身近な実像を照らし出すことに成功している。
なお、ヴィトゲンシュタインと神学との結びつきについて、著者星川氏の手になる翻訳(A・キートリー『ウィトゲンシュタイン・文法・神』法蔵館)があることを、付言しておく。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
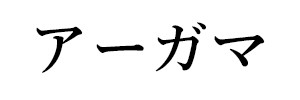
アーガマ(終刊) 1990年9月
ALL REVIEWSをフォローする





































