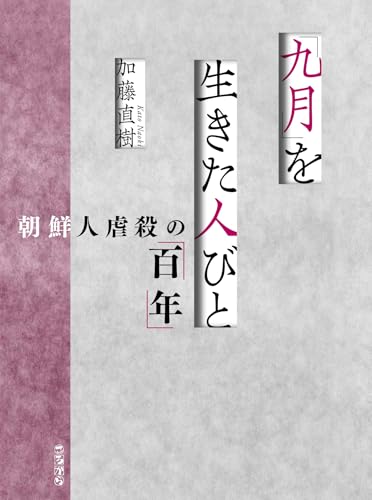書評
『日本蒙昧前史』(文藝春秋)
小説にしか描けない歴史
本書の中で扱われる事件は、一九六五年から一九八五年までの二十年間に起こる。冒頭の「グリコ・森永事件」から、続いて起こった「日航ジャンボ機墜落事故」に筆は移り、「ちょうど同じ頃、」と書き出されるのは、「買い手の付かなかった銀座五丁目の百坪ほどの土地」の物語だ。昭和史回顧番組の常連である二つの事件に比べると、銀座五丁目の話は人口に膾炙してきたものとは思えないが、「日本で初めて、坪単価一億円を超えた土地取引だった」と書かれるのを読むと、一九八五年がバブル前夜だったことを思い出す。
次のエピソードは「オリンピックが終わってほどなく」「大蔵大臣に就任」するキャバレー好きの政治家の話だ。小説内では年号も名前も明示されないが、この政治家の逸話は当時「角福戦争」と呼ばれていて、「角」が脳梗塞で倒れ、実質的に政治活動ができなくなったのも八五年だったと思い出した。
東京オリンピック後からバブル直前まで。それはたしかに、その前やその後とは区別されるべき二十年だと、同時代を生きた者として感じるものがある。
「我々は滅びゆく国に生きている、そしていつでも我々は、その渦中にあるときには何が起こっているかを知らず、過ぎ去った後になって初めてその出来事の意味を知る、ならば未来ではなく過去のどこかの一点に、じつはそのときこそが儚く短い歴史の、かりそめの頂点だったのかもしれない、奇跡のような閃光を放った瞬間も見つかるはずなのだ」。そう語り始められる、七〇年の大阪万博について読みながら、しかし、待てよ、これのどこが「かりそめの頂点」なのかと読者は訝(いぶか)るだろう。
絶望的に難航する万博用地買収、万博に電気を供給するために運転を開始し、「以降何百年も続く災厄の種を蒔」くことになる原発の操業開始、いまや頭痛の種と化しつつあるのに未来の乗り物として絶賛展示されていたリニアモーターカーといったエピソードが続くからだ。
本書に描かれる「事件」たちは、五つ子一家に猛禽類のように襲い掛かるメディアスクラムも含め、「かりそめの頂点」というより「滅びの原点」に見えなくもない。
しかし、読むうちに「過去のどこかの一点」とは、「大阪万博」ではなく、ずっと小さな一点、「太陽の塔」の右目部分に座り込んで万博反対を訴え、たいして報道もされず、力尽きて抗議を頓挫せざるを得なかった「目玉男」のことなのだと気づく。
「目玉男」の逸話は、輝かしくもヒロイックでもないが、この男の半生を微に入り細を穿(うが)ち創作した作者の筆の熱量ゆえに、胸を打つ。
その二十年が、いまよりいい時代だったのかは正直判断がつかないが、目玉男の愚行に、グアムで過ごしたのと同じくらい長い時間を帰国後生きた横井庄一の孤独に、五つ子の父の父性に、その時代を生きた人々の存在と時間を、いとおしく抱き寄せたくなる感覚を抱く。
メインのストーリーではないのだが、カメオ出演のように登場する文豪川端康成、「目玉男」に嫉妬する岡本太郎、万博の各国「ホステス」の制服から、背中にファスナーのついた怪獣を連想してしまう小学生などなどのディテールが秀逸。小説ならではの「歴史」を堪能した。第五六回谷崎潤一郎賞受賞。
ALL REVIEWSをフォローする