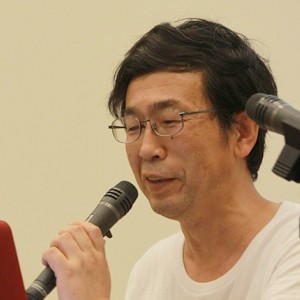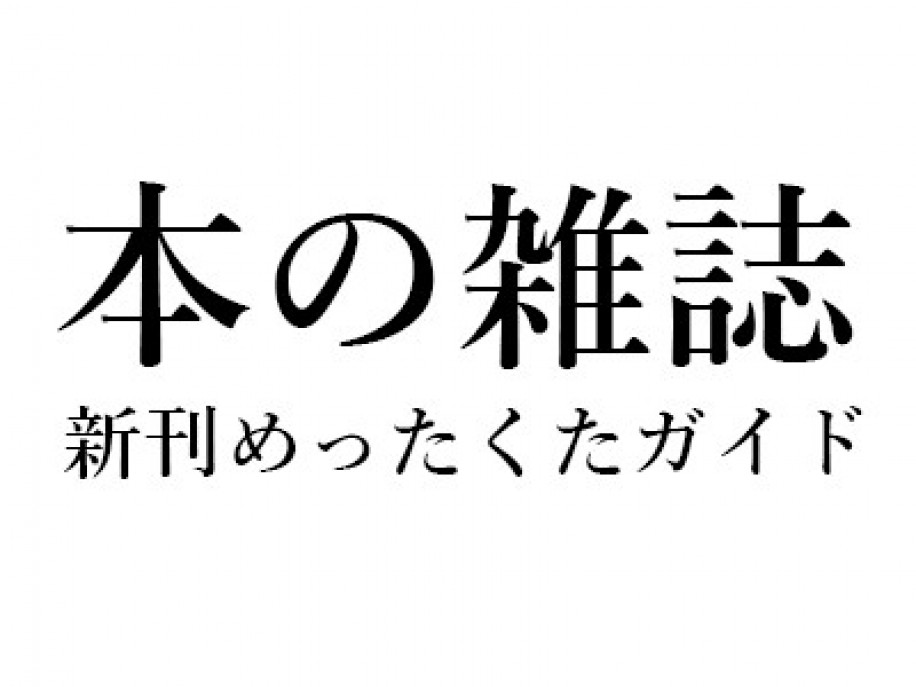書評
『指差す標識の事例 上』(東京創元社)
歴史とは何かを問う緻密な迷路
英国人は歴史小説好きである。近年でも、トマス・クロムウェルを主人公にして十六世紀の英国史を描いたヒラリー・マンテルのブッカー賞受賞作『ウルフ・ホール』をはじめとして、歴史小説がしばしば話題になっている。本書、イーアン・ペアーズの『指差す標識の事例』は、『ウルフ・ホール』より後の、いわゆる王政復古期に物語を設定し、歴史ミステリの形式を借りた作品で、歴史小説好きやミステリ好きを唸らせること必定の大傑作だと言い切ってかまわない。時は一六六三年。亡命先のオランダから戻ったチャールズ二世が復位を果たした英国は、政治的な陰謀と社会的な汚濁に満ちていた。その不安定な社会を背景にして、オックスフォード大学でグローヴ博士という人物が砒素(ひそ)によって殺害されるという事件が起こり、彼が雇っていた雑役婦のサラ・ブランディという娘が捕らえられて縛り首になる。この毒殺事件をめぐる真相が、本書のミステリ的な興味の中心である。
本書は、この事件に関わる四人の手記から成る。最初に出てくるのは、ヴェネツィアからやってきたマルコ・ダ・コーラという医学を学ぶ男で、彼の手記が公になってから、それに対する反論あるいは事実の補正として、事件当時の法学徒、幾何学教授、そして歴史学者がそれぞれ手記を綴る。
四人の手記は、意図的な欺瞞、父親の汚名を晴らそうとする妄執、愛する者を殺されたがための復讐(ふくしゅう)心から生じる推論の誤りなど、さまざまな要因から、すべてが事実の記述だとは受け取れない仕掛けになっている。前に書かれていたことが、実はそうではなかった、あるいはわざと隠蔽(いんぺい)された事実があった、ということを読者は知るたびに、ページを繰り直してたしかめることになる。上下巻を合わせて一〇〇〇ページを超えるこの大作を、そうして行きつ戻りつしながら読み進めるのは、手軽な娯楽小説を求める読者にとってはかなりの難題だが、緻密に仕組まれた迷路のようなこの小説を楽しみ、作者イーアン・ペアーズの構成力のたしかさを実感するにはそれしかない。
それでは、この小説では決定的な「真実」はどこにあるのか。歴史学者が綴る最後の手記が「真実」なのか。このアントニー・ウッドという歴史学者は、ひたすら文献を読みほどこうとする己の姿勢を守りながらも、そこに一抹の疑問を持ち、理性が人間の営みをとらえようとするときの限界を意識している。彼にとって、「歴史」の真の目的は「人間の営みに介入する神の御稜威(みいつ)を顕示すること」である。つまり、「真実」は信念の問題になってくるのだ。
こうして、本書の驚くべき結末までたどりついた読者は、「歴史」とは何だろうかという問題に直面せざるをえない。四人の語り手のうち、二人は歴史上の人物である。この他にも数多く登場する歴史上の有名人が、キャラクターとして動きまわるのは、歴史小説の楽しみの大きな部分であることは間違いないが、本書で最も印象的なのは、むしろ手記を書く役割を与えられていない、サラ・ブランディという女性の言葉とふるまいであり、歴史から切り捨てられた名もない民衆たちの姿である。それが歴史小説という枠組みを超えて、読者に感動を与えてくれる。
ALL REVIEWSをフォローする