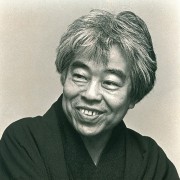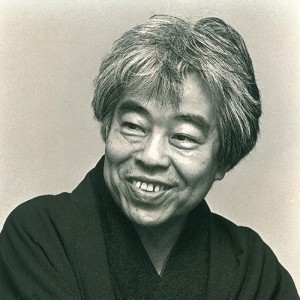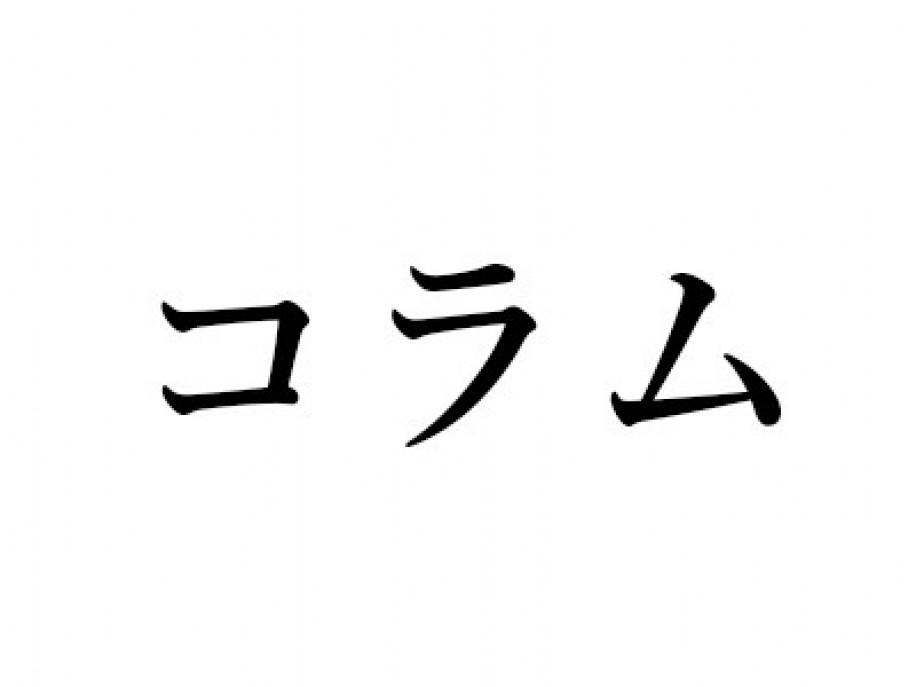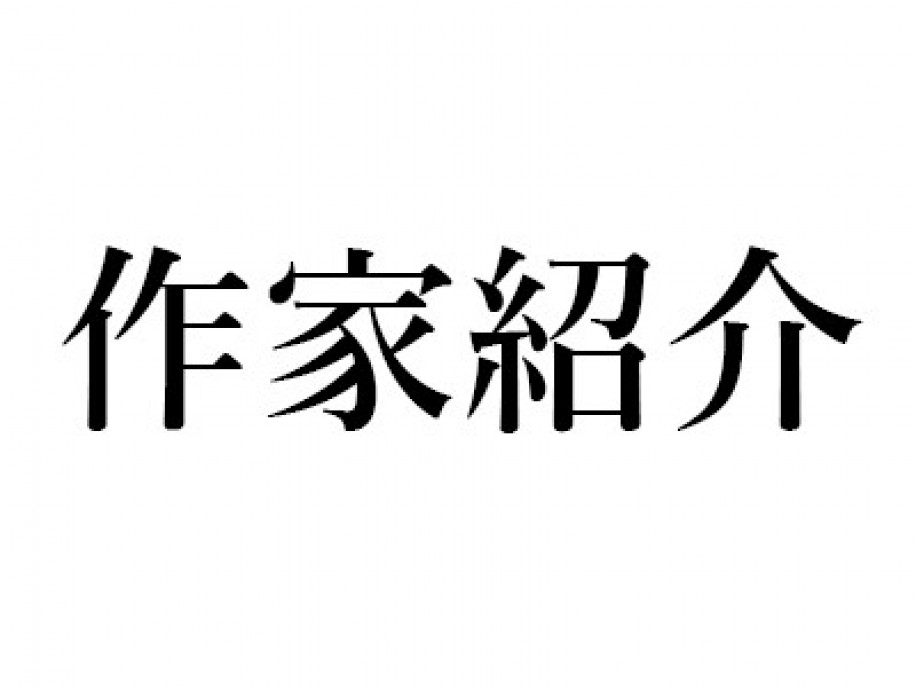書評
『人間の証明』(KADOKAWA/角川書店)
教養小説風の情報・推理小説
本格派のミステリーは、謎の構築とその論理的解明を主体とするが、同時に文学作品としても読めるものでなければならないという考えかたは、以前からあった。「高層の死角」で江戸川乱歩賞を受けて以来、本格ものの書き手として精力的な活躍をつづけてきた著者もその考えにたち、小説とよぶ以上あくまで人間が主役であると、そのエッセーの中で述べている。こうした彼の方向はこれまでの作品にもみられたが、それをいっそう明確に打ちだしただけでなく、事件や謎の解明に論理以外の人間的要素をもりこもうとしたのが、この「人間の証明」だといえよう。これは第三回角川小説賞に選ばれたが、作者にとってもその人生観や人間観を投入した野心作で、彼の代表作のひとつに数えることができよう。
世界各国の人があつまる超巨大ホテルの屋上レストランへ昇るエレベーターに、重傷を負った黒人が乗りこみ、途中で息をひきとるが、その被害者の足どりが容易につかめないといった事件からはじまり、捜査を手がける日本とアメリカのそれぞれ暗い過去をもった刑事たちの動き、それに消えた妻のゆくえを捜す男、この二つの一見無関係な話が並んで展開されるうちに、やがてひとつに結びつき、最後には刑事たちの過去までそれにからむ構成は、ミステリーとしてもみごとに筋がとおっている。
被害者の住んでいたニューヨークのスラム街や、その街の出身である刑事の姿はよく描き出されており、また被害者が持っていたと思われる西条八十の詩集をヒントに、熱心な刑事たちが山峡の霧積温泉を訪ね、さらに北越の田舎町八尾まで足をのばすなど、作品の舞台となる土地の情景も、変化に富んでいる。
そして霧積温泉の思い出をうたった西条八十の美しい詩が、事件の重要な鍵となっているあたりには、作者の詩情も感じられる。だがこの作品の主要なテーマは、親子というもっとも人間的な問題にとりくみ、一方でその親子関係の喪失と、それによる家庭の荒廃を描き出し、そこに現代社会の病痕をうつしたことであろう。そして二つの犯罪の解決を人間の証明と結びつけた点に、推理小説の枠をひろげるこころみがみられるのだ。
著者はさらに証明シリーズ第二作として「青春の証明」を書き、戦中派と現代の若者のそれぞれの青春を対比しながら、青春とは何かといった問題をミステリーの中で追求している。また「花の骸(むくろ)」では東北の出稼ぎ労務者の事件をさぐるなど、いずれも現代社会における人間の問題を積極的にとりあげている。
これらの作品がいずれもベストセラーになっているのは、情報小説としての内容に加えて、こうした人間や人生についての問いかけがあり、推理小説の魅力をも兼ねているからではないだろうか。
ALL REVIEWSをフォローする