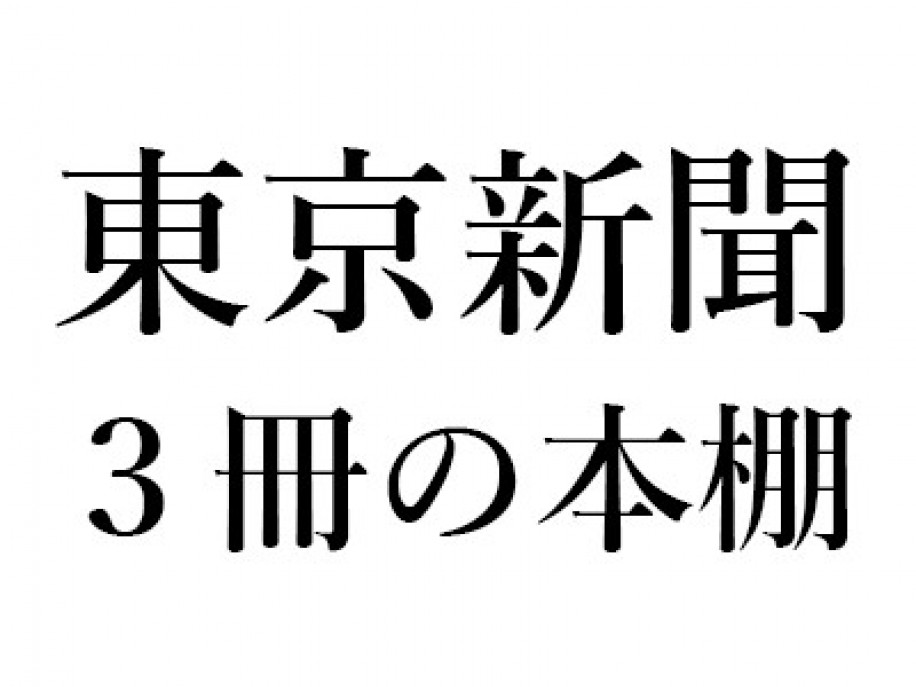書評
『思い出トランプ』(新潮社)
平凡に生きる男女の心の深淵
放送作家として長いキャリアをもつ向田邦子が、はじめて書いた小説で直木賞を受賞したのは昨年夏だが、その受賞作三篇をふくむ連作短篇集「思い出トランプ」が刊行された(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1981年)。ここに収められた十三篇は、中年男女の日常生活に影を落とすさまざまなできごとを、さりげない筆致で描きながら、そこに人生の陰翳とでもいったものを、みごとにとらえている。第一話の「かわうそ」では、脳卒中の発作を起こし、療養中の夫の目をとおして、妻の性格と行動が語られる。宅次は停年を三年後にひかえたサラリーマン、病状は右半身に軽い麻痺が残る程度だったが、厚子は悲観する様子もなく、陽気でこまめに働いている。彼女が前からときどき他愛のない嘘をつくのを、宅次もおもしろがって眺めていたが、同窓会の用事だと称し、盛装して出かけたのは、彼の意志を無視し、庭をつぶし、マンションを建てる計画のためだったとわかる。さらに彼らのひとり娘が病死したとき、厚子が医院への連絡を遅らせたことを隠していた事実も、宅次は後に看護婦から聞かされた。
宅次は厚子をふとかわうそに似ていると気づく。ひとりでに体がはしゃぎ、生きて動いていることが嬉しくてたまらないようなかわうそと同様に、厚子にとっては火事も葬式も、夫の病気も、一種のお祭りであるらしい。宅次が思わず庖丁を手にしたものの、屈託のない厚子の言葉で、夫婦の日常的な会話へ移ってしまう場面で終わっているが、作者は心理的な説明をほとんど加えず、その情景だけを淡々とした筆でうつしているのだ。
中小企業の社長が、その鈍重さにひかれて囲った娘が、彼の出張中にまぶたの整形手術を受け、イメージを変えてしまう「だらだら坂」や、飼い犬を介して近づいてきた魚屋や店員のことを、結婚して妊娠中の女性が回想する「犬小屋」なども、ユーモアの中に的確な人間観察の目が光っているのが感じられる。
「大根の月」では、やむを得ない過失で、子どもの指を切ってしまったのが原因で、夫と別居した女性を描きながら、最後にほのぼのとした情感をただよわせ、「耳」では、会社を欠勤したサラリーマンが子どもの頃、弟が中耳炎になった前後の記憶を思い浮かべる中にその異常な原因を感じとらせる。
「花の名前」は、中年の妻の前に、彼女が夫に教えたのと同じ花の名をもった女性が、いきなり現れる話であり、「ダウト」は、ダウトというトランプのゲームのように、主人公やその父の人生にひそむ嘘――かくされた汚点にふれている。
いずれも淡彩の絵の中に、一見平凡な生活を送る男女の、ドキリとするような心の深淵をのぞかせるものがあり、作者の才筆をうかがわせる。
ALL REVIEWSをフォローする