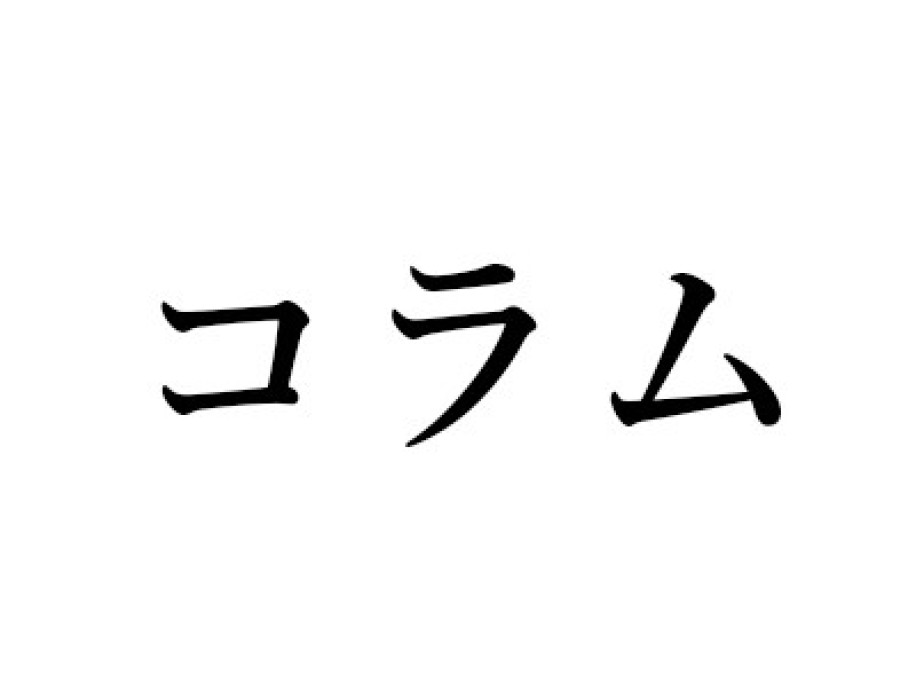解説
『ボロ家の春秋』(筑摩書房)
『ボロ家の春秋』(『梅崎春生 (ちくま日本文学全集)』(筑摩書房)収録)
空手だか柔道だか知らないが、「寸止め」というのがあるらしいじゃないか。相手の体をこぶしで殴るように見せて、体に触れるギリギリのところでピタッと止めてしまうというテクニック。なぜそういうテクニックが必要なのかわからないが、とにかくある。酔っぱらいおやじが「これが寸止めだぁ」と言ってこの技をしかけ、若い者をからかっているというのはよく見られる光景である。『ボロ家の春秋』を読んでいたら、その「寸止め」というのを思い出した。「寸止め」の妙にたんのうさせられた。
「野呂旅人(のろたびと)という名の男がいます。そいつはどこにいるか。目下僕の家に居住している。つまり僕と同居しているというわけです」という書き出しから、「亡(ほろ)びるものをして亡びしめよ。こういう悲壮(ひそう)な心境をもって、この日常のするどい緊張裡(きんちょうり)に、僕らは毎日生きているのです。御憫笑(ごびんしょう)下さい」という最後に至るまで、全編にとぼけたおかしみが漂っている。私の好きなアキ・カウリスマキの映画『ラヴィ・ド・ボエーム』や昔のつげ義春の『李さん一家』や尾崎翠の『第七官界彷徨』などにも共通する、ある匂いやおかしみである。冒頭からいきなりわくわくさせられる。
頭がいいんだか悪いんだかよくわからない、ボーッとしているわりには突然鋭いことを口走る、そんな変な人物の茶のみ話を聞かされているようだ。全編が「ゆるぎないボケ」というようなものに貫かれている。このこと自体が実にみごとである。
なぜなら、この茶のみ話の中には、下手をすると、もろに「文学的」になってしまうような、人間の心の闇とか深淵に迫っているところがあるからだ。
決して好きでも何でもない二人の男が偶然一つ屋根の下に暮らすことになる。冷ややかな距離を置いて暮らすようにしているのに、外部とのかかわりの中でついつい「被害者同士の気持の寄り合い」を感じてしまったり、ささいなことにも「闘争心だの憎悪だの」を燃やしてしまったりする。いがみ合うキッカケというのが家賃の割前であったり庭の畠のレタスであったり虫下しチョコレートであったり……非常に即物的で低次元のことなのがいい。そのために、「こんりんざいこの家を野呂だけに所有させてやるものか。全力をつくして妨害してやる」というほどに憎悪を燃やす、その憎悪のおかしさとリアリティがかえってきわだって感じられるのだ。
そうそう。話は長くなるが……梅崎春生は妙に食べものに執着しているのも面白い。『春の月』の「大根のお煮〆(にしめ)」とか。食べもの、それも高級なやつではなくごく卑俗なものである。食べものやそれから、人間のイボとかアザとか、あるいは体に合わない古着とか、非常に生理的な部分に訴えて来るものに執着している。その繊細さとしつこさに私は惹かれる。
人と人とが距離を詰め過ぎたときに生じる、何ともいえないうとましさとおぞましさ。人の心とは、エゴとは、なんと思うにまかせぬやっかいなものだろう。
と嘆くかのように見せて、茶のみ話のぬしはこう続ける。
「しかし闘争心だの憎悪だのというものは、ある意味で人間の日常を、すがすがしくまた生き生きとさせるものですな」
「僕にはその頃から自分の毎日毎日が、むしろぎっしりと充実して来るようにも感じられて来ました」
「毎日の日常がピリピリと緊張して、そのことがむしろ生甲斐を感じさせるほどでした。放って置けない相手が同じ屋根の下にいることは、実際張り合いがあるものですねえ」
最後の「ねえ」がいい、「ねえ」が。話し手も聞き手もこの「ねえ」のところで思わず顔を見合わせ、あは……と小さく笑ってしまうところだ。そこまで見えてしまったら笑うしかないなという気持で。おなかのあたりをこぶしで殴られそうになって、ハッと身構えたら、「寸止め」だったので、いきなり緊張がほどけ、つい笑ってしまったという感じである。
深刻趣味の人だったら、その先をえぐって行って、和風で行くなら「業」とか「性」の文学に、洋風で行くなら「実存」とか「不条理」の文学に仕立てるところを、この人は突き放して、ボケたおす。突けば重いものがころがり出すところを、フッと軽くしてしまう。
全編に、ほとんど細心なまでに「美徳悪徳の軽量化」がはかられている。
スリを描写するのに「財布を抜き取った手の持ち主」とあえて客観的即物的な表現をしてみたり、そのスリの逃げ方に「まことに天晴れな進退」と感心してみたり。
スリにあった人にご注進する自分を「正直に言ってそれは社会的な正義感というものではなかったようです。言うならばお節介ですか」と釈明せずにはいられなかったり、「でも、大ざっぱに言えば、人間と人間とを結び合うものは、愛などというしゃらくさいものでなく、もっぱらこのオセッカイとか出しゃばりとかの精神ではないでしょうか」とつけ加えずにはいられなかったり。
悪徳のうちに美徳を、美徳のうちに悪徳を見る。そうやってどちらも相対化し、軽量化してしまおうという強い意志が全編に感じられる。それは八〇年代以降の、いわゆる「ポスト・モダン」の相対主義=“ほんとうはインテリなのだけど明るく軽くボケてるんですよ”とは、深刻なるものへの追い詰め方において、また生理や感覚への執着においてだいぶ違うようである。自分のインテリ性を逆説的に保証するためのものではない。ほんものの「軽さ」である。
のんびりとした茶のみ話のように見えて、実は細心なまでに、そのトーンを一定しようという努力のあと(という言い方は野暮ったく、あまり適切ではないのだが)が見られる。精神の緊張がある。強い意志がある。「寸止め」の芸がある。
最後までゆるぎなくボケたおしたところ、『ボロ家の春秋』は梅崎春生の最高傑作である。たぶん、『桜島』で戦争体験を書いた、そのあとだったから書けた作品だろう。
以前、他の選集で梅崎春生のエッセーを二つ読んだことがあった。一つは六〇年安保反対デモに参加したときのレポート、もう一つは天皇制について考えていることだったが、ハッキリ言って両方ともごく良心的な「進歩的文化人」の域を出るものではなく、面白くはなかった。梅崎春生の凄さは、「Sの背中」にも見られるように、非常に言葉にしにくい生理的なというか体感的なところに執着して、その中から言葉を醱酵させてゆくところにあるようで、じかに天下国家方向のことを扱おうとすると弱点をさらけ出してしまうようだ。
しかし、この本の中の動物を題材にした二つのエッセーは両方とも面白い。私がとくに好きなのは「チョウチンアンコウについて」だ。
チョウチンアンコウは雌と雄とでは大違いで、壮大立派な外見を持った雌に較べて雄の体はその十分の一ほどしかない。小さな雄は大きな雌の体にくらいついて、ついには雌の体の一部となってしまう。そして、不要になった諸器官をどんどん消滅させてゆく、精巣だけの存在となって「全機能を発揮して、二階から目薬をさすように、その精子を海中に放出」する――。
チョウチンアンコウの雄が与える感動とは、「生きることのものすごさ」というようなものだろうか。とことん成り下がってでも唯一の目的だけは果たしてしまうという、大逆転的な行為に圧倒されてしまうのだろうか。それとも……。
と書いているうちに、私はどんどん野暮の深みにはまっている自分に気づく。言葉をつくせばつくすほど、チョウチンアンコウの雄が与える感動から遠ざかってしまう自分に気づく。
やっぱり梅崎春生のように「どういう感動かということは、うまく言えないけれども」でいいのだ。
チョウチンアンコウの雄に何だか妙に関心を燃やし、その関心の正体がついにわからず、無理して言葉でおさえこまず、だらしなく「わからない」と言ってしまう梅崎春生が、私は好きだ。私はまだまだ「寸止め」にかんしては未熟者である。
【この解説が収録されている書籍】
初出メディア
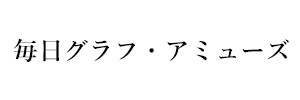
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1995年3月8日号~1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする