書評
『世界のすべての七月』(文藝春秋)
仕事柄「どんな海外文学作品を読めばいい?」という質問を受けることがよくあります。そんな時、わたしは訳者買いを薦めることにしているのです。というのも、優れた翻訳家は同時に小説のメキキスト(目利きの人)でもあるケースが多いから。英米文学なら柴田元幸さん、岸本佐知子さん、若島正さん、鴻巣友季子さん、青木純子さん、風間賢二さん、大森望さんの訳している小説なら、まずハズレなし。ちょっと癖の強い作風がお好みなら柳下毅一郎さんがお薦めです。作家の村上春樹さんもまた、ハズレなきメキキストの一人。そして、ティム・オブライエンはそんな村上さんがこよなく愛する作家なんであります。
ヴェトナム戦争と反戦運動で社会が大きく揺れ動いていた六〇年代。そんな疾風怒濤の季節に青春時代を過ごした世代が、五十代の半ばも過ぎて大学の同窓会に集っている――その様子を描いた〈1969年度卒業生〉という章の合間に、主な登場人物たちの卒業後の人生が語りおこされます。ヴェトナム戦争で片足を失ったデイヴィッド・トッド。デイヴィッドと結婚はしたものの、後年ハーレーに乗った株式仲買人と家を出てしまったマーラ・デンプシー。二人の夫の他にも愛人がいるというモテモテ人生を送りながらも、実は幼い頃に双子の妹を亡くした喪失感をいまだに埋めることができないでいるゴージャス美人のスピーク・スピネリ。そんな彼女を大学時代から愛し続けている心臓病みの太っちょ、マーヴ・バーテル。徴兵を忌避するためにカナダへ亡命し、一緒にきてくれなかったドロシー・スタイヤーをいまだに憎み続けているビリー・マクマン。ビリーを捨てた後にその親友と結婚し、何ひとつ不足ないリッチな人生を満喫していたはずなのに、乳癌で片方の乳房を切除したのをきっかけに「これでよかったのか」という懐疑を抱くようになっているドロシー。
などなど、ローリング・シックスティーズの挫折と幻滅と苦い笑いに彩られた人生の様々な軌跡を描いたこの小説を読んでいると、「オレらの若い頃はさぁ」と自慢げに闘争の日々を語る我が国の団塊の世代を忌み嫌っているわたしの胸中にすら、愛おしい気持ちがわき上がってくるから不思議です。若い季節を、ああいう躁状態気味の社会状況の中で過ごせば、そりゃあその後の平穏な人生を味気なくも感じましょうし、若き日に理想を高く掲げた世代だけに、その後の挫折感や自分に対する幻滅は深かろうと、お察し申し上げもいたしましょう。が――。
そんな風に、六〇年代に青春を過ごした、ある特殊な世代の三十年を描いた小説として、他人事のような気分で読み始めたはずなのに、いつの間にか「わたしだって、いつか五十三歳になるんだ」と我が身に引きつけて物語に没入している自分に気づくのです。エイミーとジャンという、同窓会の間中、女二人でつるんでウォッカを飲み続けている愛すべきお笑いコンビを狂言回しにして、ロンドのように展開していく全二十二章を読み終えた時、ここに登場したすべての人物を近しい友人のように感じている自分に気づくのです。大っ嫌いな世代だったはずなのに! 老いていくことの恐怖、生きてきた道のりに対する懐疑心や後悔、うまく事が運ぶことなんて万に一つもないのが人生だけど、そんなきつい人生を、それでも微(かす)かに頷(うなず)くゼスチャーで受け入れようと試みる者への共感。特定の世代の人生を描きながら、しかし、優れた小説は何かしらの普遍性を獲得するものです。そして、オブライエンはその普遍化に成功しているのです。村上春樹の紹介作品にハズレなし、の法則は今回も健在なんでありました。
【この書評が収録されている書籍】
ヴェトナム戦争と反戦運動で社会が大きく揺れ動いていた六〇年代。そんな疾風怒濤の季節に青春時代を過ごした世代が、五十代の半ばも過ぎて大学の同窓会に集っている――その様子を描いた〈1969年度卒業生〉という章の合間に、主な登場人物たちの卒業後の人生が語りおこされます。ヴェトナム戦争で片足を失ったデイヴィッド・トッド。デイヴィッドと結婚はしたものの、後年ハーレーに乗った株式仲買人と家を出てしまったマーラ・デンプシー。二人の夫の他にも愛人がいるというモテモテ人生を送りながらも、実は幼い頃に双子の妹を亡くした喪失感をいまだに埋めることができないでいるゴージャス美人のスピーク・スピネリ。そんな彼女を大学時代から愛し続けている心臓病みの太っちょ、マーヴ・バーテル。徴兵を忌避するためにカナダへ亡命し、一緒にきてくれなかったドロシー・スタイヤーをいまだに憎み続けているビリー・マクマン。ビリーを捨てた後にその親友と結婚し、何ひとつ不足ないリッチな人生を満喫していたはずなのに、乳癌で片方の乳房を切除したのをきっかけに「これでよかったのか」という懐疑を抱くようになっているドロシー。
などなど、ローリング・シックスティーズの挫折と幻滅と苦い笑いに彩られた人生の様々な軌跡を描いたこの小説を読んでいると、「オレらの若い頃はさぁ」と自慢げに闘争の日々を語る我が国の団塊の世代を忌み嫌っているわたしの胸中にすら、愛おしい気持ちがわき上がってくるから不思議です。若い季節を、ああいう躁状態気味の社会状況の中で過ごせば、そりゃあその後の平穏な人生を味気なくも感じましょうし、若き日に理想を高く掲げた世代だけに、その後の挫折感や自分に対する幻滅は深かろうと、お察し申し上げもいたしましょう。が――。
そんな風に、六〇年代に青春を過ごした、ある特殊な世代の三十年を描いた小説として、他人事のような気分で読み始めたはずなのに、いつの間にか「わたしだって、いつか五十三歳になるんだ」と我が身に引きつけて物語に没入している自分に気づくのです。エイミーとジャンという、同窓会の間中、女二人でつるんでウォッカを飲み続けている愛すべきお笑いコンビを狂言回しにして、ロンドのように展開していく全二十二章を読み終えた時、ここに登場したすべての人物を近しい友人のように感じている自分に気づくのです。大っ嫌いな世代だったはずなのに! 老いていくことの恐怖、生きてきた道のりに対する懐疑心や後悔、うまく事が運ぶことなんて万に一つもないのが人生だけど、そんなきつい人生を、それでも微(かす)かに頷(うなず)くゼスチャーで受け入れようと試みる者への共感。特定の世代の人生を描きながら、しかし、優れた小説は何かしらの普遍性を獲得するものです。そして、オブライエンはその普遍化に成功しているのです。村上春樹の紹介作品にハズレなし、の法則は今回も健在なんでありました。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
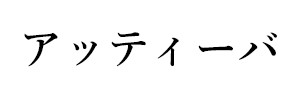
アッティーバ(終刊) 2004年6月号
ALL REVIEWSをフォローする





































