書評
『継母礼讃』(中央公論新社)
ラテンアメリカの代表的作家による実験的な官能小説
ジョルジュ・バタイユの『眼球譚』について長篇エッセーを書いていることでも分るように、バルガス=リョサはエロティシズムに対する関心をその作品の中で常に明らかにしてきたが、『継母礼讃』も基本的にはフランス・シュルレアリスムの系譜に連なる官能小説といえるだろう。彼はかつてフランスの作家になりたかったと告白している。ブルジョワ階級に属する男とその息子である金髪の美少年、そして熟した肉体が強烈なエロスの香りを放つ美しい後妻の三角関係というのは、フランスやイタリアの映画が好んで用いる構図でもある。実際、著者が舞台にしたのは、リマのヨーロッパ的世界であり、それはインディオの住む土着的ペルーとは無縁の別世界である。主人公リゴベルトの屋敷はその意味で一種の人工楽園、さかしまな世界ともいえる。
互いの肉体に酔い痴れるリゴベルトと妻ルクレシア。だが、人工楽園はもろく、三角形は必ず壊れる。天使のような少年アルフォンシートが悪魔的な顔を見せ、エデンの園の蛇のように美貌の継母を誘惑するのである。
ストーリーの単純な小品であり、下手をすれば有名作家の手遊びで終ってしまうところだが、さすがバルガス=リョサと思わせるのは、ここに平板さを防ぐ仕掛けを施したことである。彼は美術史上有名な六枚の絵をさしはさむことで、作品を重層化したのだ。
リゴベルトやルクレシアの見る夢にヨルダーエンス、ブッシェ、ティツィアーノの絵が重なることで、現実はにわかに神話性を帯びてくる。たとえば妃ギゲスの肉体を自慢するリディア王、カンダレウスが彼女の沐浴を大臣に覗き見させるというエピソード。これは絵画そのものの鑑賞ともなっているが、そこに見られるヴワユリズム(視姦)というモチーフは、小説のストーリーの伏線となり、宿命的な結末を暗示する働きをしている。
もちろんフランシス・ベーコン、シシュロ、フラ・アンジェリコの絵も効果的に使われているし、細かい仕掛けを挙げだしたらきりがない。バルガス=リョサはエンターテインメントにおいても実験してしまうのだ。
この作品にはリゴベルトの沐浴や排泄行為など、ケベードを想わせる場面がある。あるいはグロテスクな誇張からバリェ=インクランの名を出してもいい。こうした事実はスペイン文学という、バルガス=リョサのもうひとつの文学的ルーツを明らかにしている。そう、彼は偉大なるスペイン・リアリズムの継承者でもある。
この物語の時代は近過去だろう。にもかかわらず、出来事ははるか昔のことのように感じられもする。それは神話性を持ち込むことで、リマという古都に流れる古い時間を著者が表現しえたからにちがいない。植民地時代から流れる時間。『世界終末戦争』で前世紀末を描いたことにより、彼はこの古い時間をつかんだようだ。
初出メディア
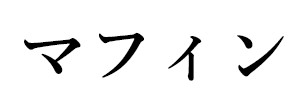
マフィン 1991年1月
ALL REVIEWSをフォローする





































