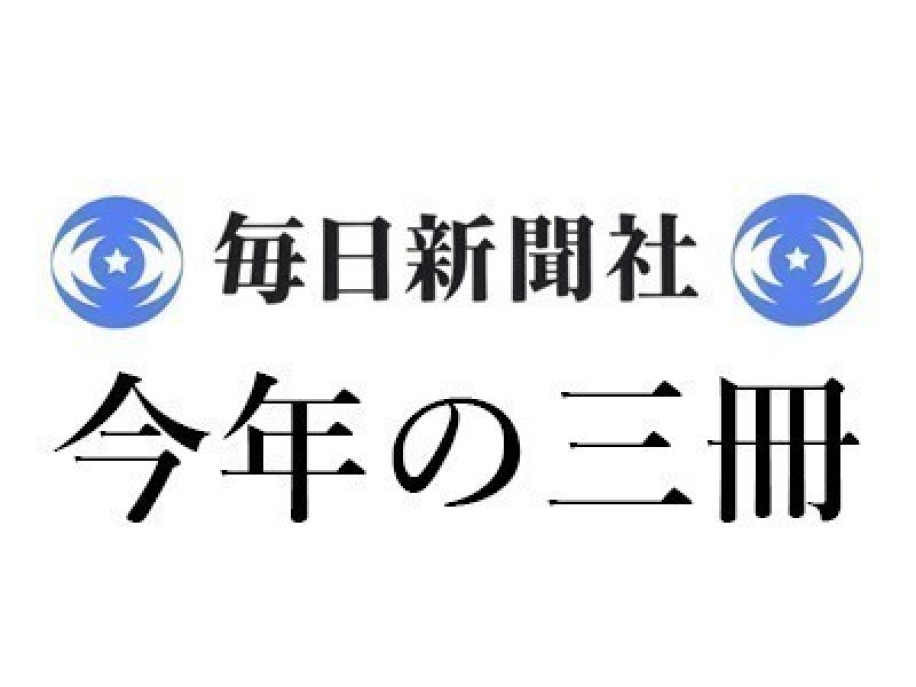書評
『南の島に雪が降る』(筑摩書房)
人はなぜ劇場を必要とするか
ごく最近、ある一冊の本にまつわる二つの出来事、というほど大げさなことでもないが、立て続けに出くわして、ちょっといい思いをした。一冊の本というのは、「わたしが召集に接したのは、楽屋の鏡のなかであった」とはじまる、今は亡き俳優加東大介の戦争体験記『南の島に雪が降る』だ。彼の父は歌舞伎狂言作者加藤伝太郎。兄に沢村国太郎、姉に沢村貞子がいて、長門裕之、津川雅彦は国太郎の息子だ。
加東は、戦前の前進座に参加して、道頓堀・中座出演中に召集をうけ、ニューギニア島マノクワリに送られる。戦局は悪化の一途をたどり、兵士たちは飢えとマラリアで次々と死んでいった。まもなく敵の一斉上陸がはじまるというので、マノクワリに残った兵士の半分近い一万人が南部パボにむかって退却する。これが、ほぼ全員が飢えとマラリアで死んだ有名な“ニューギニア死の行進”だ。
玉砕組として残された約八千人の兵の中に俳優加東大介がいた。どうせ敵の上陸が近い、死ぬにきまってるんだ。すさんでゆく兵士たちを慰めるため、加東を中心に演芸分隊が発足する。マノクワリ歌舞伎座がジャングルの中に建てられる。
昭和二十年四月から二十一年四月までの一年余、一日も休まず幕を開けつづけたマノクワリ歌舞伎座の創立から終焉までが、生前の映画や舞台の、加東大介の独特な早口のセリフ回しをほうふつさせるような、闊達であたたかな筆致で綴られるのだが、読みながら目頭が熱くなり、活字が遠くかすんでしまう回数も数えきれない。まさに出色の戦争体験記なのだ。また別に、人間がなぜ芝居や劇場を必要とし、かつどのようにして役者・俳優というものが生まれてくるのか、そこのところの原点らしきものを感動的に伝えてもくれるのだ。
なかに、岸田国士の名作「暖流」を上演する話がある。出征前、吉村公三郎監督、佐分利信、高峰三枝子主演の映画「暖流」が好きで何十回もみて、セリフはおろかシーンの移り変わり、カットわり、登場人物の動き、場所や小道具まで完全に覚えている兵士がいて、彼が再現したシナリオにもとづいて上演して大うけする。
「暖流」がかかっている時は、入場開始と同時にうんと下手に寄ったかぶりつきにむかって兵隊たちが突進する。第九景、鎌倉海岸、日疋裕三役は加東大介軍曹、日疋を慕う看護婦石渡ぎん役は斎木という上等兵。下手のかぶりつきから、波打ち際にしゃがんだ石渡ぎんのスカートのなかがみえる。それで席の取りっこがおきる。
僕がこの本を読んだのはもうひと昔も前のことだが、吉村公三郎の映画「暖流」は、先日ビデオでみることができた。傑作だ。しかし、これをニューギニアのジャングルで飢えとマラリアに苦しみながら兵士たちが演じ、観たのだと思うと、のんきな鑑賞気分も吹きとんでしまった。
さてもうひとつ。「サピオ」の2月5日号、小林よしのりの「新・ゴーマニズム宣言」を開いて驚いた(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆年は1997年頃)。マノクワリ歌舞伎座座長加東大介の片腕で、みながいやがるカタキ役を一手に引き受けていたいかつい顔の男がいた。彼は僧侶で、和尚はほんとうに大物だった、と加東は書いているが、じつはこの人、小林のおじいさんなのだ。
小林は、この本のクライマックス、「関の弥太っぺ」甲州街道・吉野宿、幕が開いて一面銀世界の舞台をみたとたん、三百人の兵士が一瞬声をのみ、それから嗚咽(おえつ)する場面を、おじいさんへの哀悼をこめて、誌上で再現している。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする




![暖 流 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41HSGqUdUzL.jpg)