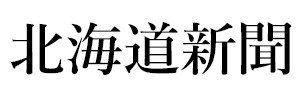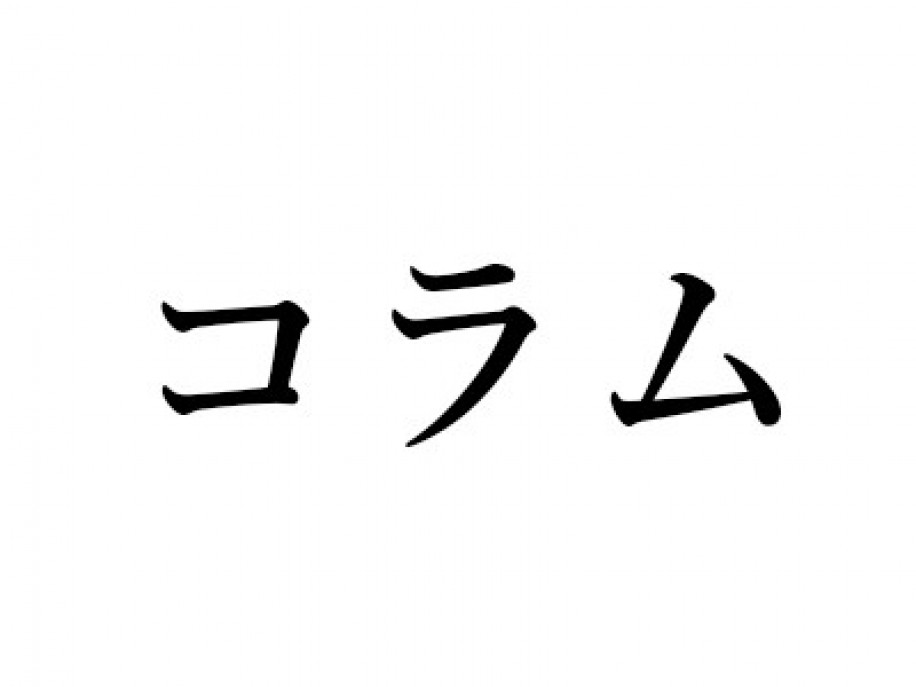書評
『わが「転向」』(文藝春秋)
『わが「転向」』とはショッキングな題だが、これは編集者のつけたもの。中身は著者・吉本氏の素直な述懐である。
著者の思想遍歴をまとめてみると、こうなる。①軍国少年・吉本氏は、戦争で死んでもいいと思いつめていた。②敗戦で、正義の戦争が実は愚劣だったと思い知らされたが、憲法九条と引きかえならいいと思った。③安保では醒めていたが、学生を理解できたので行動を共にした。④七二年ごろを境にマルクス主義・左翼が効力を失ったので、大衆文化や都市と本格的取り組み現在に至った。――戦後をリードし続けた氏の遍歴に、柔軟さと強靭さの類まれなバランスを感じる。氏に異論を挟む人びとさえ、自分の位置を測るのにこっそり吉本氏を参照している場合が多い。
吉本氏は「冷戦体制が崩壊するずっと以前に、マルクス主義・左翼思想の解体を実践した思想家」として、後世から評価されることになろう。氏は全学連主流派を評して、《ソビエトとアメリカという両体制……双方から押し潰されず、どちらの様式も取らなかったという意味では、彼らのやり方はいちばん妥当なもの……でした》(一一頁)とのべている。これは吉本氏自身のことでもある。氏の歩みは、知的世界のなかにその表現を与えられないまま、黙々と戦後の現実を築きあげてきた無名の大衆の営為を代弁した。このことは、氏が左翼の官僚制に反対し、《大衆の原像》にこだわり続けたことと符合する。
私が吉本氏に感じる唯一の異和は、氏が権力を肯定する論理をいっさい持ち合わせていないことだ。政府をリコールできることが大切だとか、自衛隊を合憲と言うべきでないとか、政治の終焉(政治が町内のゴミ当番みたいなものになること)をイメージすべきだとかいった部分に、戦後の刻印を感ずる。
柄谷行人、浅田彰氏らが吉本氏の「転向」を批判したのに対し、氏は《マルクス主義の否定的批判をしない……姑息な知識人》と切り返した。両者のどちらに分があったか、いずれ歴史が裁定を下すに違いない。
【この書評が収録されている書籍】
著者の思想遍歴をまとめてみると、こうなる。①軍国少年・吉本氏は、戦争で死んでもいいと思いつめていた。②敗戦で、正義の戦争が実は愚劣だったと思い知らされたが、憲法九条と引きかえならいいと思った。③安保では醒めていたが、学生を理解できたので行動を共にした。④七二年ごろを境にマルクス主義・左翼が効力を失ったので、大衆文化や都市と本格的取り組み現在に至った。――戦後をリードし続けた氏の遍歴に、柔軟さと強靭さの類まれなバランスを感じる。氏に異論を挟む人びとさえ、自分の位置を測るのにこっそり吉本氏を参照している場合が多い。
吉本氏は「冷戦体制が崩壊するずっと以前に、マルクス主義・左翼思想の解体を実践した思想家」として、後世から評価されることになろう。氏は全学連主流派を評して、《ソビエトとアメリカという両体制……双方から押し潰されず、どちらの様式も取らなかったという意味では、彼らのやり方はいちばん妥当なもの……でした》(一一頁)とのべている。これは吉本氏自身のことでもある。氏の歩みは、知的世界のなかにその表現を与えられないまま、黙々と戦後の現実を築きあげてきた無名の大衆の営為を代弁した。このことは、氏が左翼の官僚制に反対し、《大衆の原像》にこだわり続けたことと符合する。
私が吉本氏に感じる唯一の異和は、氏が権力を肯定する論理をいっさい持ち合わせていないことだ。政府をリコールできることが大切だとか、自衛隊を合憲と言うべきでないとか、政治の終焉(政治が町内のゴミ当番みたいなものになること)をイメージすべきだとかいった部分に、戦後の刻印を感ずる。
柄谷行人、浅田彰氏らが吉本氏の「転向」を批判したのに対し、氏は《マルクス主義の否定的批判をしない……姑息な知識人》と切り返した。両者のどちらに分があったか、いずれ歴史が裁定を下すに違いない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする