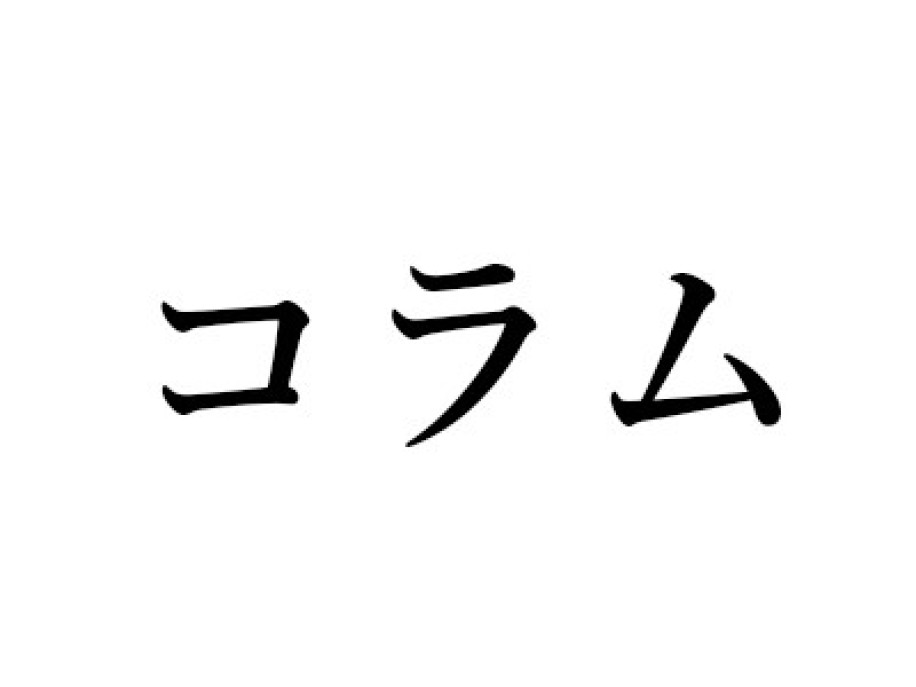インタビュー
『世界史のなかの東南アジア【上巻】―歴史を変える交差路―』(名古屋大学出版会)
近年の東南アジア史研究を牽引してきた歴史家アンソニー・リード。東南アジア全域の歴史を先史時代から現代まで一人で書き上げた畢生の大作、『世界史のなかの東南アジア』上下巻が邦訳された。本書では、国家を歴史の主役とするのではなく、環境、ジェンダー、非国家社会に焦点を当て、文字にされない表演――踊り、詠唱される詩、演劇、音楽など――や商業、宗教などの叙述を通じて地域全体の歴史的ダイナミズムを描いている。
出版までの経緯や、この地域の歴史を語ることの意義について、監訳者の太田淳/長田紀之が原著者にインタビューした。
――どうしてこの本を書こうと思い立ったのですか?
The Age of Commerce in Southeast Asia(邦訳『大航海時代の東南アジア』)第1巻を出した少し後の1990年に、ブラックウェル社の編集者ロバート・ムーア氏から、同社の「世界の歴史」シリーズで東南アジアについて書いてみないかと話がありました。面白い企画だと思ったので、その年のうちに契約書に署名して前金を受け取りましたが、時間がかかるということも同時に伝えました。この地域の全史をまとめるのは一生分の仕事のようなものであり、キャリアのあまり早い時期に取り組むべきではないと考えたからです。しかし私は1990年代には多くの仕事を抱えていて、東南アジア経済史プロジェクト、華人ディアスポラ・プロジェクト、トヨタ財団の支援を受けた東南アジアの自律国家による「最後の抵抗」プロジェクトも運営していました。1999年からは、UCLAでの新しい挑戦[聞き手注:同大・東南アジア研究所の初代所長を務めたこと]もありました。そこで2000年頃に、執筆が大幅に遅れていることについてブラックウェル社に謝罪を伝えて、前金も返そうとしました。しかし彼らはそれを断り、私に引け目を感じさせた上で、好きなだけ時間をかけてかまわないと返事をくれました。最終的にその仕事に取り組めたのは私が2009年に引退した後のことで、契約から出版(2015年)まで25年(!)もかかってしまいました。
一人の著者が単独で[東南アジアという]地域の歴史を描き、自らのヴィジョンを表現するというのは、とくに挑戦的でワクワクすることでした。一人の外部者として、私は一国史を書くためにはこれをやろうとは思わなかったでしょう。しかし東南アジアはもっと開かれたフィールドなので、そこでは著者が重要だと考える色々なテーマを、あまり問題を引き起こすことなく選べます。
――国家よりも、環境や女性、非国家社会に注目したのはどうしてですか?
エリートはもっとも明確な書かれた記録を残すものですが、私は自分の仕事人生を通じて、社会のもっと広い横断面(クロス・セクション)を示す歴史を書くための方法を模索し続けてきました。私はこの本が、その方向に進むための一歩になることを願っています。私が東南アジアについて強調したいもっとも重要な要素をひとつだけ挙げるとするならば、この地域が、おもに環境的要因によって、強力な官僚制国家が生まれるのを拒んできたこととなるでしょう。そこから、他の多くの特徴が生まれています。そのひとつである多元性(プルーラリズム)は、とくにナショナリストが国家の強さについて確認するために過去を見ようとする時には、しばしば弱さと受け取られがちですが。
――原著出版後の東南アジアの状況を、どう見ていますか?
私は基本的に、人生についてポジティブで楽観的でいられることが好きで、特に東南アジアについてはそうです。もっとも私は、[オーストラリアのインドネシア史学者]ロバート・クリブがある本でそう指摘するまで、これが私独自のものだと気づいていなかったのですが。私はたしかにこの通史を1941年や1975年で終えるべきではないと主張し、1990年代後半の民主化まで書いたのですが、それはおもに、ものごとをポジティブに終えることを私が好むからです。たしかに2015年以降は、とくにビルマやタイで深刻な[民主化の]後退があります。もし私がいまこの本を書いているとすれば、これらのことを考慮に入れるでしょうが、同時に両国で軍のクーデタに対して民衆の抵抗が広がっていることに、楽観主義の根拠を見いだしてもいたでしょう。そしてこのことは、一種の多元的な民主化がこの地域に根づきつつあることを示すとも書いていると思います。
[話し手]アンソニー・リード(1939年生まれ。オーストラリア国立大学名誉教授。東南アジア史研究)
[聞き手]太田淳/長田紀之(監訳者)
出版までの経緯や、この地域の歴史を語ることの意義について、監訳者の太田淳/長田紀之が原著者にインタビューした。
失われることのない多元性
東南アジア地域全史という挑戦
――どうしてこの本を書こうと思い立ったのですか?
The Age of Commerce in Southeast Asia(邦訳『大航海時代の東南アジア』)第1巻を出した少し後の1990年に、ブラックウェル社の編集者ロバート・ムーア氏から、同社の「世界の歴史」シリーズで東南アジアについて書いてみないかと話がありました。面白い企画だと思ったので、その年のうちに契約書に署名して前金を受け取りましたが、時間がかかるということも同時に伝えました。この地域の全史をまとめるのは一生分の仕事のようなものであり、キャリアのあまり早い時期に取り組むべきではないと考えたからです。しかし私は1990年代には多くの仕事を抱えていて、東南アジア経済史プロジェクト、華人ディアスポラ・プロジェクト、トヨタ財団の支援を受けた東南アジアの自律国家による「最後の抵抗」プロジェクトも運営していました。1999年からは、UCLAでの新しい挑戦[聞き手注:同大・東南アジア研究所の初代所長を務めたこと]もありました。そこで2000年頃に、執筆が大幅に遅れていることについてブラックウェル社に謝罪を伝えて、前金も返そうとしました。しかし彼らはそれを断り、私に引け目を感じさせた上で、好きなだけ時間をかけてかまわないと返事をくれました。最終的にその仕事に取り組めたのは私が2009年に引退した後のことで、契約から出版(2015年)まで25年(!)もかかってしまいました。
一人の著者が単独で[東南アジアという]地域の歴史を描き、自らのヴィジョンを表現するというのは、とくに挑戦的でワクワクすることでした。一人の外部者として、私は一国史を書くためにはこれをやろうとは思わなかったでしょう。しかし東南アジアはもっと開かれたフィールドなので、そこでは著者が重要だと考える色々なテーマを、あまり問題を引き起こすことなく選べます。
社会のもっと広い横断面を示す歴史を書く
――国家よりも、環境や女性、非国家社会に注目したのはどうしてですか?
エリートはもっとも明確な書かれた記録を残すものですが、私は自分の仕事人生を通じて、社会のもっと広い横断面(クロス・セクション)を示す歴史を書くための方法を模索し続けてきました。私はこの本が、その方向に進むための一歩になることを願っています。私が東南アジアについて強調したいもっとも重要な要素をひとつだけ挙げるとするならば、この地域が、おもに環境的要因によって、強力な官僚制国家が生まれるのを拒んできたこととなるでしょう。そこから、他の多くの特徴が生まれています。そのひとつである多元性(プルーラリズム)は、とくにナショナリストが国家の強さについて確認するために過去を見ようとする時には、しばしば弱さと受け取られがちですが。
多元的な民主化が根づきつつある
――原著出版後の東南アジアの状況を、どう見ていますか?
私は基本的に、人生についてポジティブで楽観的でいられることが好きで、特に東南アジアについてはそうです。もっとも私は、[オーストラリアのインドネシア史学者]ロバート・クリブがある本でそう指摘するまで、これが私独自のものだと気づいていなかったのですが。私はたしかにこの通史を1941年や1975年で終えるべきではないと主張し、1990年代後半の民主化まで書いたのですが、それはおもに、ものごとをポジティブに終えることを私が好むからです。たしかに2015年以降は、とくにビルマやタイで深刻な[民主化の]後退があります。もし私がいまこの本を書いているとすれば、これらのことを考慮に入れるでしょうが、同時に両国で軍のクーデタに対して民衆の抵抗が広がっていることに、楽観主義の根拠を見いだしてもいたでしょう。そしてこのことは、一種の多元的な民主化がこの地域に根づきつつあることを示すとも書いていると思います。
[話し手]アンソニー・リード(1939年生まれ。オーストラリア国立大学名誉教授。東南アジア史研究)
[聞き手]太田淳/長田紀之(監訳者)
ALL REVIEWSをフォローする