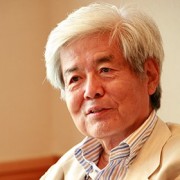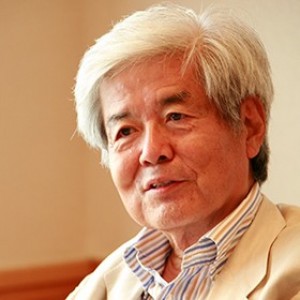書評
『土を育てる: 自然をよみがえらせる土壌革命』(NHK出版)
農業の歴史一万年を掘り起こす
自然は別に理想的にできているわけではない。想像しがたいほどの長い年月を経てひとりでに(自然に)成立したものである。本書はアメリカの農家ができるだけ自然に従って、つまり不耕起で化学肥料、殺虫剤、除草剤を使用せず、農業と畜産業を始めて、実際に採算が取れるに至るまでの考え方といきさつを記している。成功物語としても面白く、将来の農業を考える上で、乾燥地帯かつ大規模農業の話とはいえ、日本での農業にとっても、大いに参考になると思う。
タイトルにあるように、著者の考え方の中心にあるのは、「土」である。巻頭に何枚もの写真があるが、写真とその解説を読んでいるだけで、全体を把握できてしまうと思う。
世界のあちこちを旅して思うことだが、ほとんどの川が茶色く濁っている。これは流域の土が流出しているからで、巻頭の二枚目の写真には「自生の牧草地を流れる水はこんなにも澄んでいる」と解説されている。高校生のころ、屋久島に昆虫調査に行った専門家に「豪雨が降っても屋久島の川は濁らないんだよ」という話を聞いた。人がかく乱しない土地では、土は流出しないんだなあ、と当時思った覚えがある。
雨として降った水はもちろん土の中を流れるわけで、そこには流路つまり構造がなければならない。土の中にも、小さな川のような立体的な網の目状の水路が細かくできており、それが次第に合流して、地上に出れば目に見える川となるのであろう。網目の間の土の塊を著者は団粒構造と呼んでいるようである。そこには多くの細菌、菌類ほかの土壌生物が住んでいる。
アメリカでやっている農業が、日本でもうまくいくのだろうか。そう思った人はまず序章の「日本版に寄せて」をお読みください。土地によって事情が違うことを、著者は百も承知である。だから続いて、土の健康を保つために五つの基本原則を挙げる。これは第7章「土の健康の5原則」でより詳述される。(1)土をかき乱さない、(2)土を覆う、(3)多様性を高める、(4)土の中に「生きた根」を保つ、(5)動物を組み込む。六つ目を挙げるとすれば、収益性を含めて、その土地の背景に適応することである。
第9章「土さえあればうまくいく」では、著者以外の成功例が報告される。大工や消防士など農業の素人がはじめた例もいくつかある。有機農業の場合それぞれ土地の事情がまったく違うことが多いので、どうしても個別の例を列挙することになる。これは日本の場合でも同じである。
読了して思う。農業の歴史一万年の間、土をさんざん掘り返してきて、それこそが農業だと思わされて来たが、今になって掘り返さないほうがよかったんだと言われると、一瞬啞然(あぜん)としてしまう。評者自身は自分で農業に携わっているわけではない。だから本書を参考にして具体的に何かしようと思ってはいない。ただ書物として読んだだけなのに、たいへんに面白かっただけではなく、良い経験をしたと感じられた。それは著者が自己の体験を通じて素直に語ることで、農業だけではなく、何か新たな仕事を始めるときの心構えや原則を言外に教えてくれるからだと感じる。
ALL REVIEWSをフォローする