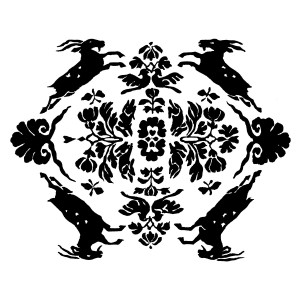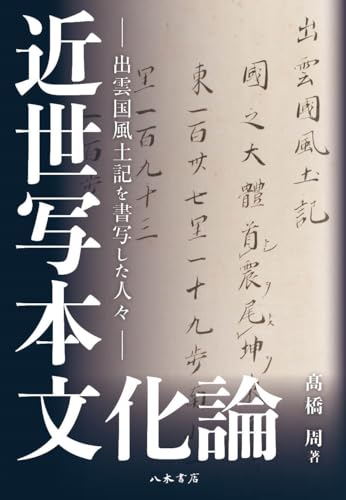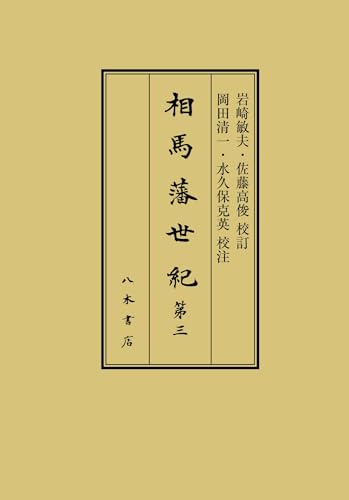自著解説
『日本古代王権と貴族社会』(八木書店)
古代国家を運営していたのは誰か。奈良・平安時代の王権を構成した太上天皇・皇后・皇太后、さらに王権を補完した貴族層に注目し浮き彫りとなった、権力抗争の真実とは――
このドラマでは、源頼朝の挙兵に始まる源平合戦、頼朝死後の権力抗争、さらには承久の乱といった見所がいくつもあった。その中で、後白河法皇・後鳥羽上皇と鎌倉武士の関係が鮮やかに描かれていた。例えば、北条義時の兄・宗時が坂東武者中心の世を作りたいと、義時に打ち明けるシーンなどである。
これは専門的に言うと、鎌倉武士が京都の朝廷から独立した立場を有していたという「東国国家論」にもとづく解釈と考えられる。これに対して、天皇・院・摂関を中心とする公家政権、幕府(武家政権)、寺社勢力が中世の国家機能を分掌しつつ、相互補完的に国家支配を行っていたとする「権門体制論」がある。
東国国家論か、あるいは権門体制論か。中世の国家をどのような枠組みで理解するかは、大変重要な問題といえよう。
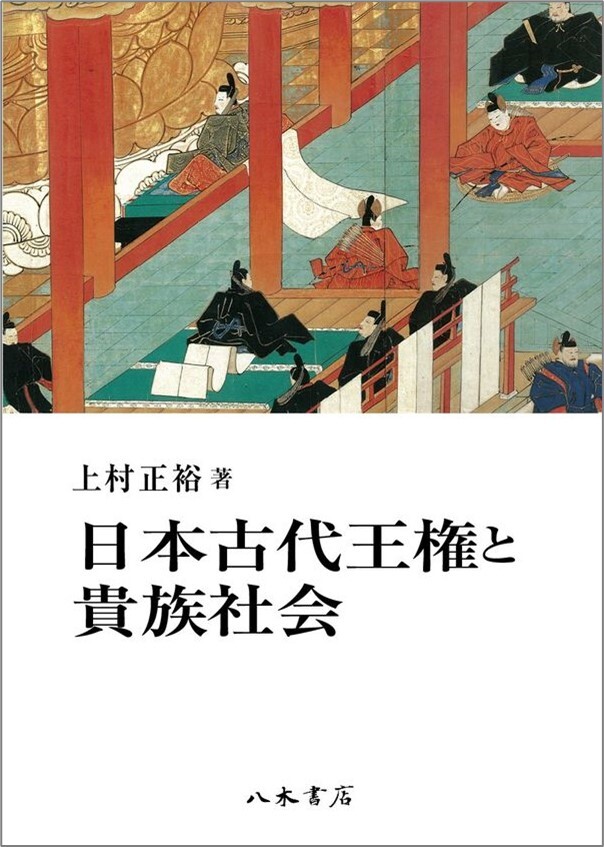
王権論とは、天皇や天皇制に限定せず、王を王たらしめている権力を分析する概念であり、構造や制度からその実像を明らかにするものである。つまり、天皇の権力を支える存在を見いだす指標として様々な材料を検討するというもので、その対象としては、太上天皇、皇后(皇太后)、皇太子などが想定される。上記の権門体制論はこれに近い考え方といってよい。
詳細は『日本古代王権と貴族社会』をご覧いただきたいが、本書の刊行により、8・9世紀の太上天皇と皇后・皇太后の特質やその変遷を示すことができた。とくに奈良時代の太上天皇や皇后・皇太后は天皇の政治を支える立場にあり、決して二重権力のような存在ではなかったことは強調しておきたい。この要因としては、奈良時代における天皇は単独での権威が不十分で、王権の多極構造を構成することが肝要であったためであると考えており、それが徐々に変質していくのが、平安時代に向けた道のりなのである。
今日では閣議や国会審議があり、国家の重要案件は会議で決めるというのが前近代以来、歴史の常だった。過去にも例えば、明治天皇の面前で岩倉具視と山内容堂が大政奉還をした徳川慶喜に辞官納地を求めるかどうかで応酬があった小御所会議が知られている。
さかのぼって、古代の皇位継承についても推古天皇の後継者をめぐって合議があったことが、『日本書紀』に記されている。
ところが、政策決定に伴う合議が奈良・平安時代前期の8・9世紀においてどのように行われたのか、その実情を語る史料は少ない。そこで本書では、8・9世紀の皇位継承決定の合議がどのように実施されているかを検討した。その結果、いわゆる「参議」ではない人々が8世紀の合議に関与しているものの、9世紀になると排除されていくということが明らかになった。
私は天皇のもとに結集する奈良時代の貴族層、特に合議に参加する「議政官」と呼ばれる人々も、後の平安時代の公卿とは異なる階層だったと考えている。王権論と貴族論を融合した上で考えた結果、いずれの視点でみても、「過渡期としての奈良時代」と位置づけるのが妥当である。つまり、「律令国家」はまだ奈良時代では完成していなかったといえるだろう。このように考えると、教科書とは異なる古代史像が見えてくるのではないだろうか。
これらの歴史的事実から天智系の革新性が強調されてきたが、この点について私は疑問に思っており、大きな画期は称徳天皇の頃より生じていたと考えている。例えば、称徳天皇は生前皇太子を置かず、道鏡即位を計画した。称徳天皇と道鏡の関係は尾ひれがつき、不適切な男女関係が説話を通して流布することになるが、史料に即して検討すると、道鏡は天皇に次ぐ地位を保持していたことが明らかとなった。さらに、称徳天皇は自らの側近を形成しつつ、藤原氏を中心とした公卿とも友好関係を結ぼうと努力していた。
実は桓武天皇も同様なあり方を考えており、皇位継承は天皇自らが決定するという方針を打ち出し、それを支える側近を集積していた。専制権力をどのように維持するか、桓武天皇は称徳天皇のあり方を学びつつ、反省もしていたのではないだろうか。奈良・平安時代の断絶性より継続性を見いだすというのが、私の考えである。
王権論を他の時代や地域で考えたらどうなるか。この視点で、本書では古代から近代、さらには東アジアの王権に関するコラムを収録している。あくまでも私のスケッチに過ぎないが、今後幅広い議論が展開されていく「のろし」となることを期待している。
[書き手]
上村 正裕(うえむら まさひろ)

1987年 茨城県生まれ
2012年 東洋大学文学部卒業
2021年 東洋大学大学院博士後期課程修了
現在 東洋大学文学部・フェリス女学院大学文学部・武蔵大学人文学部非常勤講師・京都芸術大学通信教育部業務担当非常勤講師
〔主な著作〕
『日本古代王権と貴族社会』(八木書店、2023年)
「田植御覧の成立と展開」(『人民の歴史学』234、2022年)
「伴善男の伴氏再編計画」(『続日本紀研究』427、2022年)
「葬司の基礎的考察―律令官人の一断面―」(『白山史学』56、2020年)
「八・九世紀遣使攷」(『続日本紀研究』416、2019年)
「平安時代の興福寺維摩会と藤原氏」(『国史学』223、2017年)
「鎌倉殿の13人」の世界
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が2022年12月に放送を終了した。ネタバレになるので結末は記さないが、三谷幸喜氏の脚本やドラマ制作陣の演出は細部にまで行き届いており、魅了された視聴者も多かったことだろう。私もその1人である。このドラマでは、源頼朝の挙兵に始まる源平合戦、頼朝死後の権力抗争、さらには承久の乱といった見所がいくつもあった。その中で、後白河法皇・後鳥羽上皇と鎌倉武士の関係が鮮やかに描かれていた。例えば、北条義時の兄・宗時が坂東武者中心の世を作りたいと、義時に打ち明けるシーンなどである。
これは専門的に言うと、鎌倉武士が京都の朝廷から独立した立場を有していたという「東国国家論」にもとづく解釈と考えられる。これに対して、天皇・院・摂関を中心とする公家政権、幕府(武家政権)、寺社勢力が中世の国家機能を分掌しつつ、相互補完的に国家支配を行っていたとする「権門体制論」がある。
東国国家論か、あるいは権門体制論か。中世の国家をどのような枠組みで理解するかは、大変重要な問題といえよう。
王権論とは
さかのぼって、古代国家を運営していたのは誰か。そんなことは愚問だ、天皇や藤原氏ではないかと思う方も多くおられるだろう。このナゾを解き明かすために、このたび『日本古代王権と貴族社会』という本を上梓した。そこで注目したいのが、「王権論」という概念である。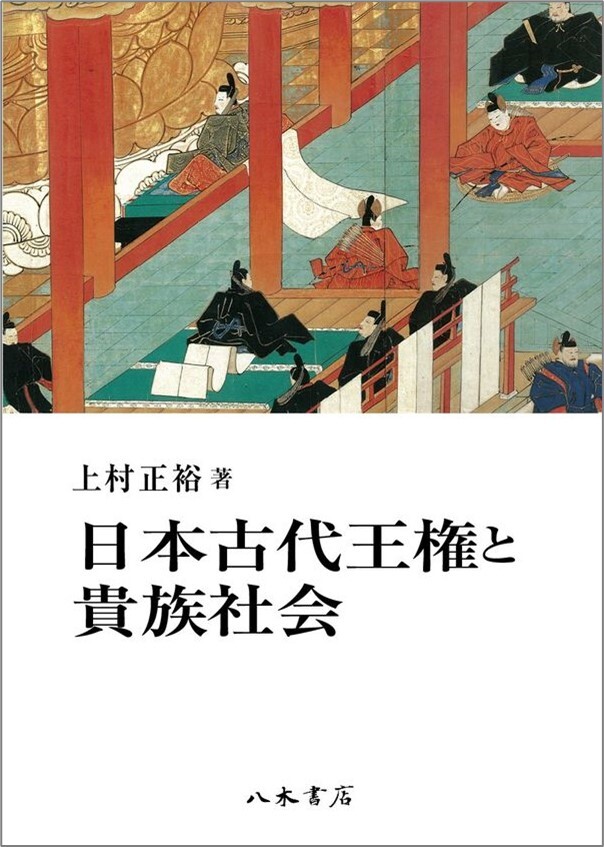
王権論とは、天皇や天皇制に限定せず、王を王たらしめている権力を分析する概念であり、構造や制度からその実像を明らかにするものである。つまり、天皇の権力を支える存在を見いだす指標として様々な材料を検討するというもので、その対象としては、太上天皇、皇后(皇太后)、皇太子などが想定される。上記の権門体制論はこれに近い考え方といってよい。
詳細は『日本古代王権と貴族社会』をご覧いただきたいが、本書の刊行により、8・9世紀の太上天皇と皇后・皇太后の特質やその変遷を示すことができた。とくに奈良時代の太上天皇や皇后・皇太后は天皇の政治を支える立場にあり、決して二重権力のような存在ではなかったことは強調しておきたい。この要因としては、奈良時代における天皇は単独での権威が不十分で、王権の多極構造を構成することが肝要であったためであると考えており、それが徐々に変質していくのが、平安時代に向けた道のりなのである。
天皇と貴族の関係
では、日本古代史では、具体的にどのように国家が運営されたのか。蘇我氏や藤原氏が政治を私物化していたようなイメージをお持ちかもしれない。確かに、専制権力を有する人物も存在していたが、そのような見方はかえって正しい歴史像をゆがめてしまう。本書では、天皇と貴族の関係に目配りし、そこから天皇や古代国家の変容を描写しようと試みた。今日では閣議や国会審議があり、国家の重要案件は会議で決めるというのが前近代以来、歴史の常だった。過去にも例えば、明治天皇の面前で岩倉具視と山内容堂が大政奉還をした徳川慶喜に辞官納地を求めるかどうかで応酬があった小御所会議が知られている。
さかのぼって、古代の皇位継承についても推古天皇の後継者をめぐって合議があったことが、『日本書紀』に記されている。
ところが、政策決定に伴う合議が奈良・平安時代前期の8・9世紀においてどのように行われたのか、その実情を語る史料は少ない。そこで本書では、8・9世紀の皇位継承決定の合議がどのように実施されているかを検討した。その結果、いわゆる「参議」ではない人々が8世紀の合議に関与しているものの、9世紀になると排除されていくということが明らかになった。
私は天皇のもとに結集する奈良時代の貴族層、特に合議に参加する「議政官」と呼ばれる人々も、後の平安時代の公卿とは異なる階層だったと考えている。王権論と貴族論を融合した上で考えた結果、いずれの視点でみても、「過渡期としての奈良時代」と位置づけるのが妥当である。つまり、「律令国家」はまだ奈良時代では完成していなかったといえるだろう。このように考えると、教科書とは異なる古代史像が見えてくるのではないだろうか。
奈良時代と平安時代のあいだ
一般的に、時代区分は首都や拠点が置かれていた地点をもとに呼ぶのがならわしで、奈良時代・平安時代という区分は、皆さんにとってもなじみ深いものと思われる。奈良時代末期、女帝の称徳天皇が死去し、いわゆる天武系(天武天皇の子孫)が断絶した。それにより、天智系の光仁天皇が即位し、その子の桓武天皇も専制権力をもとに、平安京遷都などを中心とする諸改革を断行した。これらの歴史的事実から天智系の革新性が強調されてきたが、この点について私は疑問に思っており、大きな画期は称徳天皇の頃より生じていたと考えている。例えば、称徳天皇は生前皇太子を置かず、道鏡即位を計画した。称徳天皇と道鏡の関係は尾ひれがつき、不適切な男女関係が説話を通して流布することになるが、史料に即して検討すると、道鏡は天皇に次ぐ地位を保持していたことが明らかとなった。さらに、称徳天皇は自らの側近を形成しつつ、藤原氏を中心とした公卿とも友好関係を結ぼうと努力していた。
実は桓武天皇も同様なあり方を考えており、皇位継承は天皇自らが決定するという方針を打ち出し、それを支える側近を集積していた。専制権力をどのように維持するか、桓武天皇は称徳天皇のあり方を学びつつ、反省もしていたのではないだろうか。奈良・平安時代の断絶性より継続性を見いだすというのが、私の考えである。
幅広い議論に期待
私は古代史を専門にしているが、本書の成果は決して古代史のみにとどまるものではないと思っている。摂関期・院政期、あるいはさらにその先の中世・近世の国家権力を分析する指標としての王権論や貴族論は、日本史や隣接諸分野を交えた議論の可能性を秘めているのではないか。そのように信じている。王権論を他の時代や地域で考えたらどうなるか。この視点で、本書では古代から近代、さらには東アジアの王権に関するコラムを収録している。あくまでも私のスケッチに過ぎないが、今後幅広い議論が展開されていく「のろし」となることを期待している。
[書き手]
上村 正裕(うえむら まさひろ)

1987年 茨城県生まれ
2012年 東洋大学文学部卒業
2021年 東洋大学大学院博士後期課程修了
現在 東洋大学文学部・フェリス女学院大学文学部・武蔵大学人文学部非常勤講師・京都芸術大学通信教育部業務担当非常勤講師
〔主な著作〕
『日本古代王権と貴族社会』(八木書店、2023年)
「田植御覧の成立と展開」(『人民の歴史学』234、2022年)
「伴善男の伴氏再編計画」(『続日本紀研究』427、2022年)
「葬司の基礎的考察―律令官人の一断面―」(『白山史学』56、2020年)
「八・九世紀遣使攷」(『続日本紀研究』416、2019年)
「平安時代の興福寺維摩会と藤原氏」(『国史学』223、2017年)
ALL REVIEWSをフォローする