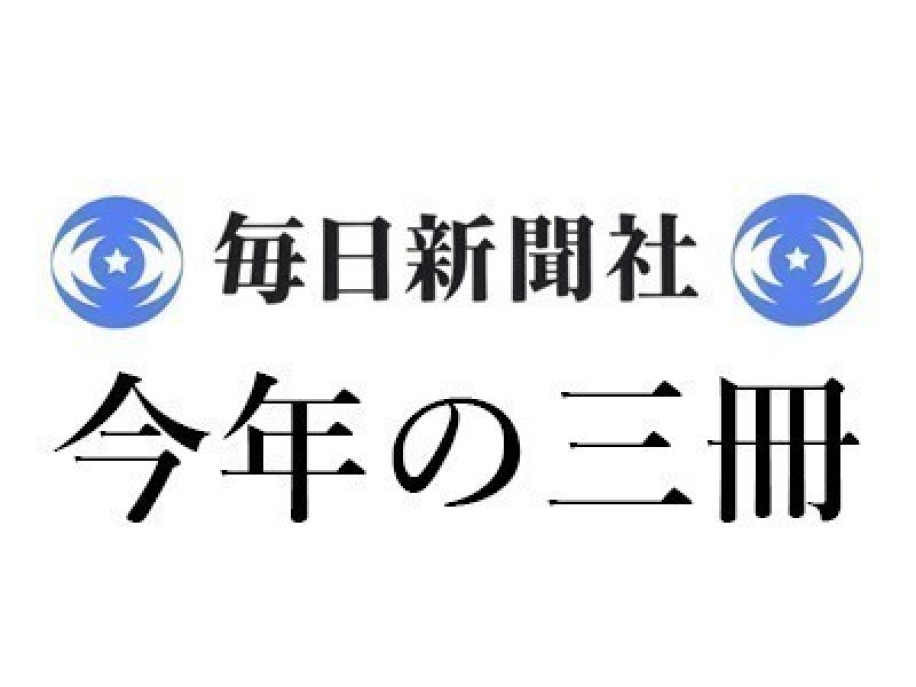書評
『津田左右吉歴史論集』(岩波書店)
貫かれた「確固たる個の視点」
本書は日本史や、日本思想・東洋思想の研究に多大な影響をあたえた津田左右吉(そうきち)の歴史関係の論考を集めたものである。戦後の古代史研究や日本思想史研究が、実に津田との格闘を経て形成されてきたものであることは疑いなかろう。ことに『日本書紀』『古事記』の研究については、津田の研究方法が今でも高く聳(そび)えている状況は変わらないように思われる。それだけに『文学に現はれたる我が国民思想の研究』全四巻の大部の主著をはじめとする津田の研究が、いかになされてきたのかを知ることは、これから歴史を学ぶ人々や、また歴史から学ぼうとする人々にとって有意義である。
編集にあたった今井修は、四つに時期区分して十八の論考を年代順に配列している。
『神代史の新しい研究』が出版される一九一三年ころまでが第一期。『古事記及日本書紀の研究』が出版される一九二四年ころまでが第二期。「日本の神道に於ける支那思想の要素」が著される一九三〇年代を経て戦時中までが第三期。そして戦後から亡くなる一九六一年までの第四期で、それぞれ重要な歴史論を収録している。
その巻頭に置かれた「学究生活五十年」がことに面白い。これは一九五一年に雑誌『思想』に求められて書かれたもので、津田が研究生活を回顧し、その学究態度をざっくばらんに記している。
それによれば、江戸の文学から始まって、明治維新ものから日本の古典、さらに日本の歴史、西洋の文芸と思想、日本の音楽・芸能へと関心を広げ、興味を抱くとすぐに多くの本を読んだものらしい。
「その時のぼくとしては読むにほねのおれるものを、かなり多く読み、あとから考えると、どうして短い時間にあれだけの書物を見たかと思われるほどに、勉強はしたらしい」と記し、「何を読むにも、それに適応する知識を得ることに注意したようにおぼえている」と、読書の方針を語っている。
こうした具合であるから、早稲田大学や東京帝大と関係はしていても、「ぼくは世間でいう私学のものでも官学のものでもなく、ただのぼくであった」という自覚になる。おそらくこの意識や対応こそが、津田の学問への姿勢を形成していたのであろう。
津田がよく用いた表現に生活と個人がある。「歴史は人の生活の過程である」といい、「歴史の第一の任務は、過去の生活を生活として叙述し描写することである」と、生活者の視点を第一としている。研究するのが個人であれば、研究の対象も何よりも個人であった。
こうした確固たる個の視点があってこそ、『日本書紀』や『古事記』の史料批判に徹する方法も生まれたのであろう。
声高な日本人論や日本精神論への批判、一面的な仏教史家や唯物論の史家への批判もまた、そこから繰り出されている。「歴史家みずからが先ず自己自身において『人』を回復しなければならない」と力説しているのが胸に響く。
戦後の津田については、皇室賛美とも思われかねない「建国の事情と万世一系の思想」という論考で物議を醸したことは有名だが、それについては解説で今井が注意深く触れている。なお丁寧な巻末の今井の解説は、津田の学問形成史をよく概観していて読みごたえがあった。
現今の性急な愛国心論議や靖国問題について考えるうえでも、本書で展開されている津田の研究の方法や態度には大いに学ぶ必要があろう。
ALL REVIEWSをフォローする