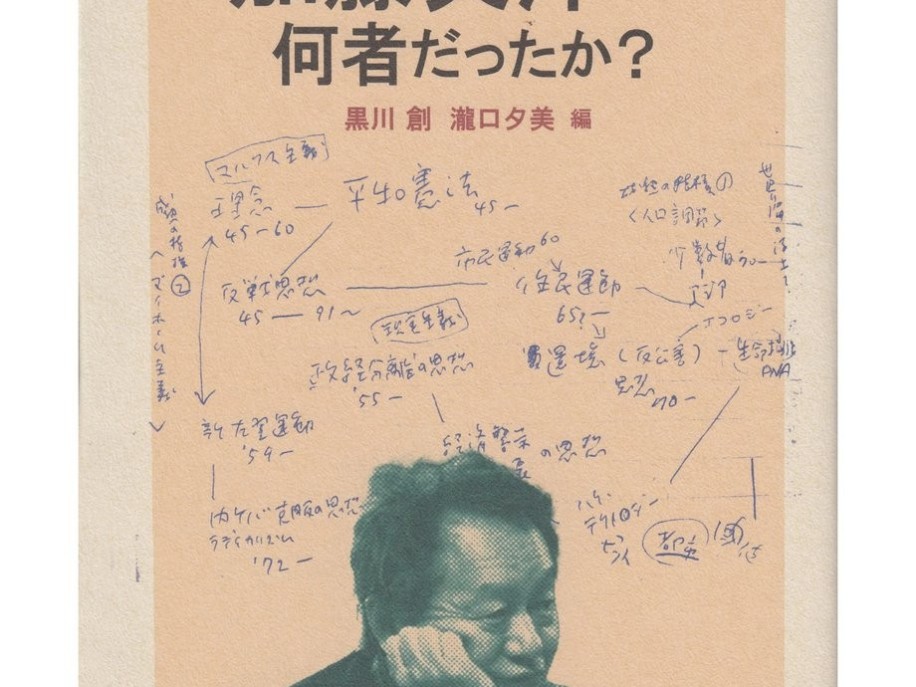書評
『舞姫』(新潮社)
みんな少しずつ悲しい
人間わざとは思えない跳躍で世界を驚かせながら、動乱の世に処することができずに狂死した天才バレエ・ダンサー、ニジンスキーの存在を、川端康成の『舞姫』ではじめて知った、という人はめぐりあわせのよさを感謝すべきだろう。新聞に連載されたのが一九五〇年。もっとあとの理屈っぽい世代は、コリン・ウィルソンの出世作『アウトサイダー』で知ることになるが、こちらはどっちかというと肖像画より解剖図に近い。どうせなら出来のよい素描で最初に見たほうがいい。些細なことのようだが、こういうあとさきは意外に大事なような気がする。生憎と僕はウィルソンのほうだった。
川端は、新聞小説に無類の腕をふるって名作を残した。とくに『舞姫』は、現在、新聞に連載小説をかかえている身の僕にとっては有害図書もいいところ。
物語は、朝鮮動乱のまっさい中、騒然とした時代の東京に設定されている。日本経済は特需景気に沸いていたが、戦後の復興が成るかどうか見通しなど誰にも立たなかった。
そうした時代を背景に、四人家族と中年男一人――母娘(おやこ)ともバレリーナの波子と品子、大学生の高男、家長の矢代、波子の恋人・竹原の五人が、足をもつれさせながら輪舞を踊る。
冒頭に、国立博物館で、父と子が天平仏の沙羯羅(さがら)像を前にする場面がある。高男は父親に向かって、沙羯羅の眉の根の寄せた感じが姉さんやお母さんの癖に似ている、といってたしなめられる。たしなめられて当然なのだ。像は可憐な童形(どうぎょう)に作ってあるが、じつは竜王、知恵の化身の大魔王なのだから。
現し身の凡人の似姿である小説のヒーロー、ヒロインを万能の魔王なんかになぞらえられるわけがない。波子や品子にかぎらず、輪舞の足がもつれるのは当たり前といえば当たり前。
竹原はカメラや双眼鏡をアメリカに売るために苦労している実業家。二十年前に波子と結婚して当然だったのに矢代にさらわれて、いまは淡いあいびきをつづけるだけ。夫の矢代は貧乏学生あがりの国文学者。古美術にまで手を広げ「ぼくは二十年の上、ほかの女に触ったこともない」といいながら波子の財産を食いつぶしている。波子は実業家の思いやりと虚業家の酷薄にはさまれて身を細らせる。
狂死した天才ニジンスキーの存在も知恵の魔王沙羯羅も、じつは矢代が波子たちに教えるのだが、物語の終わりまぎわには、「仏界入り易く、魔界入り難し」という怖い言葉を援用して、一家離散も辞さない覚悟を披露する。対抗するように竹原は、「ぼくらには深い過去がある」といって波子に再出発をうながす。
大人たちの乱調子の輪舞にはじきだされるようにして娘の品子が、以前バレエ・ダンサーとして活躍していながら、いまは伊豆で観光バスの運転手をしている心の恋人のもとへ向かおうとするところで物語は終わる。
未来へと向かう結末なのに、品子も波子も還らぬ人になってしまったようないたましさが心に残る。そういえばヒロインふたりは、タイトルには舞姫とありながら一度も晴れの舞台に立たず、ひっそりとした身ぶりで物語を過ぎてゆくだけだ。
憎まれ役の矢代だって、ただ空言をうそぶいているだけではない。みんな少しずつ悲しい。
ニジンスキーには、廃人同様になってから昔の仲間と無理やりに舞台に立たされたときの写真が残されている。魂の抜けたような顔だ。みんなの愁い顔の向こうに透けて見えるのは、沙羯羅の顔ではなく、そのニジンスキーの姿なのだ。僕がひそかに愛玩する川端の中篇。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする