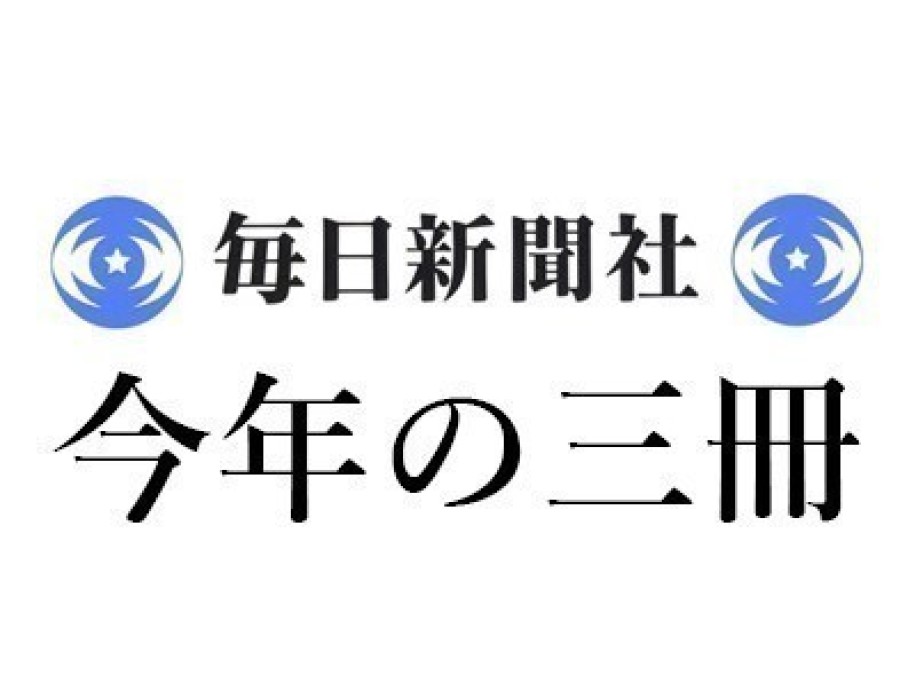書評
『読み書きの日本史』(岩波書店)
専門的知見で寺子屋の実像に迫る
江戸時代は世界一の識字率を誇り、寺子屋が読み書きの普及に大きな役割を果たした。この俗説は語られて久しいが、真偽のほどは検証されてこなかった。本書は期せずしてこの問題に答えた。古代日本人がどのように読み書きを覚えたかは、詳細がわかっていない。「習書木簡(しゅうしょもっかん)」の出土により、仮名が生まれる前後の時代について、その一端を知ることができた。律令制の時代に行政運営にあたる役人は中央と地方を問わず、木簡という短冊形の木片に書写し、典籍の習熟と公文書作成の練習をくり返していた。
片仮名や平仮名が普及すると、仮名交じり文が登場した。多様な文体が混在しているなか、中世末期から近世期にかけて候文(そうろうぶん)体が実用的な文書の主要な表記法となった。ここにいたって、貴族や官吏のみならず、一般の民衆も読み書きを手にすることができた。
書面語の訓練と習得において、往来物(おうらいもの)が初学者用の教科書として使用されていた。ほんらい、手紙文例集であったが、後に書簡の手本という範疇(はんちゅう)を超えて、教訓書のようなものや、商売の用語や地名などを列挙したものも含まれるようになった。
江戸時代になると、往来物は最盛期を迎えた。意外なのは、百姓一揆の直訴状が往来物として各地に流布していたことだ。藩政に不満を持つ百姓が、自己救済のために子弟に訴状の書き方を習得させたのは興味深い。
本書の特徴として、関連研究への目配りの広さが挙げられる。著者専門の教育史にとどまらず、隣接分野の研究資料もくまなく渉猟し、それぞれの領域の知見を総合して、読み書きの文化史的展開という野心的な課題に挑んだ。
往来物と並んで、寺子屋についての考察においてもその博引旁証(はくいんぼうしょう)ぶりがいかんなく発揮された。江戸時代には寺子屋という総称はなく、お寺で読み書きが教えられているというのもただの誤解に過ぎない。当時、「手習(てならい)師」「手習子取(ことり)」「手習塾」など、さまざまな名称で呼ばれていたが、明治になって、政府調査のなかでそうした施設を一括して「寺子屋」と称したのがきっかけだ。
江戸時代には識字率の統計がない。ただ、さまざまな角度からの研究によってその実像に迫ることができた。近世には、花押(かおう)という文様化された署名があり、一七世紀前半、長崎や京都などの都市だけでなく、地方都市にも、花押を記しえる識字者が多数いた。一部の地域には、寺子屋の師匠が死亡したときに教え子たちが筆子碑(ふでこひ)を建立する風習があり、千葉県内だけでも三〇〇〇基を超えるという。また、町の職業についての記録や「門人帳(もんじんちょう)」「軒付帳(のきつけちょう)」といった古文書も読み書きの教育の実状を解明するのに、貴重な情報を提供した。
幕府末期の識字率は明治初期の調査から比較的に正確に捉えることができる。地域別、時期別についての調査から、自分の姓名を書ける男子は約半数を超えるが、女子では半数を下回る。手紙を書ける人にいたっては男子でも一割にとどまっていた。寺子屋により、幕末の識字率が世界一だとは、ただの神話に過ぎない。
教育学、言語学、社会史、文学や哲学など、浩瀚(こうかん)な文献を読みこなし、読み書きの歴史の全体像を立ち上がらせる力量には脱帽した。
ALL REVIEWSをフォローする