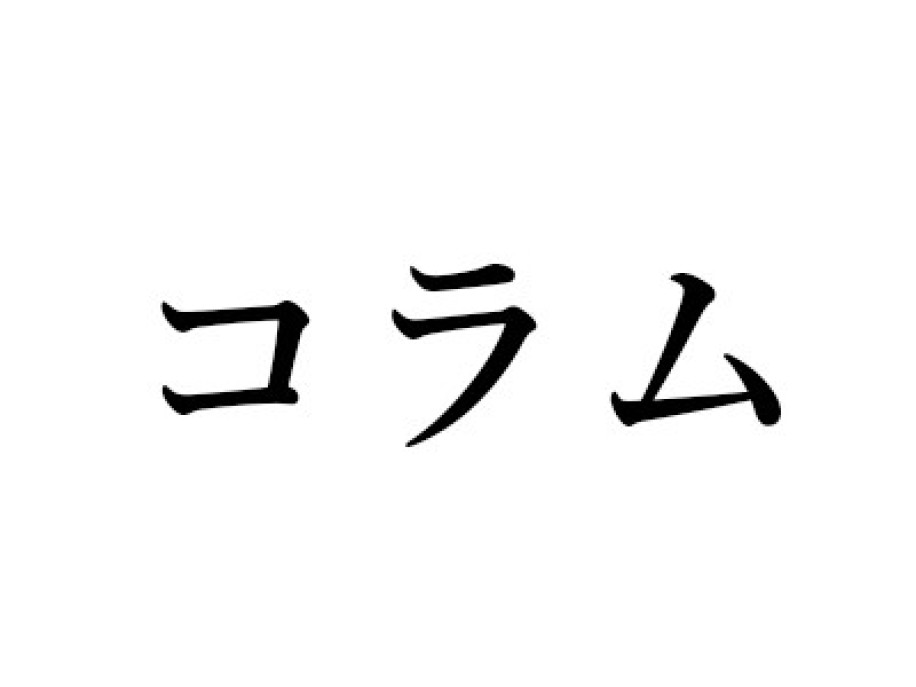本文抜粋
『書評家人生』(青土社)
このたび、明治大学名誉教授でフランス文学者の鹿島茂さんの最新書評集『書評家人生』が刊行されることになりました。2007年以来、この約15年のあいだに発表された書評を網羅した、集大成ともいえる内容になっています。いまや、当代随一の書評家となった鹿島さんですが、いかにして「書評家人生」を歩んできたのでしょうか。本書の刊行を記念して「まえがき」の一部を特別に公開いたします。
これはジャン=ポール・サルトルの『家の馬鹿息子 ギュスターヴ・フローベール論(1821年より1857年まで)』の第1巻(ちなみに最終巻である第5巻が2021年に出版され、40年をかけて完結)が刊行されたとき、たまたま原書を読んだことのある人間ということで私にお鉢が回ってきたのです。
そのときの感想はというと、「書評というのはなんと割に合わない仕事なんだ! こんなことは二度とやるまい!」というものでしたが、この感想はそれから41年たってこのまえがきを書いているいまも基本的に変わっていません。そう、書評というのは、コスト(タイム)・パフォーマンスが最悪の「労役」といっても差し支えないものなのです。
ですから、書評という仕事は、物書き業界にデビューしたての人間にまず回ってくるのが普通です。こんな割に合わない仕事を引き受けるのは新人しかいないからです。
そのいっぽうで、書評はまた、ピークを過ぎて、出版社からの注文がほとんど入らなくなった物書きの人生において最後に回ってくる仕事でもあります。
ようするに、書評は、物書き人生の最初と最後を飾る仕事なのだといえます。この意味で、どんな物書きのキャリアをひもといても、書評に始まり書評に終わっているパターンが観察できます。
では、キャリアの真ん中、つまり最盛期にはどうかというと、こちらは、書評をまったく引き受けない人と、たくさん引き受け続ける人がきれいに分かれています。
当然、前者が正しく、後者が間違っています。コスト(タイム)・パフォーマンスが最悪の「労役」に時間を割いていたのでは、自分のメインの仕事を達成はできないと考えるのが道理だからです。そのことは、死後、著作集が出版されるほどの物書きで、著作集の最後にまとめられた書評のページに当たってみると、大物ほど書評のページが少ないことからも証明されます。なかには吉本隆明氏や丸谷才一氏のような例外もありますが、書評はキャリアの最初と最後にしかない場合がほとんどなのです。
では、私はどちらのタイプの物書きかといえば、後者の部類に属しますが、しかし、それは本意ではまったくありませんでした。
物書き人生の初期である1993年から『毎日新聞』の書評ページ「今週の本棚」のレギュラー執筆者となり、1996年からは『週刊文春』の「私の読書日記」を他の4人ないしは5人の人と持ち回りで引き受けましたから、最初は書評の仕事が多いという物書きキャリアの定番コースを歩んだわけですが、実際には、2、3年の任期を務め上げれば、コス(タイ)・パ最悪のこの「労役」から解放されると心から期待していたのです。ところが、案に相違して、任期は更新され続け、なんと今日まで『毎日新聞』と『週刊文春』で切れ目なしで書評ページのレギュラー執筆者を務めているのです。
第一に、私は自分でいうのも変ですが、いたって利に聡いコス(タイ)・パ重視の、性、卑しい人間で、滅私奉公というのは一番嫌いなことです。では、そんな私が、結果的に書評を一生続けてしまったのはいかなる理由によるのでしょう?
不思議なことに、これに対して自分でも明確な答えを出せないでいるのです。
そこで、自分にとっても未解決のこの問いに答えを出すため、「まえがき」という場を借りて、なにゆえに書評を書き続けたのかについて、以下に考察を試みてみようと思います。
まず、考えてみたいのは、本を読むのはこれほど楽しいのに、書評を書くことはなぜこれほど面倒臭いのだろうか、という問題です。すでに、ゆうに千を超える書評を書いてきて、こんなことをいうのはいささか面妖かもしれませんが、この苦しい思いを感じずに書評を書いたことは一度もないのです。
では、書評のどこが苦しいのかといえば、対象の本を読むのに時間がかかるということでも、書く分量が400字詰め原稿用紙で最大5枚程度に限られていることでもありません。いわんや、労力に対して報酬が少なすぎることでもないのです。正直いえば、そんな問題はとうに解決済みです。
では、なにが苦しいのでしょうか?
理由は本という「絶対的な対象」から外れたことを書くわけにはいかないという「宿命」にあります。
このことは、本をネタにしながら自由に感じていることを書く類いの書物エッセイと比べてみれば明らかです(ちなみに、私はこの手の本を『セーラー服とエッフェル塔』(文春文庫)、『乳房とサルトル 関係者以外立ち読み禁止』(光文社知恵の森文庫)、『モモレンジャー@秋葉原』(文藝春秋)、『とは知らなんだ』(幻戯書房)と4冊も書いています)。こうしたエッセイは、まあ、内容がエロティックなものが多かったこともあって、書いていて実に楽しかったと記憶しています。
ところがです。それなら、エッセイで取り上げたのと同じ本で書評を書いてくださいといわれると、とたんに苦しさが出てくるのです。
つまり、一冊の本に対して一つの書評をきっちりと書くということそれ自体が書評の苦しさの本質をなしているのです。
なぜなのでしょうか?
それは、多くの人と付きあうよりも、一人の人と付きあうほうがはるかに面倒くさいのと似ています。この定理は人間ばかりか本にも当てはまるようです。
つまり、書評というのは、友人としてあるいは敵として、恋人としてあるいは配偶者として、一人の人と徹底的に付きあうのと同じくらいの負荷がかかるものなのです。なぜかといえば、一人の人と付きあうにはその人の全部といわぬまでも多くのことを知らなくてはならないのと同じで、書評は、一冊の本について、その全体を知らなければ書くことはできないからです。
書評の苦しさの第二の原因は、基本的に「署名」をして、文責は自分にあることを公にさらさなければならないことから来ています。匿名書評というものはこの苦しさを引き受けていない以上、書評とは認めてはいけないものです。同じく、ネットのハンドルネームを使った本のコメントは書評ではありません。書評というのは最低限、署名をすることの苦しさを引き受ける覚悟のある人でなければ書いてはいけないものなのです。これを強く感じるのは、見知らぬ作者ではなく、知己の本の書評を書くときです。友情を犠牲にしても書くべきことは書かなければならないことがあるからです。
書評の苦しさの第三は、評者と本の作者以外の第三者も読むことを、つまり公開を原則としていることです。本の感想を、著者に、昔なら手紙で、いまならメールやショート・メッセージで伝える場合には第三者がこれを読むことはありませんから、たとえその内容が批判的なものであっても、関係がおおきくこじれることはありません。
ところが、書評はあらかじめ第三者が読むという公開原則が前提となっているテクストですから、この第三者というものを心に描きながら書かなければなりません。じつは、これが案外難しく、苦しさを増すのです。
しかし、こう書くと、かならずや、なら、なんでそんなに苦しくしかもコス(タイ)・パ最悪の書評なんか引き受けているのだという疑問が再び呈されるはずです。
ごもっともな意見です。
しかし、これに答えるのは意外と簡単なのです。
苦しくてコス(タイ)・パが最悪だからこそ書くのです。そう、書評とはある意味、マゾヒズムの極致なのです。とはいえ、ここでひとつ、果たしてマゾヒズムのない職業というものは存在しうるのだろうかと問うてみる必要があるでしょう。というのも、たいていの職業人(プロ)はマゾヒストであり、そうでないプロは存在しないからです。
たとえば、プロというとすぐに思い浮かべるプロ・スポーツの選手なら、ほとんどの人が、苦しさがなければとっくにスポーツなんかやめていたと答えるでしょう。苦しさがあるからこそ、それを克服したときの喜びがあり、矜持が生まれるのだと。
ただ、優れたプロ選手ならこう付け加えることを忘れないはずです。同じ苦しさでも、それが人(コーチや監督)から押し付けられたものであれば、どこまでいっても苦痛でしかないので耐えられないが、自分が自分に課した規律から生まれる苦しさなら、それはむしろ歓迎すべきことであり、ある限界点を超えたところからそれは快楽に変わる、と。
そうなのです。自分で自分を律するために自分で定めた「規則」であれば、人間は「克己」という名でそれを美化して、自分のほうから進んでそれに従うものなのです。ウェイト・トレーニングやジョギングがそのわかりやすい例でしょう。健康のためというのは口実にすぎず、自ら定めた目標という「法」に従って、「克己」に伴うマゾヒズムを呼び込むために、これを続けるのです。
さて、書評に話を戻しますと、書評とは、小説、エッセイ、論説などと比べてもこの「克己」に拠るところが最も多いジャンルなのです。いいかえれば、書評は、脳髄のウェイト・トレーニング、知力のジョギングであり、自分が定めた規則を守り、その負荷に耐えることを介して生まれる快楽を得ること以外には、あまり目的を持たないものなのです。
(中略)
というように、いろいろと苦しいにもかかわらず41年間も書評を続けてきた理由を自分で探ってきましたが、これらの言葉をひとことでまとめると次のようになるのではないかと思います。
書評は人のためならず。
そう、書評は自分のために書くものでなければ長くは続けられないのです。
(中略)
近年、書評集が出版されることがどんどん少なくなっているように感じますが、私は逆に、ネット時代だからこそ、読書の指針として書評集が多く出版されるべきであると感じています。本書がその傾向の先駆けになれば幸いです。
書評家人生、まだ当分は、続きそうです。
[書き手]鹿島 茂(明治大学名誉教授・仏文学者)
『書評家人生』刊行記念! 鹿島茂が、40年にわたる自らの「書評家人生」を振り返る
「本意ではなかった」書評家人生
生まれて初めて書いた書評は、『日本読書新聞』1982年5月24日号の「特集・サルトルとフローベール 『家の馬鹿息子』素描」に掲載された「遡行的分析と前進的綜合「推理=小説」としての『家の馬鹿息子』」でした。これはジャン=ポール・サルトルの『家の馬鹿息子 ギュスターヴ・フローベール論(1821年より1857年まで)』の第1巻(ちなみに最終巻である第5巻が2021年に出版され、40年をかけて完結)が刊行されたとき、たまたま原書を読んだことのある人間ということで私にお鉢が回ってきたのです。
そのときの感想はというと、「書評というのはなんと割に合わない仕事なんだ! こんなことは二度とやるまい!」というものでしたが、この感想はそれから41年たってこのまえがきを書いているいまも基本的に変わっていません。そう、書評というのは、コスト(タイム)・パフォーマンスが最悪の「労役」といっても差し支えないものなのです。
ですから、書評という仕事は、物書き業界にデビューしたての人間にまず回ってくるのが普通です。こんな割に合わない仕事を引き受けるのは新人しかいないからです。
そのいっぽうで、書評はまた、ピークを過ぎて、出版社からの注文がほとんど入らなくなった物書きの人生において最後に回ってくる仕事でもあります。
ようするに、書評は、物書き人生の最初と最後を飾る仕事なのだといえます。この意味で、どんな物書きのキャリアをひもといても、書評に始まり書評に終わっているパターンが観察できます。
では、キャリアの真ん中、つまり最盛期にはどうかというと、こちらは、書評をまったく引き受けない人と、たくさん引き受け続ける人がきれいに分かれています。
当然、前者が正しく、後者が間違っています。コスト(タイム)・パフォーマンスが最悪の「労役」に時間を割いていたのでは、自分のメインの仕事を達成はできないと考えるのが道理だからです。そのことは、死後、著作集が出版されるほどの物書きで、著作集の最後にまとめられた書評のページに当たってみると、大物ほど書評のページが少ないことからも証明されます。なかには吉本隆明氏や丸谷才一氏のような例外もありますが、書評はキャリアの最初と最後にしかない場合がほとんどなのです。
では、私はどちらのタイプの物書きかといえば、後者の部類に属しますが、しかし、それは本意ではまったくありませんでした。
物書き人生の初期である1993年から『毎日新聞』の書評ページ「今週の本棚」のレギュラー執筆者となり、1996年からは『週刊文春』の「私の読書日記」を他の4人ないしは5人の人と持ち回りで引き受けましたから、最初は書評の仕事が多いという物書きキャリアの定番コースを歩んだわけですが、実際には、2、3年の任期を務め上げれば、コス(タイ)・パ最悪のこの「労役」から解放されると心から期待していたのです。ところが、案に相違して、任期は更新され続け、なんと今日まで『毎日新聞』と『週刊文春』で切れ目なしで書評ページのレギュラー執筆者を務めているのです。
書評はなぜかくも「面倒臭い」のか
では、いったい、なんでコス(タイ)・パ最悪の仕事を途中でやめないで、40年以上も、つまり一生を費やしてコンスタントに書評を続け、しかも、書評集を10冊ほど刊行したのかと疑問に思う向きもあるかもしれません。第一に、私は自分でいうのも変ですが、いたって利に聡いコス(タイ)・パ重視の、性、卑しい人間で、滅私奉公というのは一番嫌いなことです。では、そんな私が、結果的に書評を一生続けてしまったのはいかなる理由によるのでしょう?
不思議なことに、これに対して自分でも明確な答えを出せないでいるのです。
そこで、自分にとっても未解決のこの問いに答えを出すため、「まえがき」という場を借りて、なにゆえに書評を書き続けたのかについて、以下に考察を試みてみようと思います。
まず、考えてみたいのは、本を読むのはこれほど楽しいのに、書評を書くことはなぜこれほど面倒臭いのだろうか、という問題です。すでに、ゆうに千を超える書評を書いてきて、こんなことをいうのはいささか面妖かもしれませんが、この苦しい思いを感じずに書評を書いたことは一度もないのです。
では、書評のどこが苦しいのかといえば、対象の本を読むのに時間がかかるということでも、書く分量が400字詰め原稿用紙で最大5枚程度に限られていることでもありません。いわんや、労力に対して報酬が少なすぎることでもないのです。正直いえば、そんな問題はとうに解決済みです。
では、なにが苦しいのでしょうか?
理由は本という「絶対的な対象」から外れたことを書くわけにはいかないという「宿命」にあります。
このことは、本をネタにしながら自由に感じていることを書く類いの書物エッセイと比べてみれば明らかです(ちなみに、私はこの手の本を『セーラー服とエッフェル塔』(文春文庫)、『乳房とサルトル 関係者以外立ち読み禁止』(光文社知恵の森文庫)、『モモレンジャー@秋葉原』(文藝春秋)、『とは知らなんだ』(幻戯書房)と4冊も書いています)。こうしたエッセイは、まあ、内容がエロティックなものが多かったこともあって、書いていて実に楽しかったと記憶しています。
ところがです。それなら、エッセイで取り上げたのと同じ本で書評を書いてくださいといわれると、とたんに苦しさが出てくるのです。
つまり、一冊の本に対して一つの書評をきっちりと書くということそれ自体が書評の苦しさの本質をなしているのです。
なぜなのでしょうか?
それは、多くの人と付きあうよりも、一人の人と付きあうほうがはるかに面倒くさいのと似ています。この定理は人間ばかりか本にも当てはまるようです。
つまり、書評というのは、友人としてあるいは敵として、恋人としてあるいは配偶者として、一人の人と徹底的に付きあうのと同じくらいの負荷がかかるものなのです。なぜかといえば、一人の人と付きあうにはその人の全部といわぬまでも多くのことを知らなくてはならないのと同じで、書評は、一冊の本について、その全体を知らなければ書くことはできないからです。
書評の苦しさの第二の原因は、基本的に「署名」をして、文責は自分にあることを公にさらさなければならないことから来ています。匿名書評というものはこの苦しさを引き受けていない以上、書評とは認めてはいけないものです。同じく、ネットのハンドルネームを使った本のコメントは書評ではありません。書評というのは最低限、署名をすることの苦しさを引き受ける覚悟のある人でなければ書いてはいけないものなのです。これを強く感じるのは、見知らぬ作者ではなく、知己の本の書評を書くときです。友情を犠牲にしても書くべきことは書かなければならないことがあるからです。
書評の苦しさの第三は、評者と本の作者以外の第三者も読むことを、つまり公開を原則としていることです。本の感想を、著者に、昔なら手紙で、いまならメールやショート・メッセージで伝える場合には第三者がこれを読むことはありませんから、たとえその内容が批判的なものであっても、関係がおおきくこじれることはありません。
ところが、書評はあらかじめ第三者が読むという公開原則が前提となっているテクストですから、この第三者というものを心に描きながら書かなければなりません。じつは、これが案外難しく、苦しさを増すのです。
コスパもタイパも悪い書評を書き続ける理由
以上、書評について語るには、書評を書くのは苦しいことだという前提から始めなければなりません。この前提を外した議論はすべて無効です。しかし、こう書くと、かならずや、なら、なんでそんなに苦しくしかもコス(タイ)・パ最悪の書評なんか引き受けているのだという疑問が再び呈されるはずです。
ごもっともな意見です。
しかし、これに答えるのは意外と簡単なのです。
苦しくてコス(タイ)・パが最悪だからこそ書くのです。そう、書評とはある意味、マゾヒズムの極致なのです。とはいえ、ここでひとつ、果たしてマゾヒズムのない職業というものは存在しうるのだろうかと問うてみる必要があるでしょう。というのも、たいていの職業人(プロ)はマゾヒストであり、そうでないプロは存在しないからです。
たとえば、プロというとすぐに思い浮かべるプロ・スポーツの選手なら、ほとんどの人が、苦しさがなければとっくにスポーツなんかやめていたと答えるでしょう。苦しさがあるからこそ、それを克服したときの喜びがあり、矜持が生まれるのだと。
ただ、優れたプロ選手ならこう付け加えることを忘れないはずです。同じ苦しさでも、それが人(コーチや監督)から押し付けられたものであれば、どこまでいっても苦痛でしかないので耐えられないが、自分が自分に課した規律から生まれる苦しさなら、それはむしろ歓迎すべきことであり、ある限界点を超えたところからそれは快楽に変わる、と。
そうなのです。自分で自分を律するために自分で定めた「規則」であれば、人間は「克己」という名でそれを美化して、自分のほうから進んでそれに従うものなのです。ウェイト・トレーニングやジョギングがそのわかりやすい例でしょう。健康のためというのは口実にすぎず、自ら定めた目標という「法」に従って、「克己」に伴うマゾヒズムを呼び込むために、これを続けるのです。
さて、書評に話を戻しますと、書評とは、小説、エッセイ、論説などと比べてもこの「克己」に拠るところが最も多いジャンルなのです。いいかえれば、書評は、脳髄のウェイト・トレーニング、知力のジョギングであり、自分が定めた規則を守り、その負荷に耐えることを介して生まれる快楽を得ること以外には、あまり目的を持たないものなのです。
(中略)
というように、いろいろと苦しいにもかかわらず41年間も書評を続けてきた理由を自分で探ってきましたが、これらの言葉をひとことでまとめると次のようになるのではないかと思います。
書評は人のためならず。
そう、書評は自分のために書くものでなければ長くは続けられないのです。
(中略)
近年、書評集が出版されることがどんどん少なくなっているように感じますが、私は逆に、ネット時代だからこそ、読書の指針として書評集が多く出版されるべきであると感じています。本書がその傾向の先駆けになれば幸いです。
書評家人生、まだ当分は、続きそうです。
[書き手]鹿島 茂(明治大学名誉教授・仏文学者)
ALL REVIEWSをフォローする