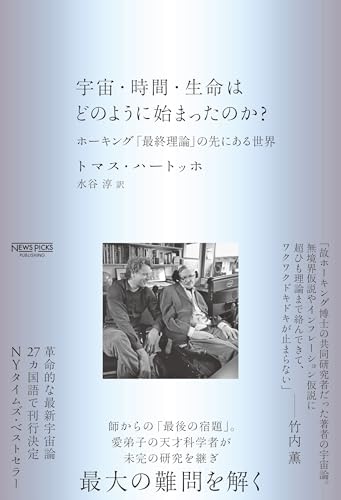書評
『あつまる細胞 体づくりの謎』(岩波書店)
世界的研究の歩み、心地よく追体験
あつめるでなく、あつまる細胞。身近な生きものはどれも多細胞生物と呼ばれ、細胞が集まって心臓、脳、腸などの器官をつくり、体をつくっている。そのしくみが分かり始めてから40年ほどが経った今、この分野をリードしてきた著者が、大学院時代から研究生活を終えるまでを語っている。派手な話ではないが、良質の研究の様子が分かる心地よい物語であり、専門外の方も楽しめるはずだ。まず「おわりに」を見よう(あとがきはその本の顔であることが少なくない)。「胚の中で集団移動している細胞は、サバンナを大移動する草食動物の集団とそっくりだ」「とくにおもしろいのは、(中略)個々の細胞がずいぶん勝手に動いていることだ。(中略)しかし、必ず目的地にたどり着く」「人が建物や機械を作る場合、設計図を作成し、これに基づいて、部品を組み立てるのだが、体作りの場合は、部品が自律的に組み上がるわけだ。バラバラにされた細胞が再び集まって器官作りをすることを『自己組織化』といい、これが動物の体作りの本質だといってよい」。細胞が集まる話、何だか面白そうと思えないだろうか。
二つの実験がある。一つはウニやヒトデの胚をカルシウムを含まない人工海水に入れるとバラバラになり、通常の海水に変えると元に戻るというものだ。もう一つ、ニワトリの胚の中腎(発生初期に現れる腎臓)はトリプシン(タンパク質分解酵素)処理でバラバラになるが、培養していると中腎になる。細胞接着にはタンパク質とカルシウムが関わっているようだ。ニワトリの胚で眼の水晶体の培養実験をしていた著者は、培養液に特定のタンパク質を入れると接着阻害が起きることを見出したことから、「細胞接着の謎解きにはまる」。
京大ではトリプシン液でバラバラにした細胞がまた接着したのに、留学先の米国カーネギー研究所でやったら着かない。実験ではよくあること。ここで腐らずその理由を考えると新天地が開けるのだ。このような具体的な謎解きの過程が丁寧に書かれているので、研究の現場が見えてくる。科学は苦手と言わず、図解を見ながらクイズを解くつもりになると、優れた研究者を追体験できて楽しい。
「先陣争いすれすれ」で細胞接着タンパク質発見者となった著者は、それを「カドヘリン」と名づけた。カルシウムを必要とする接着(adherens)タンパク。よい命名であり国際的名称となった。その後、上皮細胞と、神経系、筋肉、結合組織のカドヘリンは異なることが分かり、前者をE—カドヘリン、後者をN—カドヘリンとした。同じカドヘリン同士だとよく接着し、器官をつくる。
カドヘリンは細胞外ではたらくが、細胞内でもいくつかのタンパク質がはたらいて接着を強力にしている。著者は、腹いっぱい食事をしてパンパンになった胃が破れないほどの接着力が必要なのだろうと言う。とはいえ食べ過ぎには気をつけた方がよいけれど。
発生過程でのカドヘリンの重要な役割は容易に想像できる。複雑な構造をもつ脳で調べると、シナプスの成熟にも関わることが分かった。このように重要なカドヘリン、当然がんの浸潤、転移を含む様々な病気に関わるなど、これから調べたいことがたくさんある。読むうちに自分で次の課題を考えてみたくなってきた。
ALL REVIEWSをフォローする