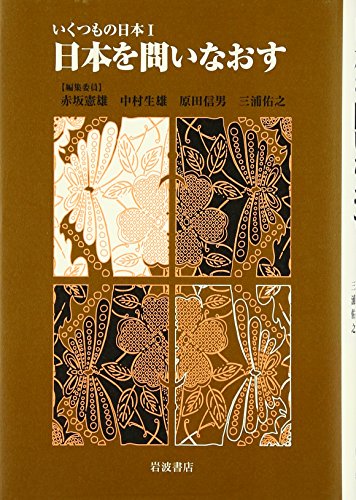書評
『南朝全史 大覚寺統から後南朝へ』(講談社)
明治国家に適合した王権至上主義
後醍醐天皇が京都から逃れて開かれた南朝は、花の吉野を中心にして五十五年にわたって勢力を維持し、室町幕府の擁する北朝と対峙した。この時代は南北朝時代と称されているが、戦前には南朝は「吉野朝」とも称され、南北朝正閏(せいじゅん)論争以後には、これが正統な政権として国家により定められてきたのであった。
しかし戦後になると、そのくびきがはずれ、室町幕府を中心にして政治を捉えることが一般的になるなか、南朝の政治やあり方については、いつしか関心も失われていった。
だが南朝方として東国で活躍した北畠親房の政治思想や、九州で活躍した懐良(かねよし)親王の征西府の対外活動などへの関心が広がるなか、南朝の動きをきちんと考えておく必要性が強まってきていたが、それに応えたのが本書であり、待望の書である。
著者は鎌倉後期から南北朝期にかけての政治史を多角的に扱ってきたが、この課題に応じて、鎌倉後期の大覚寺統と持明院統の皇統の対立に始まり、建武の新政、南朝の成立と南北朝の抗争、南北朝の合体、そしてその後の後南朝の動きにいたるまでの南朝の全史を、総合的に描いている。
問題は、消滅した政権ということもあって、圧倒的に少ない史料という制約があり、それをいかに描くのかにある。
そこで著者はまず、鎌倉後期の二つの皇統対立における路線の違いに注目し、その流れの中に南北朝の路線の違いを位置づけた。そのため建武政権までの叙述が本の半分を占めることになった。
南朝へと引き継がれる大覚寺統には王権至上主義的な考え方があり、それに対する北朝に引き継がれる持明院統には、武家政権との融和主義的な考え方があることを明解に指摘し、それが南北朝対立の底流にあったことを明らかにしている。
確かにそう見ると、名分論だけでなく、天皇に軍事大権を集中させた明治国家にとっては、南朝のあり方は適合的であったのである。そして象徴天皇制をとる今の体制は、北朝の流れを引き継ぐものであったといえるのかも知れない。
続いて著者が苦心したのは新たな史料の発掘である。ここで注目したのが後醍醐天皇の皇子宗良親王の撰になり、長慶天皇に奏覧されて勅撰集とされた『新葉和歌集』である。中世においては和歌は政治と文化の好個の歴史資料ではあり、それを有効に活用している。
南朝の皇族や廷臣たちに詠まれる和歌に付けられた詞書などから、南朝の年中行事の執行状況を探り、廷臣たちの動きや、天皇を祈祷によって守る護持僧たちの動きなどを明らかにしている。
これは貴重な成果であり、弱体化していたとはいえ、南朝が朝廷として機能していたことがここからよくうかがえる。とくに大覚寺統のうちでも後醍醐の系統でない恒明(つねあき)親王や後二条天皇の流れの動きを明らかにした点は注目される。
さらに本書の特色としてはもう一つ、合体以後の後南朝の動きを明らかにして、どうして南朝の動きがその後も消えずに続いていったのかを追跡したこともあげられよう。武家政権がその命脈を絶やさずに温存したことの意味を明らかにしている。
全体的に禁欲的にまとめられているだけに、印象はややおとなしい感もあるが、これまでに過剰な言説が多くあっただけに抑制的にまとめられたもので、これからの基礎となる一冊といえよう。
ALL REVIEWSをフォローする