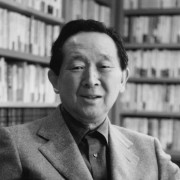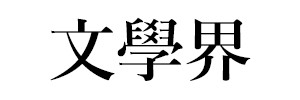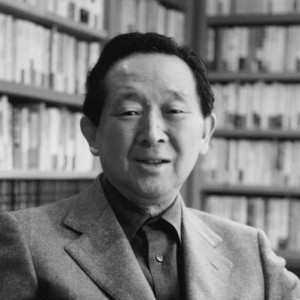書評
『燃える塔』(新潮社)
『燃える塔』は重要な作品である。それは作者が自らの創作活動の原点になっている主題を採り上げているという意味においてばかりではない。現代の文学にとって大きく重い主題であるはずなのに、多くの作者が意識的にか無意識的にか避けてきた主題に作者が取組んでいるからである。
やや飛躍した連想かもしれないが、私は『燃える塔』を読みながら昨年外国文学部門でベストセラーになったベルンハルト・シュリンクの『朗読者』を思い出した。この作品は戦争がいかに戦争を知らない世代にまで暗く深い影響を与えるかが主題になっていたと言うことが出来るものであった。
主人公「わたし」は特攻隊の中隊長だった父を持つ。父は「自分も後から行く」と、死を意味する攻撃に出発する部下に約束していた。彼の出撃予定は八月十八日だったから、日本の突然の降伏によって彼は生きのびてしまった。敗戦後間もなく「わたし」が生れる。
その頃、父は九州Y県の特別攻撃隊の基地になっていた飛行場の近くの民家の一室を借りて身重の妻と住んでいたのである。
敗戦から長い年月が経って、その民家の所有者の息子だった野川という人から、成人したわたしに電話が掛ってきたところから小説がはじまる。父は、敗戦から三十年ほどたって、なんの遺書もなしに自死していた。
と、わたしは書く。
戦争が烈しかった時代「親の世話や家を継ぐといった責任から遠い順に特攻隊に出された」、とわたしは教わる。わたしの父は「いのち永らえるために母と結婚し、母の方の婿養子になったのか」と、わたしは父の生きざまを追跡しはじめる。わたしの「夢」や「幻想」そして官能がもたらす陶酔がその追跡を助け、あるいは混乱させる。
半ば夢のような時間のなかで飛行場が襲撃され燃え上る。「父はこのあかあかと燃える夜を呪いながら(中略)、この夜に酔っているのではないか」とわたしは考える。浪曼主義の美意識が、エロスと死=タナトスを結びつける。
この死と性的なものの一致は次章「海からの客」の若い助手の美津子と一緒に寝たわたしの、海から上ってくる黒い生き物に父が呑みこまれていく幻想のなかでも暗示されている。生前、父が教鞭をとっていた大学の臨海実験所だった場所を尋ねて、わたしは生きた化石であるカブトガニが集ってくる海岸に立つ。年配の研究者瀬山は、研究所目がけて這い上ってくるカブトガニは戦争で死んだ死者と思っているらしい。若い美津子には戦死者の喩としてのカブトガニというのが分らない。わたしは、その蟹を研究している瀬山先生の胸中が分ってくるにつれて、彼が父と同じように突然いなくなってしまうのではないかという不安に捉われる。瀬山先生が研究所の後輩に、
と責められているのを立ち聞きしてしまったわたしは、瀬山先生が他人とは思えなくなってくる。
第三章でわたしは「鳥たちの島」に出かける。その島が並々ならぬ重力で、水中に潜っているうちに幻聴に襲われて流されたわたしを招き寄せたのだ。それは沖島と呼ばれる裏の名前を持っているが、地図や旅行社で調べても見付からない性質の島なのだ。そこには、「トッコウ、トッコウ」
と鳴く姿の見えない鳥が棲んでいる。この呼び名の起源は「特攻隊」らしいと読者は気付く。漂着したわたしは、島の戦死した特攻隊員の遺児沖田時夫とその母と妹の水奈子に会う。戦死した彼らの父はそのとき二十二歳、わたしの父親は二十四歳で、両者のあいだには、「年齢差以上の階級差」があって、わたしの父は生き残ったのだった。
わたしは戦死した水奈子の父が、その島で一番好きだった場所に案内してもらう。それは岩穴で、清水が湧いている他は何もない場所だ。そこは神が降りる場所のようでもあり、女性の体内、あるいは膣としての洞窟のようでもある。その場所で水奈子は「わたし」の存在の根本の不条理を指摘する。彼女は、
と戦死した父親のことを言い、
と、上官の娘であるわたしに詰め寄る。やがて気持を切り換えた水奈子は、
と和解の言葉をさしのべるが、わたしの心は少しも慰められない。その日、わたしは郷里の家の庭に四羽のトッコウ鳥と覚しき客が舞い降りる夢を見る。十二歳のわたしと父と母が四人を迎える。
沖田守が、
と父に質問する。父は卑屈な態度を見せ、わたしは、
と述べる。この記述は私に、サルトルの『嘔吐』のなかで主人公が盛り上った木の根の瘤を見て嘔吐を覚える記述を想起させたのであったが。
やがて客が帰る様子を、わたしが槙の垣根の隙間から見ていると、その男たちの中に父の姿があることを発見する。この光景の描写の中で作者は父の死の原因と形を理解したのだと言ってもいいのかもしれない。
こうして、この父の自死を巡る話は第四章「燃える塔」で物語を閉じる。
この章ではラジオのジョッキーの声などを現代ふうのノイズとして使い、いくら積み上げても崩れてしまうZ聖堂の話を前触れにして肉体を持った父親が登場する。尚、その教会を何度崩されても建てているのはTと呼ばれる年齢不詳の男である。わたしは父に連れられていった研究室の階段で遊んでいた子供の頃の光景を思い描く。そこには働いている父親の姿があった。どこかに重く戦争の影を曳きながら。その父は戦争で死んだ友人の妹らしい女と会っているが、彼女の声はわたしにも似ているのだ。幻想のなかでわたしは父に、
と言いかけてやめ、やはり父に付きまとうのである。あたかも、どこまでもどこかにいるはずのもっと別の父を見付けようとしているみたいに。わたしはスナック喫茶「ダイアリー」を探し出す。それは、Z聖堂の庭、東隅のヤツデの木、その横の石灯籠の下、という妙な場所にある。地中のスナックらしい。
その"ダイアリー"で父が飲む器には死んだ戦友や部下の名前が、猫の置物には「必中必沈」というような字が印されている。これは特攻隊の合言葉だったのだろうし、板壁に刻まれている、「20・4・28、20・5・4、20・7・19」というのは特攻隊が出撃した日付ではないかと思われる。だから父が行くスナックの名は"ダイアリー"なのだ。その店で女は、
と父を責める。その責め言葉は、いまや甘く父のからだを溶かしていくようだ。
わたしは何か書かなければという想いに駆られてペンを取る。自分がどんな状況下で生れたのか、などと考えることは意味がない、という意味の元、性の快楽の中から自分のいのちも発生したのだと直感する……、などと書いているとしきりに鐘が鳴る。ふと目をずらすと「終ったよ」という誰かの書いた文字が目にとび込んでくる。
その文字が目にとび込んできた時、神父が登場しTやわたしたちと一緒に砂の聖堂を造りはじめる。Tとは父さんのTかもしれないし特攻隊のTかもしれない。
この重い思想的作品は、
と言う言葉で終る。
このように、章を追ってくると、作者が力をふり絞るようにして、いかに戦争という不条理が人間存在を逆光のなかに浮び上らせているか、という主題と取組んだかが伝ってくる。
この作品は必ずしも読みやすいものではない。それはひとつには今日の我が国の文学が他の国と違って、こうした人間存在の根本にかかわるような主題を避けているからであり、文学が思想を表現する文脈を失っているからでもある。作者はこうした停滞には目もくれずに果敢な挑戦を試みたのだ。その意味でもこの作品は今日の文学にとって看過することのできない問題を提起した。この主題は今後もいろいろな形で取り上げられるべきものであり、その最初の一歩を踏み出したという意味でもこれは作者本人にとって、記念碑的な作品であるに違いない。
【この書評が収録されている書籍】
やや飛躍した連想かもしれないが、私は『燃える塔』を読みながら昨年外国文学部門でベストセラーになったベルンハルト・シュリンクの『朗読者』を思い出した。この作品は戦争がいかに戦争を知らない世代にまで暗く深い影響を与えるかが主題になっていたと言うことが出来るものであった。
主人公「わたし」は特攻隊の中隊長だった父を持つ。父は「自分も後から行く」と、死を意味する攻撃に出発する部下に約束していた。彼の出撃予定は八月十八日だったから、日本の突然の降伏によって彼は生きのびてしまった。敗戦後間もなく「わたし」が生れる。
その頃、父は九州Y県の特別攻撃隊の基地になっていた飛行場の近くの民家の一室を借りて身重の妻と住んでいたのである。
敗戦から長い年月が経って、その民家の所有者の息子だった野川という人から、成人したわたしに電話が掛ってきたところから小説がはじまる。父は、敗戦から三十年ほどたって、なんの遺書もなしに自死していた。
父はわたしに戦争の話は一切しなかった。(中略)海軍時代の仲間が集まっても軍歌になると笑ったまま口を閉じ、あとで植木等の歌をうたったのだそうだ。
と、わたしは書く。
戦争が烈しかった時代「親の世話や家を継ぐといった責任から遠い順に特攻隊に出された」、とわたしは教わる。わたしの父は「いのち永らえるために母と結婚し、母の方の婿養子になったのか」と、わたしは父の生きざまを追跡しはじめる。わたしの「夢」や「幻想」そして官能がもたらす陶酔がその追跡を助け、あるいは混乱させる。
半ば夢のような時間のなかで飛行場が襲撃され燃え上る。「父はこのあかあかと燃える夜を呪いながら(中略)、この夜に酔っているのではないか」とわたしは考える。浪曼主義の美意識が、エロスと死=タナトスを結びつける。
この死と性的なものの一致は次章「海からの客」の若い助手の美津子と一緒に寝たわたしの、海から上ってくる黒い生き物に父が呑みこまれていく幻想のなかでも暗示されている。生前、父が教鞭をとっていた大学の臨海実験所だった場所を尋ねて、わたしは生きた化石であるカブトガニが集ってくる海岸に立つ。年配の研究者瀬山は、研究所目がけて這い上ってくるカブトガニは戦争で死んだ死者と思っているらしい。若い美津子には戦死者の喩としてのカブトガニというのが分らない。わたしは、その蟹を研究している瀬山先生の胸中が分ってくるにつれて、彼が父と同じように突然いなくなってしまうのではないかという不安に捉われる。瀬山先生が研究所の後輩に、
あの時期に結婚したり子供をつくったり、誰もがそうしたくても出来ないときに、やったじゃないですか。あっち(死の世界―註筆者)に行くのが嫌だったからなんだ。
と責められているのを立ち聞きしてしまったわたしは、瀬山先生が他人とは思えなくなってくる。
第三章でわたしは「鳥たちの島」に出かける。その島が並々ならぬ重力で、水中に潜っているうちに幻聴に襲われて流されたわたしを招き寄せたのだ。それは沖島と呼ばれる裏の名前を持っているが、地図や旅行社で調べても見付からない性質の島なのだ。そこには、「トッコウ、トッコウ」
と鳴く姿の見えない鳥が棲んでいる。この呼び名の起源は「特攻隊」らしいと読者は気付く。漂着したわたしは、島の戦死した特攻隊員の遺児沖田時夫とその母と妹の水奈子に会う。戦死した彼らの父はそのとき二十二歳、わたしの父親は二十四歳で、両者のあいだには、「年齢差以上の階級差」があって、わたしの父は生き残ったのだった。
わたしは戦死した水奈子の父が、その島で一番好きだった場所に案内してもらう。それは岩穴で、清水が湧いている他は何もない場所だ。そこは神が降りる場所のようでもあり、女性の体内、あるいは膣としての洞窟のようでもある。その場所で水奈子は「わたし」の存在の根本の不条理を指摘する。彼女は、
木で出来たようなちゃちな飛行機に片道だけのガソリンを積んで、死ぬために飛び立つ役目を、黙って引き受けたんです。
と戦死した父親のことを言い、
あなたのお父様はわたしたちの父親の上官だったんです。あのころ部下を死地に向かわせる上官は、自分も必ずあとから行く、と言ったそうですね。
と、上官の娘であるわたしに詰め寄る。やがて気持を切り換えた水奈子は、
このときこんなふうに父は死んだ、とはっきりしているわたしの方が(三十年後に父親に突然死なれたあなたより―註筆者)、気が楽なのかもしれませんね。
と和解の言葉をさしのべるが、わたしの心は少しも慰められない。その日、わたしは郷里の家の庭に四羽のトッコウ鳥と覚しき客が舞い降りる夢を見る。十二歳のわたしと父と母が四人を迎える。
沖田守が、
中隊長殿、この奥様とお嬢さんのために、生きのびられたのですか。
と父に質問する。父は卑屈な態度を見せ、わたしは、
父が皆に苛められていることより、父がそれを怯えながらも喜んで受け入れていることの方が、余程怖くて気持悪かった。
と述べる。この記述は私に、サルトルの『嘔吐』のなかで主人公が盛り上った木の根の瘤を見て嘔吐を覚える記述を想起させたのであったが。
やがて客が帰る様子を、わたしが槙の垣根の隙間から見ていると、その男たちの中に父の姿があることを発見する。この光景の描写の中で作者は父の死の原因と形を理解したのだと言ってもいいのかもしれない。
こうして、この父の自死を巡る話は第四章「燃える塔」で物語を閉じる。
この章ではラジオのジョッキーの声などを現代ふうのノイズとして使い、いくら積み上げても崩れてしまうZ聖堂の話を前触れにして肉体を持った父親が登場する。尚、その教会を何度崩されても建てているのはTと呼ばれる年齢不詳の男である。わたしは父に連れられていった研究室の階段で遊んでいた子供の頃の光景を思い描く。そこには働いている父親の姿があった。どこかに重く戦争の影を曳きながら。その父は戦争で死んだ友人の妹らしい女と会っているが、彼女の声はわたしにも似ているのだ。幻想のなかでわたしは父に、
父さんを訪ねる旅はもうこれきりにしようと思ってるんだけど。
と言いかけてやめ、やはり父に付きまとうのである。あたかも、どこまでもどこかにいるはずのもっと別の父を見付けようとしているみたいに。わたしはスナック喫茶「ダイアリー」を探し出す。それは、Z聖堂の庭、東隅のヤツデの木、その横の石灯籠の下、という妙な場所にある。地中のスナックらしい。
その"ダイアリー"で父が飲む器には死んだ戦友や部下の名前が、猫の置物には「必中必沈」というような字が印されている。これは特攻隊の合言葉だったのだろうし、板壁に刻まれている、「20・4・28、20・5・4、20・7・19」というのは特攻隊が出撃した日付ではないかと思われる。だから父が行くスナックの名は"ダイアリー"なのだ。その店で女は、
少年たちは時間に負けて、先生は勝ったの。先生がずるくなかったらこの娘さんは、この世にいなかったんじゃないの。
と父を責める。その責め言葉は、いまや甘く父のからだを溶かしていくようだ。
わたしは何か書かなければという想いに駆られてペンを取る。自分がどんな状況下で生れたのか、などと考えることは意味がない、という意味の元、性の快楽の中から自分のいのちも発生したのだと直感する……、などと書いているとしきりに鐘が鳴る。ふと目をずらすと「終ったよ」という誰かの書いた文字が目にとび込んでくる。
その文字が目にとび込んできた時、神父が登場しTやわたしたちと一緒に砂の聖堂を造りはじめる。Tとは父さんのTかもしれないし特攻隊のTかもしれない。
この重い思想的作品は、
Tの建てた聖堂は、満潮のたびに海に呑まれた。Tは、海に呑まれるために、聖堂を作っているのかもしれなかった。
と言う言葉で終る。
このように、章を追ってくると、作者が力をふり絞るようにして、いかに戦争という不条理が人間存在を逆光のなかに浮び上らせているか、という主題と取組んだかが伝ってくる。
この作品は必ずしも読みやすいものではない。それはひとつには今日の我が国の文学が他の国と違って、こうした人間存在の根本にかかわるような主題を避けているからであり、文学が思想を表現する文脈を失っているからでもある。作者はこうした停滞には目もくれずに果敢な挑戦を試みたのだ。その意味でもこの作品は今日の文学にとって看過することのできない問題を提起した。この主題は今後もいろいろな形で取り上げられるべきものであり、その最初の一歩を踏み出したという意味でもこれは作者本人にとって、記念碑的な作品であるに違いない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする