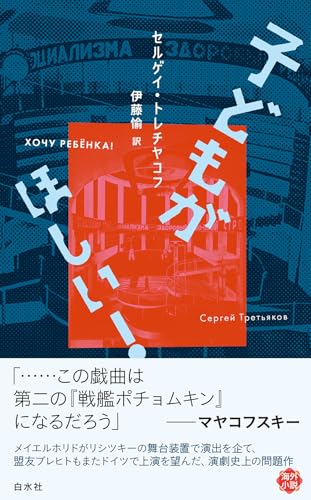書評
『ジートコヴァーの最後の女神たち』(新潮社)
小説の姿で描かれた中欧の歴史と驚異
現代チェコ文学の話題作。原書が二〇一二年に出版されて以来、現在までに世界二十三カ国語に翻訳されたという。舞台となるのは、白カルパチア地方の山あいのジートコヴァー。豊かな自然に恵まれた、文明から隔絶した辺境だ。この地方では、特別な能力を持つとされる「女神」たちが独自の伝統を守ってきた。主人公ドラは母の非業の死の後、伯母スルメナに育てられたのだが、じつは母も伯母もジートコヴァーの女神だった。女神たちは薬草を使って病気を治療するだけでなく、男を女に惚(ほ)れさせることもできた。さらに予知能力を持ち、嵐を静めることもできた(らしい)。このような非科学的な女神という存在は、文明社会と相容れるものではなかったが、病苦や悩みを抱えた人々の心のより所となっていた。ところが、ある日官憲の介入によってのどかな生活は突然絶たれる。スルメナは反社会的な危険人物として警察に連行されてしまうのだ。
時は過ぎ、ビロード革命の九年後、いまや民俗学者となったドラは、公開された秘密警察の文書の中に、伯母スルメナの名前を発見して愕然(がくぜん)とする。はたしてあの伯母が、警察の協力者だったのか? ドラは女神の生涯に織り込まれた謎の解明に乗り出す。それはまたドラ自身の自分探しの長い旅、二十世紀チェコの激しい転変の歴史をさかのぼる困難な旅への出発でもあった。彼女は決意する。「自分の使命は、系譜に連なるすべての女性たちの運命を明らかにし、暗黒の過去から彼女たちの物語を掘り起こ」すことだ、と。
秘密警察の文書を粘り強く調べるうちに、おぞましい事実が次々に明らかになっていく。スルメナは狂人扱いされて国立精神療養所で拷問のような治療を受け、廃人となって死んだ。スルメナを執拗(しつよう)に攻撃し続けた秘密警察の職員の正体は? そして、ドラ自身にかけられていた一族の呪いとは?(女神には善悪の両側に関わる両義性があった) さらに歴史をさかのぼると、ナチ・ドイツのチェコ支配時代には、魔女研究プロジェクトの一環として女神たちが調査の対象になっていた、という衝撃的な事実も明らかになる。親衛隊(SS)長官ヒムラーは、チェコ辺境の女神たちを、古代ゲルマンの巫女(みこ)の自然秘教を受け継ぐものと考えていたのだ。
かくして小説は、戦前のナチ・ドイツ支配時代とそれ以前・戦後の社会主義時代とその後の現代、とあわせて四つの時代を重層的に積み重ねていく。辺境の女神たちは、ナチ・ドイツと共産主義という二つの全体主義に翻弄(ほんろう)されながら辛うじて生き延びたのに、文明化された現代に絶滅してしまった。本書は、常に歴史の主役であった男たちの支配に対抗する原理を担った女たちに焦点を当てた。それは宮田登が『ヒメの民俗学』で論じた、日本古来の女たちの霊的な力にも通じるものだろう。
注目すべきは、「七割以上は実際の資料に基づいている」という本書が、民俗学の研究書ではなく、小説として書かれたということである。本書を中欧版の魔術的リアリズムと呼んでもいいのだが、そういった常套(じょうとう)句では掬(すく)いきれない複雑な陰影を持った、歴史と驚異の交錯する世界がここにはある。それはおそらく、小説でなければうまく書けないものだ。
ALL REVIEWSをフォローする