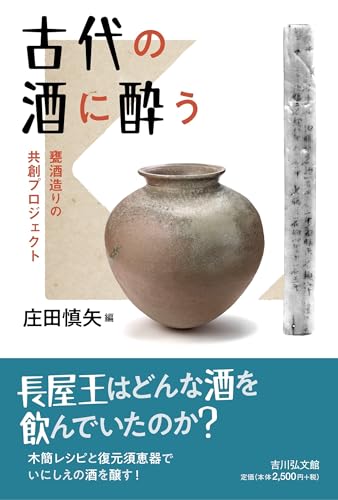書評
『宮本常一──民俗学を超えて』(岩波書店)
権威性をそぎ民衆の小さな声聞く
日本や日本人を主語にした語りには警戒が必要で、警戒せずに濫用(らんよう)し、その資格を問うような語り、つまり、愛しているのか、権利があるのか、と詰め寄る語りを受容したくはない。では、そういった声を避けながら日本や日本人を問うことは可能なのだろうか。いたずらに伝統を持ち出して共有させるような手口を持たない民俗学はひとつの道だろう。本書のサブタイトルに「超えて」とある。何をどのようにして超えるのか。エピローグにミュージシャン・後藤正文の言葉が出てくる。宮本常一からの影響を語りつつ、「政府がやった横暴は絶対に残らないですよ。だから、俺たちは俺たちの民俗史を書き綴(つづ)らないと駄目」と述べる。宮本は渋沢敬三からの「大事なことは主流にならぬことだ。傍流でよく状況を見ていくことだ」との言葉を大切にしていた。民俗学・民俗史が超えるものが時代だとするならば、そこに根ざしている言葉には、似た匂いがある。
『忘れられた日本人』などの代表作を読み解きながら、「均質な『日本』像の持つ画一性に異議を唱え、『日本人』という支配的な言説からこぼれ落ちる人びとと共に生きることを理想に掲げた稀有(けう)な民俗学者」を捉え直していく。
宮本の再評価が始まったのは一九九〇年代半ばだが、その理由として、網野善彦の言葉を受けつつ、「異様に長い耐用年数を持ったその文章の力」と記す。権威性をそぎ落として民衆の声を聞き取る。その場、その時代における、市井のあり方を活写した。
否定的な見解がなかったわけではない。たとえば森崎和江による宮本批判は手厳しい。「わたしは、宮本さんが明るいとみておられる農婦のエロ話と称されるものに、暗さをみる」「日本の民俗学もなさけないな、と思った」と書いた。
外からやって来て、その場に根付いた言葉や文化を掬(すく)い取っていく。その構図への批判に対して宮本自身はどのように向き合ったのか。宮本も民俗学という学問に疑問を持っていた。「日常生活の中からいわゆる民俗的な事象をひき出してそれを整理してならべる」だけでいいのかどうか。
小さな声を意識的に聞き取らなければ、大きな声に揉(も)み消されてしまう。民俗学の態度は、ジャーナリズムの態度にも似ている。聞く対象を特定の事柄や状態を伝えるためのアイテムにするかのように、ことさら象徴的に扱うリスクもある。その恣意(しい)性を書き手や読み手がどうやって自覚すべきなのか。日本列島の隅々まで歩き回った宮本は「日本」という枠組みを俯瞰(ふかん)で語るのではなく、ひとつの場所をズームし、そこにある粒子を見て、声を受け止めた。
とりわけ離島を見た。谷川雁(がん)が宮本への追悼文で記した「眼(め)のまえにある現実の課題を解くために経験と知性のすべてを動員しようとする表情があった」の一文は、離島振興に取り組む宮本への評価だが、他の著作にも通底する評価だろう。
日本も日本人も複数形で存在する。それを単一化させようとする時には強い力がかけられるものだが、よほど意識的にならないと自分自身が強い力の加担者になってしまう。そうならないためにも宮本の民俗学がある。
「超えて」いくために、再度、その中に潜り込める本だ。
ALL REVIEWSをフォローする