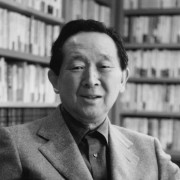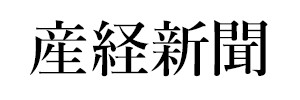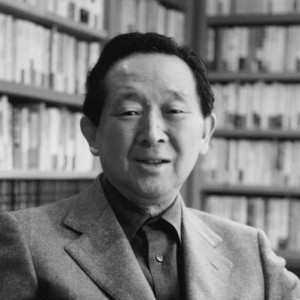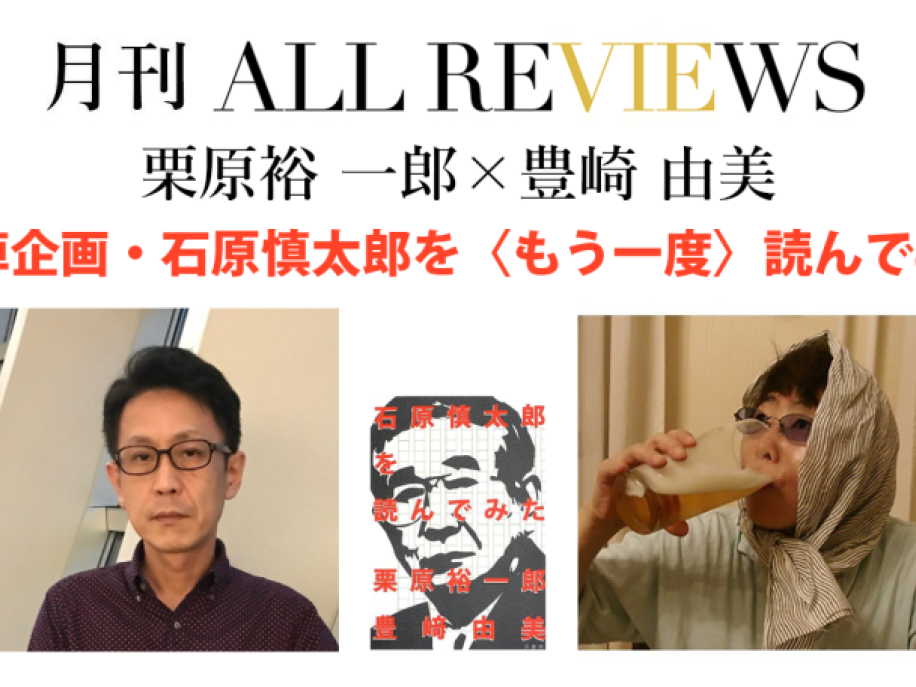書評
『生還』(新潮社)
どの部分を抜き出して読んでも、人間存在のおどろおどろしさ、淋しさが湧き出してくるような作品に久しぶりに接した。
この小説の主人公は末期癌と宣告された製薬会社の経営者である。彼は迷った末、友人の獣医の薦めに従って、仕事からも家族からも離れ、シーボニアというヨットハーバーの一室でコハク酸の一種の酵素を飲み続ける。
死を宣告された主人公が何を考え、感じ、絶望し、憤り、試行錯誤を繰返すかが、そして家族の反応が簡潔に描かれ、次いで、孤独な闘いの有様が、ヨットハーバーの荒々しい自然、季節はずれのわびしい佇い、遊びに来ている若い男女の何の屈託もない様子を背景に語られる。主人公は自死を想い、夢魔に襲われ、今までの、上の空のように思われる生活を振返り、妻や子供達への懐しさ、いとおしさにのたうつ。
個室に連絡してくるのは後事を委せた友人の川野だけである。主人公は独自の療法を試みた結果、体調がゆっくり変ってゆくのを、実験しているような目差しで見つめることを忘れない。その肉体の変化によって惹起される心の迷いとの闘いの様子も、可能なかぎり飾りを落して描写されている。助かるかもしれない、と考えられるようになってからの苦悩は、かえって深くなる。そんな彼にとって、小料理屋で偶然知り合った漁労長の柴田との交遊がわずかに開いた天窓のような役割を果してくれる。三年半の闘病の後、彼は快癒して現世に生還する。
俗界に戻ってみると、自分の生還が、実はどんな意味を持っていたのかが徐々に見えてくる。友人の川野と妻は深い関係になっていて、主人公は妻と離婚する。「だってあなたは、私に、俺を死んだものと思え、俺を忘れろと―」と泣きじゃくる妻の言葉を読んだ時、私は今から三十年ぐらい前までに、多くの帰還兵士の物語が書かれていたのを思い出した。奇跡的に生きて帰れた結果、兵士達がかえって、いかに絶望しなければならなかったかを、当時年少の私は反戦という文脈でしか読んでいなかったと思った。そのもうひとつ奥に、世の常識、通念、つまり本質的に体制に反する行動が、人間をどのような孤立に陥れるか、の問題があったのだ。この作品の主題は、むしろ常識、に反することが、どのように困難な時代かを表現しているのだ。時おり姿を見せる近代的病院は、まさに体制そのものである。今日に生きる人から、いつの間にか失われた権利、それは死ぬ権利であったようだ。ということは生きる権利も、しっかりと体制、制度に握られてしまったのではないだろうか。この体制を、表層的な政治のレヴェルでのみ認識していることの誤りをも、この作品は指摘しているのである。
体制そのものが人間によって作られているだけに、人間存在の奥へと分け入ってゆく視野を持たなければ、本当の生還はあり得ないと思い知らされる。
【この書評が収録されている書籍】
この小説の主人公は末期癌と宣告された製薬会社の経営者である。彼は迷った末、友人の獣医の薦めに従って、仕事からも家族からも離れ、シーボニアというヨットハーバーの一室でコハク酸の一種の酵素を飲み続ける。
死を宣告された主人公が何を考え、感じ、絶望し、憤り、試行錯誤を繰返すかが、そして家族の反応が簡潔に描かれ、次いで、孤独な闘いの有様が、ヨットハーバーの荒々しい自然、季節はずれのわびしい佇い、遊びに来ている若い男女の何の屈託もない様子を背景に語られる。主人公は自死を想い、夢魔に襲われ、今までの、上の空のように思われる生活を振返り、妻や子供達への懐しさ、いとおしさにのたうつ。
個室に連絡してくるのは後事を委せた友人の川野だけである。主人公は独自の療法を試みた結果、体調がゆっくり変ってゆくのを、実験しているような目差しで見つめることを忘れない。その肉体の変化によって惹起される心の迷いとの闘いの様子も、可能なかぎり飾りを落して描写されている。助かるかもしれない、と考えられるようになってからの苦悩は、かえって深くなる。そんな彼にとって、小料理屋で偶然知り合った漁労長の柴田との交遊がわずかに開いた天窓のような役割を果してくれる。三年半の闘病の後、彼は快癒して現世に生還する。
俗界に戻ってみると、自分の生還が、実はどんな意味を持っていたのかが徐々に見えてくる。友人の川野と妻は深い関係になっていて、主人公は妻と離婚する。「だってあなたは、私に、俺を死んだものと思え、俺を忘れろと―」と泣きじゃくる妻の言葉を読んだ時、私は今から三十年ぐらい前までに、多くの帰還兵士の物語が書かれていたのを思い出した。奇跡的に生きて帰れた結果、兵士達がかえって、いかに絶望しなければならなかったかを、当時年少の私は反戦という文脈でしか読んでいなかったと思った。そのもうひとつ奥に、世の常識、通念、つまり本質的に体制に反する行動が、人間をどのような孤立に陥れるか、の問題があったのだ。この作品の主題は、むしろ常識、に反することが、どのように困難な時代かを表現しているのだ。時おり姿を見せる近代的病院は、まさに体制そのものである。今日に生きる人から、いつの間にか失われた権利、それは死ぬ権利であったようだ。ということは生きる権利も、しっかりと体制、制度に握られてしまったのではないだろうか。この体制を、表層的な政治のレヴェルでのみ認識していることの誤りをも、この作品は指摘しているのである。
体制そのものが人間によって作られているだけに、人間存在の奥へと分け入ってゆく視野を持たなければ、本当の生還はあり得ないと思い知らされる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする