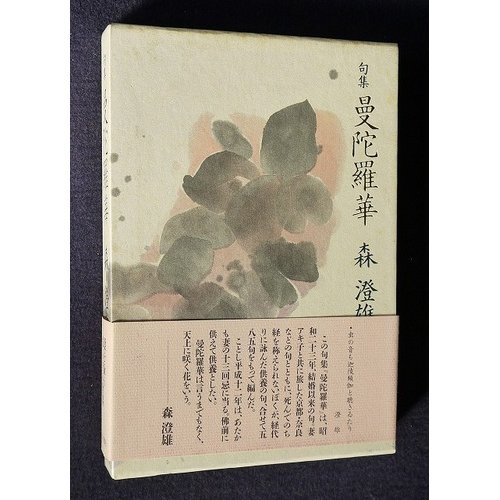書評
『田園風景』(講談社)
「文学は、現実の動きを反映しているのか」「現代にとって文学とは何なのか」「文学の衰退は防ぐことができるのか」
といった類の問題提起が近頃よく見られるようになった。それにはいくつかの外的条件が作用しているのであろう。そのひとつは、ソ連の瓦解などに現われている世界の仕組みの大きな変化である。冷戦の消滅後、より確かな拠り処を、民族とか宗教に求めようとする人々が増大した結果、地域紛争が烈しくなっていること、自由市場体制の爛熟がバブル崩壊となって世界の経済を混乱に陥れており、産業社会とは一体何だったのかという疑問を人々の胸に植えつけたこと等々。
これらの情況が人々に久しく忘れられていた、「人間とは何か」という疑問、ひいては「文学の問題」を想起させたのでもあったろう。
たしかに、第二次大戦後今日まで、わが国の現代文学が、現実に対して文学でなければできないどんな役割を果たしてきたのか、という疑問は、問題形成の当否をも含めて論議される必要があるのではないか。それこそ湾岸戦争を契機にして「詩に何ができるか」という論争が詩壇に起こったように。
坂上弘の九つの短篇からなる『田園風景』をこうした背景のなかで読む時、何気ない触れ方で描かれたこれらの作品のひとつひとつがじつは軽く読み過ごすことのできない大きな問題を含んでいることに気付かされるのである。陳腐な言い方かもしれないけれども、人と人との何ということのない行きずりの触れ合いにも、その時代や世界が映っていると言ってもいいかもしれない。
作品に登場する主人公は、「短い一年」の仁木睦男、「向かいて聞く」の慶介をのぞいて名前を与えられていない。くたびれた中年の会社人間である主人公は、決して感受性や心の柔らかさを大切にしようとはしない、効率追求の組織のなかで、どう生きていったらいいか戸惑っている。彼らは、原因が分からずに左遷されたり、突然海外勤務を命ぜられたりする。
その任地先で、会社人間ではない家族や女に出会った時、主人公の心は揺れる。そこから友情が拡がったり恋が生まれたりする。しかし主人公はその人間関係を深め、育ててゆくことで自らも変わっていこうとする活力を持っていない。やがて、これらの人間関係は、主人公の転勤とか帰国で終わりを告げる時の流れのなかに消えてゆく。いずれ、それは忘れられるだろう。主人公は、二人が本当の触れ合いを求めて「プールに飛込む」ように飛び込むとすれば、「自分が彼女をひどく傷つけることになる」と知っているので、黙ってひとりで飛行機に乗る。また、「田園風景」の主人公のように
「何かちがうものにとらわれ、ちがうものを発見する。そういうことが自分におこらないともかぎらない。これを期待するのが私のばかなところかもしれないが」
と醒めた目で自分を観察しているから、「何かちがうもの」は決して主人公には訪れないことを読者は予感するのである。
この主人公の述懐こそ、作品集『田園風景』の主題と言ってもいいのではないか。
劇的状況の主役になる立場を捨てている主人公の周辺には、身も心も産業社会に同調している人間や、日本を捨て、社長でも専務でもない〝人格的〟指導力で漆器や焼物の工芸品工場を作り、〝酩酔亭〟と命名した小屋に住んでいる小学校の友人などが登場する。その工場で働いている少女たちは、「日本の伝統産業と競争する」などという考えとは程遠い屈託のない夢みるような笑顔を見せるのである。
ここには、簡潔で透明な描写のなかに日常生活の矛盾や深淵を浮かび上がらせる坂上弘のポエジーが見事に現われている。
作者が従来の枠組みを壊そうとしている努力を読みとり、その試みは何故成功したか、あるいは失敗したのかを解明して、その作家の次の仕事の役に立つのが批評というものの効用だとすれば、この『田園風景』を成功に導いたのは他ならぬ作者のポエジーであり、その詩心をもって本来は扱いにくい素材にあえて挑戦したところに、この作品のオリジナリティが生まれたのだと指摘すべきであろう。言いかえれば坂上弘流に現代の扉を押し開いたのである。
【この書評が収録されている書籍】
といった類の問題提起が近頃よく見られるようになった。それにはいくつかの外的条件が作用しているのであろう。そのひとつは、ソ連の瓦解などに現われている世界の仕組みの大きな変化である。冷戦の消滅後、より確かな拠り処を、民族とか宗教に求めようとする人々が増大した結果、地域紛争が烈しくなっていること、自由市場体制の爛熟がバブル崩壊となって世界の経済を混乱に陥れており、産業社会とは一体何だったのかという疑問を人々の胸に植えつけたこと等々。
これらの情況が人々に久しく忘れられていた、「人間とは何か」という疑問、ひいては「文学の問題」を想起させたのでもあったろう。
たしかに、第二次大戦後今日まで、わが国の現代文学が、現実に対して文学でなければできないどんな役割を果たしてきたのか、という疑問は、問題形成の当否をも含めて論議される必要があるのではないか。それこそ湾岸戦争を契機にして「詩に何ができるか」という論争が詩壇に起こったように。
坂上弘の九つの短篇からなる『田園風景』をこうした背景のなかで読む時、何気ない触れ方で描かれたこれらの作品のひとつひとつがじつは軽く読み過ごすことのできない大きな問題を含んでいることに気付かされるのである。陳腐な言い方かもしれないけれども、人と人との何ということのない行きずりの触れ合いにも、その時代や世界が映っていると言ってもいいかもしれない。
作品に登場する主人公は、「短い一年」の仁木睦男、「向かいて聞く」の慶介をのぞいて名前を与えられていない。くたびれた中年の会社人間である主人公は、決して感受性や心の柔らかさを大切にしようとはしない、効率追求の組織のなかで、どう生きていったらいいか戸惑っている。彼らは、原因が分からずに左遷されたり、突然海外勤務を命ぜられたりする。
その任地先で、会社人間ではない家族や女に出会った時、主人公の心は揺れる。そこから友情が拡がったり恋が生まれたりする。しかし主人公はその人間関係を深め、育ててゆくことで自らも変わっていこうとする活力を持っていない。やがて、これらの人間関係は、主人公の転勤とか帰国で終わりを告げる時の流れのなかに消えてゆく。いずれ、それは忘れられるだろう。主人公は、二人が本当の触れ合いを求めて「プールに飛込む」ように飛び込むとすれば、「自分が彼女をひどく傷つけることになる」と知っているので、黙ってひとりで飛行機に乗る。また、「田園風景」の主人公のように
「何かちがうものにとらわれ、ちがうものを発見する。そういうことが自分におこらないともかぎらない。これを期待するのが私のばかなところかもしれないが」
と醒めた目で自分を観察しているから、「何かちがうもの」は決して主人公には訪れないことを読者は予感するのである。
この主人公の述懐こそ、作品集『田園風景』の主題と言ってもいいのではないか。
劇的状況の主役になる立場を捨てている主人公の周辺には、身も心も産業社会に同調している人間や、日本を捨て、社長でも専務でもない〝人格的〟指導力で漆器や焼物の工芸品工場を作り、〝酩酔亭〟と命名した小屋に住んでいる小学校の友人などが登場する。その工場で働いている少女たちは、「日本の伝統産業と競争する」などという考えとは程遠い屈託のない夢みるような笑顔を見せるのである。
ここには、簡潔で透明な描写のなかに日常生活の矛盾や深淵を浮かび上がらせる坂上弘のポエジーが見事に現われている。
作者が従来の枠組みを壊そうとしている努力を読みとり、その試みは何故成功したか、あるいは失敗したのかを解明して、その作家の次の仕事の役に立つのが批評というものの効用だとすれば、この『田園風景』を成功に導いたのは他ならぬ作者のポエジーであり、その詩心をもって本来は扱いにくい素材にあえて挑戦したところに、この作品のオリジナリティが生まれたのだと指摘すべきであろう。言いかえれば坂上弘流に現代の扉を押し開いたのである。
【この書評が収録されている書籍】
中央公論 1993年2月
雑誌『中央公論』は、日本で最も歴史のある雑誌です。創刊は1887年(明治20年)。『中央公論』の前身『反省会雑誌』を京都西本願寺普通教校で創刊したのが始まりです。以来、総合誌としてあらゆる分野にわたり優れた記事を提供し、その時代におけるオピニオン・ジャーナリズムを形成する主導的役割を果たしてきました。
ALL REVIEWSをフォローする