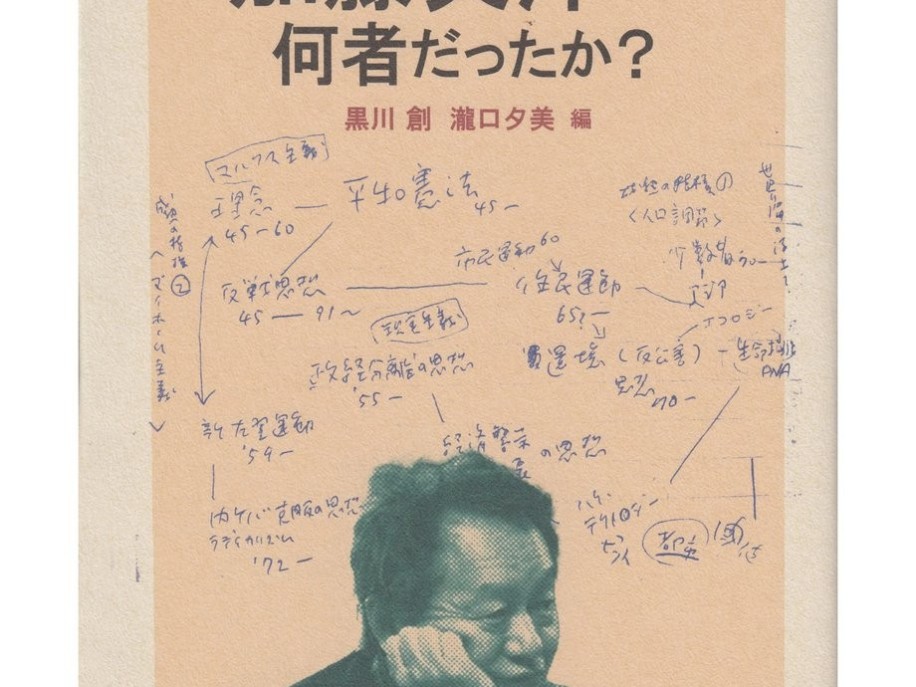書評
『戦後入門』(筑摩書房)
戦後生まれの戦後入門
戦後70年経(た)った(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2015年)。昭和22年生まれの私がもう68才なんだから、戦争が終わって70年たったとして驚くにあたらないが、驚く。68年、ずっと戦後に暮らした者としての印象を言うなら、「戦争のことは話題にしたくもない、もうこりごりだし考えたくもない」というのが世間の空気だった。
学校でも、戦争のことは教わらなかった。教科書に戦争のことも書いてあったろうが、授業ではたいがいそこまでいかないのだ。後は自分で読んどけと言われたって、読むはずない。
GHQのさしがねだったかもしれないし、現場の先生も、何と教えたものか、なるべくやりたくなかったのかもしれない。
戦争を体験した世代の人は、戦争に敗(ま)けたことを、悔しがったり、屈辱ということをいうけれども、外国の軍隊が駐留していることも、その外国、アメリカに従属していることの実感も関心も、戦争を知らないコドモ達の我々にはなかった。
屈辱というならたとえば日米地位協定だけれども、米軍の兵士が日本の少女に性犯罪を犯したのを日本に処罰させないという理屈がわからない。なぜ、さっさと引き渡さない?
なぜ犯罪者の肩を持つ? 屈辱というなら、恥ずかしいのはむしろアメリカ人のほうだろう。
このへんの感覚が、今も、コドモの頃とかわらないのは、そういうことをちゃんと考えた事がないからだろう。戦争はやらないのが正しいんなら、そのやり方も知らなくていい。戦争の話をするのも汚らわしいというのが世間の気分だった。
たとえば「毒ガス」を使用するのが「国際法違反」だという理屈がわからない。なぜ原爆がアリなのに「毒ガス」はダメか?
原爆は、早い者勝ち、持ったもん勝ちだが、後から持とうとしたり、作ろうとすれば、じゃまをするっていう理屈もわからない。
おかしいじゃないか?と思うけれども「そういうもんなのよ」と世間が言わんばかりなので、そういうもんなのかと自分で丸めてのみこんできた。
日本の敗戦が明白なのに、アメリカはダメ押しのように原爆を二発も落としたのだ。なんでそんなことをするのか、なんでそんなことができるのかわからない。
よくそんなことをする。キリスト教とかって、そういうことをゆるすような宗教なのか。
人の持ってるものを欲しがって、力ずくでそれをもぎとるのは普通恥ずかしい行いだ。
自分が正しいというのを証明するために暴力に訴えるとしたらそれは単なるバカだろう。
個人がしたらそうなることを、国がすると「国益」だとかいう。おかしな話だ。
この本は、そういう素朴な疑問に、とてもていねいに答えてくれる。うかうか老人になるまで、そういうことを知ろうともしないで、年だけとってきてしまった。
「いまから知ってもおそくない」
私は、この本を同世代の人々に特にすすめたい。
ALL REVIEWSをフォローする