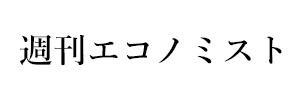書評
『ウィトゲンシュタインと同性愛』(未来社)
一九七三年に出版されるや、たちまち大きな反響を呼んだ問題の書の翻訳である。その理由は、書名から察せられよう。原題は『ウィトゲンシュタイン』だが、《本書がひきおこした論争からすれば、この書名こそもっともふさわしいと判断した》(訳者あとがき)。小河原氏が、『同性愛』をつけ加えた。
ヴィトゲンシュタインが同性愛者であった事実に目をつぶったら、生涯にわたる彼の苦悩を理解できなくなってしまうというのが、著者バートリーの主張である。けれども、同性愛をじかに論じた部分は、書名から予想されるほど多くない。《約四、五頁にわたってごく手短に言及されている》(二一三頁)にすぎない。それよりも《本書の眼目》は、《彼の「失われた年月」、すなわち、小学校教師時代》(訳者あとがき)に焦点をあてたところにある。
ヴィトゲンシュタインには、『論理哲学論考』を執筆した若い日々から、ケンブリッジに戻る四十歳までの間に、空白の十年間があった。彼はこの期間、オーストリアの寒村で小学校の教師を務め、そのあと園丁をしたり、姉の邸宅の設計・建築にたずさわったりしていた。哲学にまったく興味を失った時期として、これまで人びとの関心をひくことがなかった。
著者バートリーが一九六七年に、たまたまその寒村をたずね、いまは年老いた彼の教え子たちに出逢ったことが、本書を生むきっかけになった。村人たちは、教師ヴィトゲンシュタインのことをよく覚えていて、興味ぶかい証言をした。その結果、著者は、この時期こそ、前期(論理学研究の時代)と後期(言語ゲームの時代)とをつなぐ、きわめて重要な時期であるとの結論に達する。
たとえば「嘘つきのパラドクス」を、ヴィトゲンシュタインは子供たちに教えている。また、彼の教育法は、当時オーストリアで試みられていた、ゲシュタルト心理学の流れをくむカール・ビューラーの学校改革運動と軌を一にしている。岩石を採集に山野を歩き、模擬装置をこしらえ、『小学生のための単語帳』をこしらえたヴィトゲンシュタインの実践は、この運動の精神を体現するものである。
こう考えてくると、『哲学探究』の言語ゲームの議論も、この延長上で理解できそうだ。すなわちそれは、《児童言語心理学の概要を展開する試み》、《子供は母国語をどう習得するのかという問題に焦点をあて》(一七三頁)たものなのだ。
著者バートリーは、ヴィトゲンシュタインその人の人格に尊敬の念を隠さないが、彼の哲学には極めて批判的である。批判のすべてが納得できるものとは思わなかったが、本書が、ヴィトゲンシュタインについて考える場合、必ず参照すべき一冊となるだろうことは確かだ。
最後に、同性愛に話を戻そう。どこまでその証拠があがっているのだろうか。今回の日本語版には、一九八五年に書かれたあとがき「ウィトゲンシュタインと同性愛」も訳されていて、初版への批判に対する著書の反論も読むことができる。でも証拠になるのは、未公開だった初期草稿の一部に《自慰行為……の記録》があるというくらいで、ほんとうに同性愛で悩んだとされる一九二八、二九年以降の時期、「プラーター公園の……彼を性的に満足させる用意のあった粗野な若者》(五二頁)について、具体的な材料がなにもあがっていない。真相は闇の中、ということなのだろう。
【この書評が収録されている書籍】
ヴィトゲンシュタインが同性愛者であった事実に目をつぶったら、生涯にわたる彼の苦悩を理解できなくなってしまうというのが、著者バートリーの主張である。けれども、同性愛をじかに論じた部分は、書名から予想されるほど多くない。《約四、五頁にわたってごく手短に言及されている》(二一三頁)にすぎない。それよりも《本書の眼目》は、《彼の「失われた年月」、すなわち、小学校教師時代》(訳者あとがき)に焦点をあてたところにある。
ヴィトゲンシュタインには、『論理哲学論考』を執筆した若い日々から、ケンブリッジに戻る四十歳までの間に、空白の十年間があった。彼はこの期間、オーストリアの寒村で小学校の教師を務め、そのあと園丁をしたり、姉の邸宅の設計・建築にたずさわったりしていた。哲学にまったく興味を失った時期として、これまで人びとの関心をひくことがなかった。
著者バートリーが一九六七年に、たまたまその寒村をたずね、いまは年老いた彼の教え子たちに出逢ったことが、本書を生むきっかけになった。村人たちは、教師ヴィトゲンシュタインのことをよく覚えていて、興味ぶかい証言をした。その結果、著者は、この時期こそ、前期(論理学研究の時代)と後期(言語ゲームの時代)とをつなぐ、きわめて重要な時期であるとの結論に達する。
たとえば「嘘つきのパラドクス」を、ヴィトゲンシュタインは子供たちに教えている。また、彼の教育法は、当時オーストリアで試みられていた、ゲシュタルト心理学の流れをくむカール・ビューラーの学校改革運動と軌を一にしている。岩石を採集に山野を歩き、模擬装置をこしらえ、『小学生のための単語帳』をこしらえたヴィトゲンシュタインの実践は、この運動の精神を体現するものである。
こう考えてくると、『哲学探究』の言語ゲームの議論も、この延長上で理解できそうだ。すなわちそれは、《児童言語心理学の概要を展開する試み》、《子供は母国語をどう習得するのかという問題に焦点をあて》(一七三頁)たものなのだ。
著者バートリーは、ヴィトゲンシュタインその人の人格に尊敬の念を隠さないが、彼の哲学には極めて批判的である。批判のすべてが納得できるものとは思わなかったが、本書が、ヴィトゲンシュタインについて考える場合、必ず参照すべき一冊となるだろうことは確かだ。
最後に、同性愛に話を戻そう。どこまでその証拠があがっているのだろうか。今回の日本語版には、一九八五年に書かれたあとがき「ウィトゲンシュタインと同性愛」も訳されていて、初版への批判に対する著書の反論も読むことができる。でも証拠になるのは、未公開だった初期草稿の一部に《自慰行為……の記録》があるというくらいで、ほんとうに同性愛で悩んだとされる一九二八、二九年以降の時期、「プラーター公園の……彼を性的に満足させる用意のあった粗野な若者》(五二頁)について、具体的な材料がなにもあがっていない。真相は闇の中、ということなのだろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする