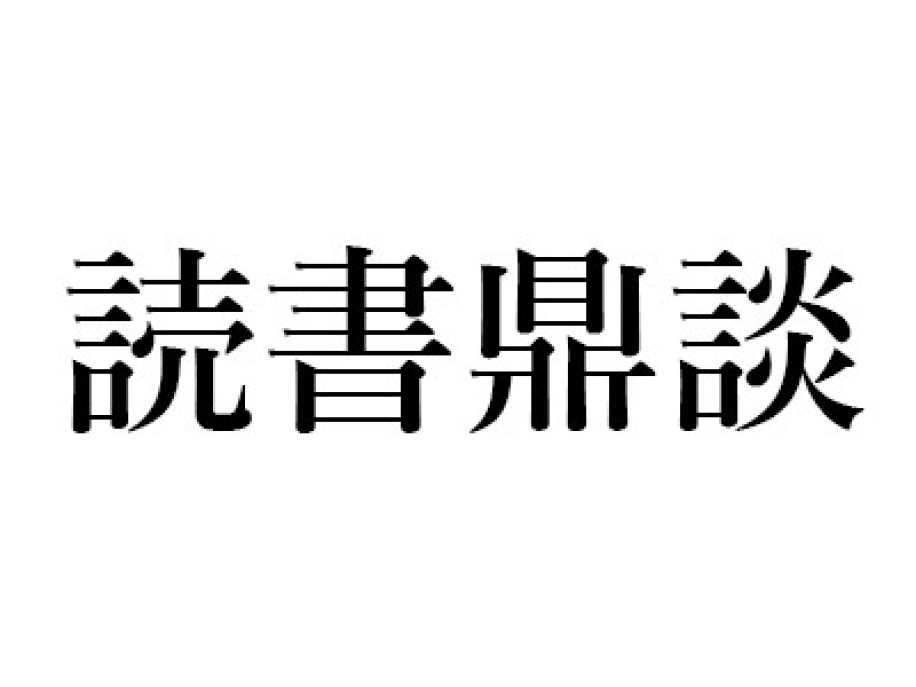書評
『袋物のはなし』(未来社)
縫うことのよろこび
苛酷な生、とどこかに書いたら、この平和で豊かな時代に何が、といわれた。そうだろうか。そうは思わない。泣きたいこと、腹の立つこと、毎日どっさりある。そういうときちくちく木綿を縫う。花ふきんや子どもの保育園の袋物をちくちく……。縫い物仲間に出会ったような気持ちで森南海子著『袋物のはなし』(未来社)を読み出した。
「私たちの暮らしの中から消えていった袋たちのことを、ちょっと考えてみたいのです」
まずは洗顔用の糠(ぬか)袋。「母は化粧っ気のない人なのに、洗顔にだけは熱をいれていて、心ゆくまで糠袋でこめかみから額を、そして頬をゆっくり撫で、お風呂のときだけはあらゆる家事から解放されて、のんびりくつろいでいたのが深く印象に残っています」
「丹念でこざっぱり」した文章に心がほどけてくる。「私はどうしても晒もめんの持つしなやかな風合いは忘れたくないのです」
したいのです、したくないのです、という言葉が祈りのように繰り返される。それは見かけの豊かさ、インスタント、使い捨ての時代に、まっとうなくらしを手放すまいという決意なのだろう。
出雲に里をもつひとからお米袋が届く。袋は十三枚の端ぎれから作られていた。女の子の可愛らしげな模様に混じった、男模様の船の図柄のきれに目をとめる。そこから「男の子たちが湯上がりにひとさわぎしているさまや、夕暮れにもなお家路につかず、たわむれているさま」がパアッと浮かぶ。なんという想像力だろう。
端ぎれをつなげてつくるのは村の衆の力をかりて幼な児を息災に育てる願いだろうか。斜めに布をよじってつくる袋は体の動きに合っているからかつぎやすいのかしら……。いっしょに考えているうちに、私はたちまち袋物のゆたかな世界に連れ去られた。コーランを入れる袋、数珠を入れる袋、お坊さんの頭陀袋の紐はえりのように肩にやさしい。匂い袋、信玄袋、合財袋。なんて豊かな袋の文化だろう。「いせこみ」(いい言葉だ)のついた袋を、森さんは「子宮のような味わい」と表現する。自由にふくらんだりちぢんだりして、体になじむやわらかさ。
読んでいるうちに断然、袋をつくりたくなった。幸い、図面がたくさん入っている。著者も仲間と競争で袋をつくるという。図書館の司書がハンカチを斜めにたたんだブックカバーをみせる。その薄さ軽さ、切符もはさめる形にハッとしたり、全盲のお母さん作の腕にかける手さげに感心する。手先はあけておかなければならないからだ。
「ひょっとすると晴眼者というのは、手さげ袋を手や肩で持たずに、実は『みた眼』で持ってしまっているのではないでしょうか」。さりげない、そして心にくい、しめの一文。
男の人のように上衣のポケットから軽やかにペンや文庫本を取り出してみたいと思う。
「女は所詮、軽装など無理ではないのか。男たちが、地平線のかなたを見つめるようにして素手をかざし、いそぎ足に去って行くようにはいかぬ。女の足どりは重い。曲がりくねった道を荷をさげてさまよう。子供を担い、ときには親たちや祖父母や夫までを担い、引きずって歩く」
森南海子さんは、奇をてらいがちなファッション界にあって、めずらしく生活の大道をゆく。負うものの多い苛酷な性をいたわりながら、生きていくのにとどのつまり、何が必要かを見すえている。
ALL REVIEWSをフォローする