書評
『機械状無意識―スキゾ分析』(法政大学出版局)
ポスト・モダン哲学の旗手ガタリが、大作家マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』を批評した問題の書。原著は一九七九年に出版されている。その内容は、さすがガタリだけあって一筋縄ではいかない。
全体は二部からなる。第Ⅰ部「機械状無意識」は、分析の方法論をのべる部分。キー・ワードはアジャンスマン(鎖列)とリトネルロ(テンポ取り作用)だ。この原理が、作品のいろいろな要素を空間的・時間的に配列して全体を組み立てているーどうやらそういうことが書いてあるらしいのだが、ほんとうにそうかどうか、私は自信がない。
第Ⅱ部はいよいよ作品分析。〈「失われた時を求めて」は驚くべき一大リゾーム地図である。……それ自体で一つのスキゾ分析的モノグラフである〉(二五五頁)。こう宣言する著者は、思い切りよく、作品をズタズタに切り刻んでしまう。なるほどポスト・モダン批評である。
どう控え目に言っても、この本は難解だ。たとえば〈諸表現素材へのある種の詩的受動性……が創造への道を開く。この受動性は、支配的ファルス至上主義的価値観のコンテクストにおいては、プルーストによって女性らしさとして体験される〉(三四四頁)とある。これなど「プルーストは何を見ても、創作意欲を刺戟された。ただ、自分がホモなので気がとがめ、女性らしさに魅かれがちだったけれど」という意味なのだろうか。
ガタリは「顔面性成分の軌跡」と称して、ある作中人物の顔が、さまざまな別な人物の顔とイメージがつながっている、という多角的な網の目を追いかけたりしている。なかなか面白い着眼だ。でもこういう分析が、プルーストの作品の価値や味わいとどういう関係があるのか、よくわからなかった。
とにかく本書は、よく出回っているポスト・モダン批評の種本らしい。「文学部唯野教授」の第9講も、本書の理解の助けになる。
【この書評が収録されている書籍】
全体は二部からなる。第Ⅰ部「機械状無意識」は、分析の方法論をのべる部分。キー・ワードはアジャンスマン(鎖列)とリトネルロ(テンポ取り作用)だ。この原理が、作品のいろいろな要素を空間的・時間的に配列して全体を組み立てているーどうやらそういうことが書いてあるらしいのだが、ほんとうにそうかどうか、私は自信がない。
第Ⅱ部はいよいよ作品分析。〈「失われた時を求めて」は驚くべき一大リゾーム地図である。……それ自体で一つのスキゾ分析的モノグラフである〉(二五五頁)。こう宣言する著者は、思い切りよく、作品をズタズタに切り刻んでしまう。なるほどポスト・モダン批評である。
どう控え目に言っても、この本は難解だ。たとえば〈諸表現素材へのある種の詩的受動性……が創造への道を開く。この受動性は、支配的ファルス至上主義的価値観のコンテクストにおいては、プルーストによって女性らしさとして体験される〉(三四四頁)とある。これなど「プルーストは何を見ても、創作意欲を刺戟された。ただ、自分がホモなので気がとがめ、女性らしさに魅かれがちだったけれど」という意味なのだろうか。
ガタリは「顔面性成分の軌跡」と称して、ある作中人物の顔が、さまざまな別な人物の顔とイメージがつながっている、という多角的な網の目を追いかけたりしている。なかなか面白い着眼だ。でもこういう分析が、プルーストの作品の価値や味わいとどういう関係があるのか、よくわからなかった。
とにかく本書は、よく出回っているポスト・モダン批評の種本らしい。「文学部唯野教授」の第9講も、本書の理解の助けになる。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
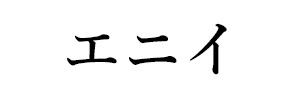
エニイ 1991年4月
ALL REVIEWSをフォローする

































