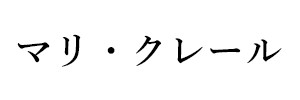書評
『リゾーム…序』(朝日出版社)
この本はまず本についての考え方、言葉についての考え方、それから本が成立つのに、ぜひとも必要だとされる中味についての考え方、また中味を作りだすために行使されている精神の働きについての考え方、それからひとつの本がここに在り、まだ少年期を脱け出したすぐの時期に、ズィズ・イス・ア・ブックというふうに習ったことがある「この本」の存在の仕方についての考え方、これらをぜんぶいままでと変えることにしようと、提案している本だということができる。また、提案以上でもそれ以外でも、またそれ以下でもない。
そこでまず、ひとつの本が、紙をある判型に区切って束ねたものに、文字が印刷されていて、その文字を書き連ねたひとりの著者が、個性と個性の由来と、知識の蓄積とその由緒ある出自を傾けて表現したものから出来ている、という考え方をやめようという提案から、この本ははじまっている。著者はG・ドゥルーズとF・ガタリという二人の連名になっている。だが著者たちは言う。習慣上そうしているだけで、G・ドゥルーズが、すでに幾人かから出来上っており、F・ガタリもまた幾人かから出来上っているので、大勢がいろいろな位置と視角から手を出して「この本」に始末をつけ、また「この本」からさまざまな場所や人や現実の地層や地盤にたくさんの触手を延ばし連結するように、しつらえられた多面多様体だというように、「この本」を理解するよう求められている。もちろんG・ドゥルーズがどの個所を書き、F・ガタリがどの部分の執筆を担当しといったことは、まるでわからないようにしてあるし、ただ無署名の多様な手が集まっていることの象徴としてしか、「この本」の共著者の名前には意味がない。そういう理念が「この本」だし、一般に「本」というものはどれも、そんなふうに読まれるべきだし、そんなふうに存在すべきだという理念が、著者たちの宣明に当っている。
わたしたちがふつう本の中味とか、意味とか、本を流れている理念とか呼んでいるものは、著者たちにとっては存在しないものだ。本はそれ自体が小さな「組みこみ」機械で、本の外部にある性愛とか戦争とか革命とか官庁とか動物とか植物とかを、どんなふうに「組みこみ」あいを作り出し、どんな地盤や傾斜や領地を作りあうかということがあるだけなのだ。ふつうはそう考えられていない。著者たちが多発している比喩を使えば、本には中心となり根となる理解があり、そこから展開や意味作用や分岐があって樹木のように枝葉を繁らしていて、その全容はうつ然とした大木のように統一し、内閉した世界を作っているとかんがえられている。だがそういうのは嘘なのだ。強いて植物の比喩をもってくれば、いつでも根が茎でありながら、また根でもあり、中心もなければ枝葉もなく、どの部位も茎でありながら根でもあるさまざまな触手によって、本の外部にある事物と連結しようとしてうごめいているような「リゾーム(根茎)」が、本のほんとうの姿なのだ。そしてこれはたんに本の姿というだけではなく、人間の身体も、思考作用も、それから世界像も、リゾーム状の連結機械としてできている。これがD-G(ドゥルーズ+ガタリ)の基本的な考え方として提案されている。
では世界連結の「組みこみ」機械であるリゾームには、どんな原理があるのか。著者たちはいくつか、その原則を列挙し、説明を加えている。それはおよそつぎのようにたどることができる。
まずこのリゾームは、どんな一点からでも外部にあるどんな点とも接合されうる。そこでは特殊な民族語もなければ、逆に均質的な言語共同体もない、たまたま政治的なリゾームのうちひとつの支配的な言語が権力を奪ったところでは、民族語の流通圏が固定化されて存在しているだけだ。
またリゾームは多様な場所からたくさんの連結の触手を出して、外とつながっているときには、客体にも主体にも統一性などはなく、ただ多面的な多様体として、中心などはどこにもないような、またどこにも帰属することのないような開かれた実体を形成している。そしてこの実体は意味によってさまざまな構造を区分けしたりすることはないかわりに、意味のない個所で、勝手に切断したり折りまげたりすることができる。それはリゾームがたくさんの分節線を含んでいて、その分節線に則して地層や領域や意味や帰属を分類することができるとともに、どんな意味でもないし、属領化もできないような非属領化の線も含んでいて、この線に則してゆけば、いつでもどこか外部へ脱出できるようになっているからだ。
リゾームには、それに沿って生成し展開してゆくような、特異な生成の軸もなければ、さまざまな構成物にその基盤のところで繋がりをもたせているような深層構造もない。だから自己を再現するための契機となるような、均衡も無意識の記憶もない。ただいつでも連結ができ、組みこみができ、変貌することもできるようなたくさんの入口と出口とを持っているだけだ。これが塞がれてしまうと、リゾームはだんだんと流れがある個所で停滞し、ある個所ではまえよりもスムーズになるといった変化のあげくに、根がありそれと区別される幹と枝ができ、葉が繁り、うつ然としたひとつの世界を作る樹木の系統図に変貌してしまう。いいかえれば著者たちによるリゾームという中心概念の新規な設定が、従来の系統樹的な認識の秩序と階程にたいしてもっている意義もまた、中心集約的な認識の仕方、中心という考え、根幹と枝葉という考え方、うつ然たるひとつの世界の輪郭という考え、継時的にいえば記憶と無意識の暗がりの方から、出自と系譜が歴史的にもエディプス的にも由来するという考え方を、否定しようとするモチーフに発していることがわかる。だがなぜこういうモチーフを著者たちは必要としたのか、この考えは鳴り物を入れるほど効果的かとかんがえていくと、それほどはっきりしたことは構想されていない。これは著者たちの主著のひとつ『アンチ・オイディプス』を読んだときにも共通して感じるものだ。たぶんわたしたちには事情がよくわからない心的な外傷が著者たちにあって、リゾームという概念を作り出しているとおもう。この本でいえば、繰返し固執されている精神分析学にたいする過剰な否定にその外傷が象徴されている。つぎに引用するのがそれに該当する個所だ。またこの本の中心的なモチーフなので、丁寧に筆写しておく。
これは精神分析にたいする相当にひどい反感の表明にあたっている。そんなに反感をもついわれが、もてなかったとしたら? リゾームは何ら専制的な権力を行使していないかわりに、格別の有効性ももたないとしたら? たしかに無意識が振る舞う仕方にたいするフロイトの概念は専制的だし、乳幼児のとき、とくに授乳期にすでに無意識が意識的な人格とかかわりない振る舞い方を確定してしまうという見方は、宿命観的であって、けっして愉快なことではない。だが、だからといって無意識が手易く産出できるかのようなことを、言いふらすのはいかがなものか? 無意識と遺伝子的な素因のあいだには、まだよくわからない関係と断絶とが介入しているとおもわれる。でもフロイトの無意識には専制的なところもなければ、そんな意図もない。ただフロイトはたしかに精神とくに無意識の表情が、顔の表情とおなじように自然権的であり、これを左右するにはエディプスの直接性、その直接を無数の層状物のようにとりまき、条件づけている完全な偶然(つまり必然)というものを考慮すべきであり、それがほとんど自然生理的な宿命にちかいほど、人間という種は動物的で植物的であると考えられていたようにおもえる。この本の著者たちは、何かわたしたちにはうかがいしれない理由を混えて、フロイトの精神分析に不服であり、フロイトの無意識の根拠であるエディプス(母親の専制期)を解体させる概念としてリゾームを提案しているようにおもえる。
著者たちはほんとうは、もっと広い類別の領野に出てゆきたいに違いない。『アンチ・オイディプス』を念頭にして読むとそう感じられる。ヘーゲルならば西欧は理性が原理だというべきところを、西欧は森の樹木とその伐採によって造られた特権的な樹木の系譜との関係だといわれている。また東洋の原理は自然だというべきところを、リゾームだと考えている。とくにオセアニア(ベイトソンのバリ島などを念頭においているのだろう)はそうだと言っている。そして現代のアメリカには特別のタイプを与えようとしている。「かつて起った重要なこと」、「いま起りつつある重要なこと」のすべてがアメリカというリゾームを媒介にして起っている、そしてアメリカの東部は樹木状であり、西部は樹木でさえもリゾーム状になっていて、西洋と東洋とを仲立ちする中間項をなして、かつて十九世紀にトルキスタン-ヒンドスタンが演じた役割を、現代の世界で演じていると著者たちは述べている。この本を読みながら愉しくさせられるのはこういう、あまり正確でない冗談をリゾームの概念に沿ってふり撒きながら唱いあげている個所だ。正確な概念ではなくても、感覚的なマトはきちっと当っているように仕上げられている。
本には理解もできず、何の役に立つかもわからないのに、そのことで役に立つ本がある。また逆にとてもよく理解でき、役立ちそうなことがあちこちにばら撒かれているのに、何の役にも立たない本がある。また本は中味で読みそうになったらすぐに引き返して、そんなやり方で読んだら駄目だと、たえずつき崩し、茶々をいれていることで役立つ本もある。「この本」は全体としてこのすべての本の性格を具えているようにおもえる。そして著者たち自身にも、読者にもこう言っている。「そう、あなたのお望みのやつをお取りなさい。われわれは流派を作ろうなどと思い上ってはいない、もろもろの流派、セクト、分派、協会、前衛、後衛なんかはいまだに樹木なのであり、その滑稽な昂揚においても墜落においても、通ってゆく重要なものすべてを押しつぶしてしまう」。これは著者たち自身にとくに宣告してもらいたい言葉だ。それがこの本の概念であるリゾームの良さなのだとおもうから。
【この書評が収録されている書籍】
そこでまず、ひとつの本が、紙をある判型に区切って束ねたものに、文字が印刷されていて、その文字を書き連ねたひとりの著者が、個性と個性の由来と、知識の蓄積とその由緒ある出自を傾けて表現したものから出来ている、という考え方をやめようという提案から、この本ははじまっている。著者はG・ドゥルーズとF・ガタリという二人の連名になっている。だが著者たちは言う。習慣上そうしているだけで、G・ドゥルーズが、すでに幾人かから出来上っており、F・ガタリもまた幾人かから出来上っているので、大勢がいろいろな位置と視角から手を出して「この本」に始末をつけ、また「この本」からさまざまな場所や人や現実の地層や地盤にたくさんの触手を延ばし連結するように、しつらえられた多面多様体だというように、「この本」を理解するよう求められている。もちろんG・ドゥルーズがどの個所を書き、F・ガタリがどの部分の執筆を担当しといったことは、まるでわからないようにしてあるし、ただ無署名の多様な手が集まっていることの象徴としてしか、「この本」の共著者の名前には意味がない。そういう理念が「この本」だし、一般に「本」というものはどれも、そんなふうに読まれるべきだし、そんなふうに存在すべきだという理念が、著者たちの宣明に当っている。
わたしたちがふつう本の中味とか、意味とか、本を流れている理念とか呼んでいるものは、著者たちにとっては存在しないものだ。本はそれ自体が小さな「組みこみ」機械で、本の外部にある性愛とか戦争とか革命とか官庁とか動物とか植物とかを、どんなふうに「組みこみ」あいを作り出し、どんな地盤や傾斜や領地を作りあうかということがあるだけなのだ。ふつうはそう考えられていない。著者たちが多発している比喩を使えば、本には中心となり根となる理解があり、そこから展開や意味作用や分岐があって樹木のように枝葉を繁らしていて、その全容はうつ然とした大木のように統一し、内閉した世界を作っているとかんがえられている。だがそういうのは嘘なのだ。強いて植物の比喩をもってくれば、いつでも根が茎でありながら、また根でもあり、中心もなければ枝葉もなく、どの部位も茎でありながら根でもあるさまざまな触手によって、本の外部にある事物と連結しようとしてうごめいているような「リゾーム(根茎)」が、本のほんとうの姿なのだ。そしてこれはたんに本の姿というだけではなく、人間の身体も、思考作用も、それから世界像も、リゾーム状の連結機械としてできている。これがD-G(ドゥルーズ+ガタリ)の基本的な考え方として提案されている。
では世界連結の「組みこみ」機械であるリゾームには、どんな原理があるのか。著者たちはいくつか、その原則を列挙し、説明を加えている。それはおよそつぎのようにたどることができる。
まずこのリゾームは、どんな一点からでも外部にあるどんな点とも接合されうる。そこでは特殊な民族語もなければ、逆に均質的な言語共同体もない、たまたま政治的なリゾームのうちひとつの支配的な言語が権力を奪ったところでは、民族語の流通圏が固定化されて存在しているだけだ。
またリゾームは多様な場所からたくさんの連結の触手を出して、外とつながっているときには、客体にも主体にも統一性などはなく、ただ多面的な多様体として、中心などはどこにもないような、またどこにも帰属することのないような開かれた実体を形成している。そしてこの実体は意味によってさまざまな構造を区分けしたりすることはないかわりに、意味のない個所で、勝手に切断したり折りまげたりすることができる。それはリゾームがたくさんの分節線を含んでいて、その分節線に則して地層や領域や意味や帰属を分類することができるとともに、どんな意味でもないし、属領化もできないような非属領化の線も含んでいて、この線に則してゆけば、いつでもどこか外部へ脱出できるようになっているからだ。
リゾームには、それに沿って生成し展開してゆくような、特異な生成の軸もなければ、さまざまな構成物にその基盤のところで繋がりをもたせているような深層構造もない。だから自己を再現するための契機となるような、均衡も無意識の記憶もない。ただいつでも連結ができ、組みこみができ、変貌することもできるようなたくさんの入口と出口とを持っているだけだ。これが塞がれてしまうと、リゾームはだんだんと流れがある個所で停滞し、ある個所ではまえよりもスムーズになるといった変化のあげくに、根がありそれと区別される幹と枝ができ、葉が繁り、うつ然としたひとつの世界を作る樹木の系統図に変貌してしまう。いいかえれば著者たちによるリゾームという中心概念の新規な設定が、従来の系統樹的な認識の秩序と階程にたいしてもっている意義もまた、中心集約的な認識の仕方、中心という考え、根幹と枝葉という考え方、うつ然たるひとつの世界の輪郭という考え、継時的にいえば記憶と無意識の暗がりの方から、出自と系譜が歴史的にもエディプス的にも由来するという考え方を、否定しようとするモチーフに発していることがわかる。だがなぜこういうモチーフを著者たちは必要としたのか、この考えは鳴り物を入れるほど効果的かとかんがえていくと、それほどはっきりしたことは構想されていない。これは著者たちの主著のひとつ『アンチ・オイディプス』を読んだときにも共通して感じるものだ。たぶんわたしたちには事情がよくわからない心的な外傷が著者たちにあって、リゾームという概念を作り出しているとおもう。この本でいえば、繰返し固執されている精神分析学にたいする過剰な否定にその外傷が象徴されている。つぎに引用するのがそれに該当する個所だ。またこの本の中心的なモチーフなので、丁寧に筆写しておく。
例えばまたもや精神分析を取り上げてみよう――その理論におけるのみならず、計算と治療との実践においてもまた、精神分析は無意識を樹木構造に、段階序列的グラフに、要約用説的記憶に、中心的諸器官、ファロス、樹木-ファロスに引渡す。精神分析はこの点に関して方法を変えることはできない――無意識というものについての専制的な考え方にもとついて、それはわが専制的権力を打ち立てているのだ、つまり精神分析医の被精神分析患者に対する、そしてもろもろの精神分析協会の精神分析医に対する権力を。精神分析の行動に残された余白はこうして非常に限られている。精神分析にもその対象にも、つねに一人の将軍、一人の首長がいる(フロイト将軍)。これとは反対に、無意識を非中心化システムとして、ということは完結した自動装置群(リゾーム)の機械状の網目として扱うことによって、精神分裂分析(スキゾアナリース)は無意識のまったく別な一状態に到達する。同じ指摘の数々が言語学についても妥当するのであり、ロザンティエールとプティトーは正当にも、「語の一群落(ソシエテ)の非中心化組織」の可能性を考察している。言表にとっても欲望にとっても同様、問題は決して無意識を縮小=還元することではなくて、一個の樹木にしたがってそれを解釈し意味せしめることでもない。問題、それは無意識を産出すること、そして無意識と共に、新たな言表、新たな欲望の数々を産出することなのだ――リゾームはこのような無意識の産出そのものなのである。
これは精神分析にたいする相当にひどい反感の表明にあたっている。そんなに反感をもついわれが、もてなかったとしたら? リゾームは何ら専制的な権力を行使していないかわりに、格別の有効性ももたないとしたら? たしかに無意識が振る舞う仕方にたいするフロイトの概念は専制的だし、乳幼児のとき、とくに授乳期にすでに無意識が意識的な人格とかかわりない振る舞い方を確定してしまうという見方は、宿命観的であって、けっして愉快なことではない。だが、だからといって無意識が手易く産出できるかのようなことを、言いふらすのはいかがなものか? 無意識と遺伝子的な素因のあいだには、まだよくわからない関係と断絶とが介入しているとおもわれる。でもフロイトの無意識には専制的なところもなければ、そんな意図もない。ただフロイトはたしかに精神とくに無意識の表情が、顔の表情とおなじように自然権的であり、これを左右するにはエディプスの直接性、その直接を無数の層状物のようにとりまき、条件づけている完全な偶然(つまり必然)というものを考慮すべきであり、それがほとんど自然生理的な宿命にちかいほど、人間という種は動物的で植物的であると考えられていたようにおもえる。この本の著者たちは、何かわたしたちにはうかがいしれない理由を混えて、フロイトの精神分析に不服であり、フロイトの無意識の根拠であるエディプス(母親の専制期)を解体させる概念としてリゾームを提案しているようにおもえる。
著者たちはほんとうは、もっと広い類別の領野に出てゆきたいに違いない。『アンチ・オイディプス』を念頭にして読むとそう感じられる。ヘーゲルならば西欧は理性が原理だというべきところを、西欧は森の樹木とその伐採によって造られた特権的な樹木の系譜との関係だといわれている。また東洋の原理は自然だというべきところを、リゾームだと考えている。とくにオセアニア(ベイトソンのバリ島などを念頭においているのだろう)はそうだと言っている。そして現代のアメリカには特別のタイプを与えようとしている。「かつて起った重要なこと」、「いま起りつつある重要なこと」のすべてがアメリカというリゾームを媒介にして起っている、そしてアメリカの東部は樹木状であり、西部は樹木でさえもリゾーム状になっていて、西洋と東洋とを仲立ちする中間項をなして、かつて十九世紀にトルキスタン-ヒンドスタンが演じた役割を、現代の世界で演じていると著者たちは述べている。この本を読みながら愉しくさせられるのはこういう、あまり正確でない冗談をリゾームの概念に沿ってふり撒きながら唱いあげている個所だ。正確な概念ではなくても、感覚的なマトはきちっと当っているように仕上げられている。
本には理解もできず、何の役に立つかもわからないのに、そのことで役に立つ本がある。また逆にとてもよく理解でき、役立ちそうなことがあちこちにばら撒かれているのに、何の役にも立たない本がある。また本は中味で読みそうになったらすぐに引き返して、そんなやり方で読んだら駄目だと、たえずつき崩し、茶々をいれていることで役立つ本もある。「この本」は全体としてこのすべての本の性格を具えているようにおもえる。そして著者たち自身にも、読者にもこう言っている。「そう、あなたのお望みのやつをお取りなさい。われわれは流派を作ろうなどと思い上ってはいない、もろもろの流派、セクト、分派、協会、前衛、後衛なんかはいまだに樹木なのであり、その滑稽な昂揚においても墜落においても、通ってゆく重要なものすべてを押しつぶしてしまう」。これは著者たち自身にとくに宣告してもらいたい言葉だ。それがこの本の概念であるリゾームの良さなのだとおもうから。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする