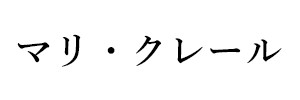書評
『襞:ライプニッツとバロック』(河出書房新社)
ベルクソンはかつて「哲学的直観」なる論文(一九一一年)において、哲学者の根源的直観に限りなく近接し、しかもそれを翻訳しているイマージユなるものについて語ったことがある。「媒介的イマージユ」と名づけられたそれは、まだ見ることができるという点ではほとんど物質的であるが、もはや触れることができないという点ではほとんど精神的なものであるという。そしてベルクソンは、たとえばバークレーが物質を人間と神の間に置かれた透明な薄い膜とみなしていたことを指摘したのである。
ジル・ドゥルーズの近著『襞──ライプニッツとバロック』は、「膜」ならぬ「襞」という「媒介的イマージユ」によって、ライプニッツ哲学とバロック芸術とを等しなみに論じようという、ベルクソニアン・ドゥルーズならではのまことに野心的な力作である。いや、「襞」はここではもはや「媒介的」というよりは、むしろあらゆるものをさしおいていたるところで自己を主張する、それ自体「自己目的的」とでもいうべき特権的形象になりおおせている。ドゥルーズは一九八六年に刊行された『フーコー』のなかで、すでに「襞」のイマージュを用いていた。そこで彼はフーコー自身の概念的構築をまるで無化するかのように、「〈襞〉はフーコーの著作につきまとい続けた」と書いていたのである。いささか唐突の感を与えなくもなかったフーコー論のなかの位相論的な「襞」は、しかしいまや限りなく増殖し、イマージュとしての世界を覆い尽くす。
本書は、ベルクソン、ヒューム、ニーチエ、カン卜、スピノザそしてフーコーに次いで、ライプニッツを対象とするドゥルーズの七番目の哲学者論とみることもできる。あるいは、マゾッホ、カフカ、プルース卜、キャロル、ベーコンなどを論じた広い意味での芸術論の系譜に属する著作とみることもできよう。いや、このような言い方には、さほど意味があるまい。「襞」は哲学と芸術の二領域を横断し、しかもそうした既成の区別そのものを無効にしうる形象だからこそ、まさに「特権的」なのであるから。
バロックの特徴とは限りなく生成する襞にある、とドゥルーズはいう。それは物質においても精神においても同様である。たとえば非有機的な物質は、つねに外側ないし周囲から規定される外生的襞とみなされるし、有機体はその固有の諸部分を折目づけ、また展げるその能力によって規定される内生的襞とみなされるのである。物質の科学は、それゆえドゥルーズによれば、日本の折紙をモデルとすることになるだろう。しかし精神における襞とはどういうことだろうか。微積分学というまさに「襞」の数学の基礎原理を確立したライプニッツにあって、しかもなおあの「モナド(単子)」は一個の形而上学的な点にほかならなかったのではあるまいか。モナドは、いわば「生ける鏡」としてひとつの視点から宇宙全体を「表現」する。しかもそれは窓も穴も扉ももたぬ閉じた単純実体にほかならない。だがドゥルーズは、このモナドもまた内に多数の襞を含みもつとみるのである。
ドゥルーズによれば、モナドの本質は、なによりもそれが「暗い底」をもつという点にある。外部に対して自己を閉ざしたモナドはその「暗い底」からすべてを引き出す。それは、バロックにおなじみの小室や聖室や地下納骨堂、あるいは教会や劇場や読書室や版画室と同列に語られるべきものなのだ。実際、ライプニッツのモナドおよびその「光─鏡─視点─内部装飾」のシステムは、バロック建築と関係づけなければ理解しえないというのが、ドゥルーズの主張の眼目なのである。たしかに内部の自律、外部なき内部として特徴づけられるモナドは、内部なき外部たるファサードと内部空間との断絶として特徴づけられるバロック建築に類比的である。ドゥルーズはさらに上下の序列を導入し、モナドという建物を二層に区別する。上の階は形而上学的(メタフィジック)な、精神に関わる部分、下の階は物質的(フィジック)な、身体に関わる部分である。しかも下の階には、上の階とちがって、窓がある。つまり、この上下の区別は、内部と外部の区別に対応するわけである。この下階=外部、つまりモナドの「暗い底」で繰りひろげられる物質的な襞を音に翻訳し響かせる二階こそ、精神と呼ばれるところの「音楽サロン」にほかならない。そしてそこは魂のもっとも親密(アンチーム)な「襞」の場所でもあるというわけである。こうしてドゥルーズは、不可分者であったはずのモナドをいささか強引とも思えるやり方で構造化し、結局、襞=音としての精神を語るにいたる。そしてこのことはまた、ライプニッツのいう「調和」とバロック音楽のハーモニーとの間の「正確な類比(アナロジー)」をも論じることを可能にしてくれるだろう。
このように本書の論述は、ライプニッツ哲学の諸概念をバロック的形象を援用することによって明らかにするというかたちでおおむね進められる。「十分理由」や「個別性」や「自由」や「微小表象」といった諸概念についても、ドゥルーズは同じように生き生きと語ってくれるはずだ。実際、外部と内部、ファサードと部屋、見えるものと読みうるものは、截然と分かたれた二つの世界ではない。見うるものはその読本(レクチュール)をもち、読みうるものはその劇場をもつからである。ベンヤミンの強調したバロック的アレゴリーは、まさに両者の結合の所産とみることができよう。いずれにせよ、われわれはドゥルーズとともにこういうことができるだろう。ライプニッツの哲学に対するは、バロックの芸術一般に対するに等しい、と。
バロックの代表的彫刻家ベルニーニの《聖テレサ》や《ルドヴィカ・アルベルトーニ》のあのおびただしい「襞」を知る者なら、従来のバロック論において何故その「襞」が強調されてこなかったのか、いささか首をひねらずにはいられまい。ドゥルーズによってこうして明言されてみると、われわれは「襞」を一も二もなくバロックの根本的形象として受け容れることができる。静物画などは、その対象として「襞」をしかもたないともいいうるのだ。しかし本書をとりわけおもしろくしているのは十七世紀の哲学や芸術を対象とする論述の内部に唐突に「外部」が侵入する、否むしろ折り返されてくるという点であろう。「襞」を根本的形象とすることによって、ドゥルーズは、たとえばカルテジアン・カンディンスキーに対するバロック・クレーを語り、タブローの表面が窓であることをやめたラウシェンバーグやポロックの名前をもち出し、そして地球を「襞」で覆おうとするあのクリストについて言及することができるのである。ドゥルーズによれば「襞」という形象によって、マラルメ、プルースト、ミショー 、ブーレーズ、アンタイの作品をも、「ネオ・バロック」の名のもとに包括しうることになろう。
本書はまぎれもなく問題の書である。それはバロック論の系譜のなかで特異な位置を占めるばかりではない。明言されてはいないものの、おそらく本書は、『言葉と物』(一九六六年)のなかで「人間」を経験的=先験的な二重性としての「襞」と呼びながらもデカルトとライプニッツを等しく「古典主義時代」に属する代表的哲学者として一様に論じたあのフーコーにこそ差し向けられた、秘かな挑戦の書でもあるにちがいないのだ。実際、「エピステーメー 」と「襞」──フーコーとドゥルーズの差異をこれほど端的に示す対比もありえまい。
【この書評が収録されている書籍】
ジル・ドゥルーズの近著『襞──ライプニッツとバロック』は、「膜」ならぬ「襞」という「媒介的イマージユ」によって、ライプニッツ哲学とバロック芸術とを等しなみに論じようという、ベルクソニアン・ドゥルーズならではのまことに野心的な力作である。いや、「襞」はここではもはや「媒介的」というよりは、むしろあらゆるものをさしおいていたるところで自己を主張する、それ自体「自己目的的」とでもいうべき特権的形象になりおおせている。ドゥルーズは一九八六年に刊行された『フーコー』のなかで、すでに「襞」のイマージュを用いていた。そこで彼はフーコー自身の概念的構築をまるで無化するかのように、「〈襞〉はフーコーの著作につきまとい続けた」と書いていたのである。いささか唐突の感を与えなくもなかったフーコー論のなかの位相論的な「襞」は、しかしいまや限りなく増殖し、イマージュとしての世界を覆い尽くす。
本書は、ベルクソン、ヒューム、ニーチエ、カン卜、スピノザそしてフーコーに次いで、ライプニッツを対象とするドゥルーズの七番目の哲学者論とみることもできる。あるいは、マゾッホ、カフカ、プルース卜、キャロル、ベーコンなどを論じた広い意味での芸術論の系譜に属する著作とみることもできよう。いや、このような言い方には、さほど意味があるまい。「襞」は哲学と芸術の二領域を横断し、しかもそうした既成の区別そのものを無効にしうる形象だからこそ、まさに「特権的」なのであるから。
バロックの特徴とは限りなく生成する襞にある、とドゥルーズはいう。それは物質においても精神においても同様である。たとえば非有機的な物質は、つねに外側ないし周囲から規定される外生的襞とみなされるし、有機体はその固有の諸部分を折目づけ、また展げるその能力によって規定される内生的襞とみなされるのである。物質の科学は、それゆえドゥルーズによれば、日本の折紙をモデルとすることになるだろう。しかし精神における襞とはどういうことだろうか。微積分学というまさに「襞」の数学の基礎原理を確立したライプニッツにあって、しかもなおあの「モナド(単子)」は一個の形而上学的な点にほかならなかったのではあるまいか。モナドは、いわば「生ける鏡」としてひとつの視点から宇宙全体を「表現」する。しかもそれは窓も穴も扉ももたぬ閉じた単純実体にほかならない。だがドゥルーズは、このモナドもまた内に多数の襞を含みもつとみるのである。
ドゥルーズによれば、モナドの本質は、なによりもそれが「暗い底」をもつという点にある。外部に対して自己を閉ざしたモナドはその「暗い底」からすべてを引き出す。それは、バロックにおなじみの小室や聖室や地下納骨堂、あるいは教会や劇場や読書室や版画室と同列に語られるべきものなのだ。実際、ライプニッツのモナドおよびその「光─鏡─視点─内部装飾」のシステムは、バロック建築と関係づけなければ理解しえないというのが、ドゥルーズの主張の眼目なのである。たしかに内部の自律、外部なき内部として特徴づけられるモナドは、内部なき外部たるファサードと内部空間との断絶として特徴づけられるバロック建築に類比的である。ドゥルーズはさらに上下の序列を導入し、モナドという建物を二層に区別する。上の階は形而上学的(メタフィジック)な、精神に関わる部分、下の階は物質的(フィジック)な、身体に関わる部分である。しかも下の階には、上の階とちがって、窓がある。つまり、この上下の区別は、内部と外部の区別に対応するわけである。この下階=外部、つまりモナドの「暗い底」で繰りひろげられる物質的な襞を音に翻訳し響かせる二階こそ、精神と呼ばれるところの「音楽サロン」にほかならない。そしてそこは魂のもっとも親密(アンチーム)な「襞」の場所でもあるというわけである。こうしてドゥルーズは、不可分者であったはずのモナドをいささか強引とも思えるやり方で構造化し、結局、襞=音としての精神を語るにいたる。そしてこのことはまた、ライプニッツのいう「調和」とバロック音楽のハーモニーとの間の「正確な類比(アナロジー)」をも論じることを可能にしてくれるだろう。
このように本書の論述は、ライプニッツ哲学の諸概念をバロック的形象を援用することによって明らかにするというかたちでおおむね進められる。「十分理由」や「個別性」や「自由」や「微小表象」といった諸概念についても、ドゥルーズは同じように生き生きと語ってくれるはずだ。実際、外部と内部、ファサードと部屋、見えるものと読みうるものは、截然と分かたれた二つの世界ではない。見うるものはその読本(レクチュール)をもち、読みうるものはその劇場をもつからである。ベンヤミンの強調したバロック的アレゴリーは、まさに両者の結合の所産とみることができよう。いずれにせよ、われわれはドゥルーズとともにこういうことができるだろう。ライプニッツの哲学に対するは、バロックの芸術一般に対するに等しい、と。
バロックの代表的彫刻家ベルニーニの《聖テレサ》や《ルドヴィカ・アルベルトーニ》のあのおびただしい「襞」を知る者なら、従来のバロック論において何故その「襞」が強調されてこなかったのか、いささか首をひねらずにはいられまい。ドゥルーズによってこうして明言されてみると、われわれは「襞」を一も二もなくバロックの根本的形象として受け容れることができる。静物画などは、その対象として「襞」をしかもたないともいいうるのだ。しかし本書をとりわけおもしろくしているのは十七世紀の哲学や芸術を対象とする論述の内部に唐突に「外部」が侵入する、否むしろ折り返されてくるという点であろう。「襞」を根本的形象とすることによって、ドゥルーズは、たとえばカルテジアン・カンディンスキーに対するバロック・クレーを語り、タブローの表面が窓であることをやめたラウシェンバーグやポロックの名前をもち出し、そして地球を「襞」で覆おうとするあのクリストについて言及することができるのである。ドゥルーズによれば「襞」という形象によって、マラルメ、プルースト、ミショー 、ブーレーズ、アンタイの作品をも、「ネオ・バロック」の名のもとに包括しうることになろう。
本書はまぎれもなく問題の書である。それはバロック論の系譜のなかで特異な位置を占めるばかりではない。明言されてはいないものの、おそらく本書は、『言葉と物』(一九六六年)のなかで「人間」を経験的=先験的な二重性としての「襞」と呼びながらもデカルトとライプニッツを等しく「古典主義時代」に属する代表的哲学者として一様に論じたあのフーコーにこそ差し向けられた、秘かな挑戦の書でもあるにちがいないのだ。実際、「エピステーメー 」と「襞」──フーコーとドゥルーズの差異をこれほど端的に示す対比もありえまい。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする