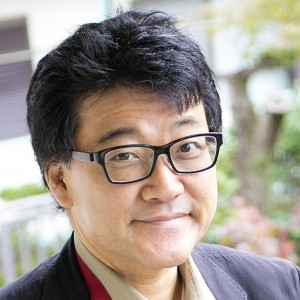書評
『キャッチ=22』(早川書房)
ジョーゼフ・ヘラー(Joseph Heller 1923-1999)
アメリカの作家。コピーライターなどをしながら、八年がかりで『キャッチ=22』(1961)を書きあげる。この作品はグレアム・グリーンらに絶賛され、無名の新人だったにもかかわらず大ベストセラーとなる。70年にはマイク・ニコルズ監督で映画化された。そのほかの著作に『なにかが起こった』(1974)、『輝けゴールド』(1979)、S・ヴォーゲルと共著の闘病記『笑いごとじゃない』(1986)などがある。introduction
『キャッチ=22』は、めったに他人の小説を褒めない星新一が絶賛していたので、記憶にひっかかっていた。だが、ベストセラーになった本ということで敬遠していて、実際に手にとったのはかなりあとである。「ああ、もっと早く読めばよかった!」と地団駄をふんだ。ぼくはのんびりした読者で、読むべき作品にはいずれ人生のどこかで巡りあうだろうくらいの気持ちでいる。しかし、この本ばかりは、読まずにいた時間を無駄したと思った。それくらいのおもしろさである。カート・ヴォネガットも自伝的小説『タイムクエイク』のなかで、この作品の題名をあげて、読者に「読みなさい!」と呼びかけている。世のため人のため、いまひとたび繰りかえそう。頼むからオレの忠告を聞いて『キャッチ=22』を買え!▼ ▼ ▼
戦地では、時間の経過を出撃の回数で計る。オレはもう四十四回飛んだから、あと少しで軍務とはオサラバだ――という具合。日常的な時間感覚はとうに麻痺している。なにしろ爆弾を投下しようと飛んでいくたび、見も知らぬ外国人が機関砲を撃ってくるのだ。日曜には、やくたいもない分列行進をさせられ、将校クラブでポーカーをすれば、気にさわる音でカードを弾くバカがいる。
泥沼のような毎日のなか、確実に増えていくのは出撃回数だけだ。もっとも、いくら回数を重ねたところで、泥沼が終る保証はない。将軍はことあるごとに出撃回数の規定を引きあげるのだ。五十回ではなく、六十回飛べと言われれば、さからいようがない。将兵はつねに指揮官の命ずることをなすべし。キャッチ=22には、そう定められている。
気まぐれで理不尽な軍規、キャッチ=22。その全貌を知るものはいないが、だれかが「それはキャッチ=22で決まっている」と言えば、従うしかない。
そんな不条理をなんとも思わず、反射行動のように出撃し、爆弾を投下し、ときには撃墜され、帰ってくればケンカをし、わけのわからない悪夢にうなされ、休暇には娼婦を買い、なかには娼婦に惚れる奴もいる。とにかく、この『キャッチ=22』という作品には、まともな人物はひとりとして登場しない。戦争を恐れ、死ぬことを真剣に忌避しているのは、主人公のヨッサリアン大尉だけだ。だが、彼だって正気とはいえない。
彼が所属しているのは、イタリアのピアノーサ島に基地を置くアメリカ空軍部隊。仮病を使って病院に逃げこんだヨッサリアンは、毎日、他人の手紙をせっせと改竄している。入院中の将校たちは手分けをして、下士官の出す手紙を検閲するのだ。ヨッサリアンは内容を読むのに飽きてしまい、修飾語を全部消したり、冠詞以外を塗り潰したり、ラテン語系の単語だけを残したり、というゲームを編みだす。キャッチ=22によれば、検閲官は扱った手紙に署名をしなければならない。そこで彼は、「ワシントン・アーヴィング」とサインをすることにした。アーヴィングの名が記された手紙は、たちまち軍隊上層部に波乱を巻きおこし、患者を装った特捜部員が病院に潜入することになる。
ヨッサリアンはといえば、終戦まで病院暮らしをするつもりだったのだが、あとから入院してきた、お人好しで人なつこいテキサス男にうんざりして退院してしまう。実際、このテキサス男のおかげで患者がぞくぞくと脱出をはたし、病室はガラガラ。残ったのは流感をうつされ肺炎で苦しむ特捜部員だけだった。
ヨッサリアンが自分のテントに帰ると、そこにはオア中尉と死人が待っていた。死人はまったくの厄介者で、ヨッサリアンは何度も大隊本部のタウザー曹長に苦情を申したてたのだが、曹長はそんな死人の存在を認めようとしなかい。物語がだいぶ進んでからわかるのだが、死人はオルヴィエート爆撃のときに死んだマッド少尉で、ピアノーサ島には着任したこともない。
死人よりもさらに奇態なのが、オア中尉だ。この男は、なにも訊かれていないのに、突然「おれは子どものころ、一日中両方のほっぺたに野生りんごを入れて歩きまわっていたものだ」などと言いだす。ヨッサリアンは相手をしないでおこうと思うのだが、どうにもがまんしきれず「なぜ?」と質問してしまう。オアは「橡の実よりましだったからさ」とクスクス笑うだけ。いくら問いつめても、満足な答は返ってこない。そういえば、売春宿でオアが娼婦に殴られた事件も不可解だった。ふたりとも裸のまま、娼婦が靴のかかとでオアの脳天を何度も叩いている。女は叫び、オアは笑う。けたたましい騒ぎに仲間が駆けつけるが、オアは事情を説明しない。真相は、いまも謎のままだ。
キャッチ=22以外にも、いくつもの不条理なシステムが、この基地をおおっている。その最たるものが、マイロー少尉を中心としたシンジケート〈MアンドM〉だ。食堂係として采配を振るうこの将校は、軍の爆撃機を使って大規模な貿易をおこなっている。軍隊に所属するだれもがこの事業の一株を持っており、その収益は全員の利益につながるというのが、マイローの主張だ。だが、シンジケートはドイツ軍から請けおい、味方の爆撃機を撃ちおとしさえする。
そのほか、この作品に登場する奇妙な人物は、数えきれない。裸の女の撮影に異様な執着を持つが、いつもしくじる〈ライフ〉誌の元カメラマン、ハングリー・ジョー。テントを捨てて森に住み、出会った人間に「冬がきたらおれは帰るとみんなに伝えてくれ」とささやく預言者フルーム。ぐるぐる巻きの包帯で入院し、テキサス男の饒舌に殺されてしまった正体不明の男(数か月後、同じ包帯男がふたたび入院し病室をパニックに陥れる。「あいつが帰ってきた!」)。このあたりになると、狂気や妄想というよりも、都市伝説めいてくる。
さて、ヨッサリアンはどうにか出撃を回避しようと苦心する。キャスカート大佐(この男は〈サタデー・イヴニング・ポスト〉誌の記事に自分が取りあげられること夢見て、スタンドプレイに走る)が無謀なボローニャ攻撃を命じたときは、地図上の前線をこっそりと移動させた。雨乞もしたし、仮病も使い、ついには出撃を拒否。そんな矢先、戦闘中、海に墜落して行方不明になっていたオアが、スウェーデンで生きているという報告が入る。そのとたんヨッサリアンは、オアが娼婦に殴られていた理由を悟った。そして、あわてて野生りんごと橡の実を手配し、軍隊からの脱走を企てる。
際限のない出撃と、むさ苦しいテント生活、そして狂気にむしばまれた戦友たちよ、さらば! だが、彼が逃げてゆく先に、キャッチ=22が待ち受けていないという保証は、どこにもない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする