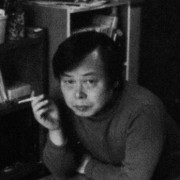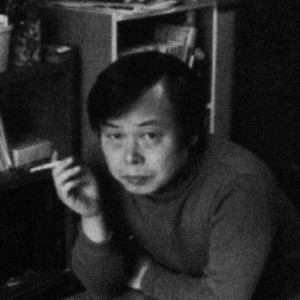書評
『坐忘録』(美術出版社)
まっ白の本
備忘録は忘れないためのメモだが、「坐忘録」は読んだらすぐ忘れてもいいのだという。はなから書評にならないようなイヤな予感がする。坐忘。荘子内篇のことばだそうだ。「坐忘とは、端座して形を忘れ我を忘れ天地万物一切を忘れること」。なにもかも忘れるのだから、なにもなくなる。では、なにもなくなるからなにもなくなったかというと、じつはそのなにもないが現れてくる。ということは、天地万物一切から我を引いた、金無垢の天地万物一切が現れてくるわけだ。禅問答みたいだが、著者は現代彫刻家。アルキペンコやアルプから「二河白道(にかびゃくどう)図」や丸石神まで、東西古今の美術についてのエッセイを集めた。四百ページの大冊のほぼ三分の一は、内外の現代彫刻家を論じた京都市立芸大教授時代の講義である。なにもないどころか、なんでもある。ということは、以上のボケ老人じみた禅問答ぶりはこの人一流の韜晦ということになりそうだが、そうともいい切れないのは、それが「忘」という空白、空間性を主張する現代彫刻の厳密に方法的なセオリーでもあることだ。
おふざけといえばおふざけ、クソまじめといえばクソまじめ、嘘ともほんとともつかない。その虚実だんだら模様、いたるところでくるりと裏返ってしまう、どこまでも続く両義性がこの本の中身だといえば、それではなにも書いてないも同然ではないかといわれそうだ。事実、よくもまあと呆れ返るほど駄洒落と語呂合わせを連発するので、いっそなにも書いてないも同然だといってしまいたくなり、するとまっ白な紙を読んだ書評になるから、書評にならなくて困ったことになる。それともこういう書物をこそ、マラルメ的白のエクリチュールというのだったろうか。
自伝的部分もなくはない。戦争中、周囲の戦争賛美美術にほとほと嫌気がさして彫刻をやめ、フランス語、ラテン語、ギリシャ語を学んで、ヴァレリーとエウリピデスばかり読んでいたという。おそろしく博学である。なんでも知っている。どうでもいいことまで知っている。しかしこの博学はみせびらかしではなく、ましてや学者・批評家のようになにかをいうためのものでもない。まるきり役に立たない博学であり、役に立てないための博学である。つまりはナンセンス。だからゲラゲラ笑いながら読んでいるうちに、これは読者を坐忘に彫刻する本だったかと気がついたが手後れで、まんまと「坐忘」にされてしまっている。やっぱり書評にならなかった。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1990年12月16日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする