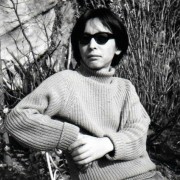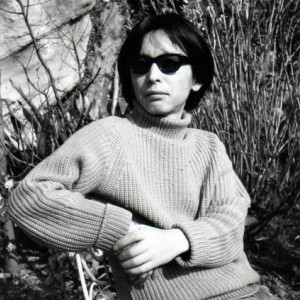書評
『ザ・ヌード―裸体芸術論・理想的形態の研究』(美術出版社)
かねて名著として聞こえていたケネス・クラーク卿の『ザ・ヌード』は、私も仏訳によって親しみ、時に評論などを書く際に参考としてページを繰ったものであるが、今度、立派な訳文による日本語版が出て、ふたたび通読し、初読の際に劣らぬ感銘を得た。訳者の労を多とすべきはもちろんであるが、それとともに、ヨーロッパの美術批評の古典的名著を豪華な造本で次々に刊行して、私たちを喜ばせている美術出版社の名編集者、雲野良平氏の弛まぬ努力についても、ここに忘れずに記しておきたい。
本書は九章に分かれ、それぞれの表題を示せば、「はだかと裸体像」、「アポロン」、「ヴィーナス」ⅠおよびⅡ、「力」、「悲劇性」、「陶酔」、「もうひとつの流れ」、「自己目的としての裸体像」となる。このうち、第一章の「はだかと裸体像」は総論であって、著者はまず、「はだか」the nakedと「裸体像」nudeの区別から始め、単なる肉体的自然としての「はだか」と、「再構成された肉体のイメージ」としての「裸体像」とが、明らかに異なるものであることを示す。著者によれば、裸体像とは「理念」であり、「芸術の主題ではなく芸術の一形式」であり、「模倣ではなく完成を望むもの」なのである。
肉体そのものを媒体とした芸術は舞踊(あるいは演劇)であり、舞踊においても、すでに舞台の上の肉体は「再構成されたイメージ」でしかないだろう。私は、フランシス・ベーコンやジョージ・シーガルの奇怪な肉体を考えてみたが、それらもまた、きわめて現代的な要求に基づいた一つの哲学の表明であることは、あまりにも明らかなのである。おそらく、最近のヌード写真のマニエリスティックな発達もまた、つとに自然主義的な模倣の段階を越えていると言えるだろう。
私が面白く思ったのは、古風な個人主義者を自認するクラークが、裸体芸術における必須の要素として、よしんば抽象的なものであるとしても、エロティックな感情を掻き立てるものを強く要求しているということであった。ただし、「芸術作品がエロティックな内容を溶解して収容し得る限界量は非常に大きい」のであり、クラナッハの媚薬的官能芸術に現われる妖女たちは、「水晶細工や七宝焼のように、誰からも欲望とは無関係に鑑賞され得る芸術品であることを決してやめない」(第八章)のである。クラナッハのエロティックな裸体の愛好者である私は、このクラークの見解に大いに満足であった。
第一章および第八章で、古典的裸体像とゴシック的裸体像との区別を、幾何学的・解剖学的に綿密に論証しているところも、私には非常に興味深かったし、教えられる点が多かった。ただ、裸体像とはギリシア人の発明になる芸術形式であると断定し、終始一貫、古典的な肉体表現を優位に置こうとする著者の立場は、ともすると、アポロン的主流に対するディオニュソス的傍系を不当に軽視するという結果になるのではないか、と思われた。たとえば、これもマニエリスムの頂点に位置する画家であろうが、独特の痙攣的な肉体表現を創始したエル・グレコの名が、ついに本文中に一ヵ所も出てこないことに、私はいささか奇異の念をおぼえたのである。第八章「もうひとつの流れ」にも登場せず、著者によって完全に無視された画家には、さらにもう一人、中世の裸の魔女や老婆を好んで描いた北方ルネサンスのハンス・バルドゥンクがある。「陶酔」という項目を設けてはいるけれども、巨大な地下の暗流ともいうべき古代のディオニュソス的・祭儀的伝統や、アレクサンドリア伝来の新プラトン派的神秘主義の流れが、どうやらクラーク卿にはお気に召さないらしいのである。しかし、すでに二ーチェも警告しているように、アポロンに対するディオニュソス、「白いギリシア」に対する「黒いギリシア」が存在するのは私たちの常識であり、この「黒いギリシア」の伝統にもっぱら依拠して、新しいエロティック美術の歴史(『エロスの涙』)を書いているジョルジュ・バタイユのような矯激な思想家もいることを忘れてはなるまい。バタイユのごときは、盛期ルネサンスをほとんど完全に無視して、中世(というよりも北方ルネサンス)から一足跳びにマニエリスムに目を移しているのである。美の規範やエロティシズムに対する考え方の相違であろうが、少なくとも裸体美術が問題である限り、あの甘美なフォンテーヌブロー派を大きく扱うのは当然ではあるまいか。
もっとも、私の言う「黒いギリシア」の伝統の二十世紀における復活は、古典的理想主義者たるクラーク卿の目には、「肉体を受け容れ、これを支配するに足る精神的エネルギーの欠如」(第二章)のように見えるらしいのである。彼は苦々しげに書いている、「十九世紀の初頭に唯物主義の煤煙のなかに消息不明となったアポロンは、今世紀に至って積極的な敵意の対象となった。メキシコから、コンゴから、そしてタルクィニアの墳墓からさえも、D・H・ロレンスがその予言者を買って出た闇の神々が、理性の光を消すためにこの世に招き出された。静けさと秩序との一身への具現は、社会共通の逆上や集団的無意識にとって代えられようとしている」と。
「闇の神々」とは、とりも直さず流血と死のエロティシズムを要求する神々である。これを要するに、クラーク卿はやはり理性の芸術、アポロン的芸術を重視する伝統的な立場を捨てがたいのであろう。
私は第一章と第八章ばかりあげつらったような気がするが、著者の美術史に対する基本的な考え方がいちばん直截に出ているのは、原理論としてのこの二章であって、その中間の六章においては、要するに古典的裸体像の時代によるプロポーションの変化に関する、細かい技術的な考察が進められているだけのように思われたからである。もちろん、その考察は精緻をきわめ、とくにミケランジェロ、ポライウオーロ、シニョレルリの男性像、ボッティチェルリ、ティツィアーノ、ルーベンス、アングル、ルノワールの女性像に関する考察は、単に技術的な面ばかりでなく、これを支配して精神の高みへ導く、メタフィジックな面への考察にまで筆が及んでいる。結局、裸体像とは自己自身の永遠化、神の観念と切り離し得ないものであるということを、著者は私たちに諄々と語りかけてくるのである。その限りにおいて、これらの分析が、きわめて説得力に富んだものであるということは否定しがたいだろう。
この滋味豊かな碩学の名著に、私たちが多くを学ばなければならないのは言うを俟たないが、そのなかでも、とりわけて重要だと思われるのは、この著者の永遠を希求する冷静な目が、今日の美術の概念の末世思想的な救いがたい混乱を、いかに眺めているかということであろう。「裸体は今もなお、物質が形式に変貌する最も完壁な範例であることに変わりはない」と信じている著者に、私は満腔の敬意を表したい。ハンス・ベルメールやポール・デルヴォーを熱愛している私もまた、少しく立場を異にしているとはいえ、この著者とまったく意見を同じくする者だからである。
【新版】
【この書評が収録されている書籍】
本書は九章に分かれ、それぞれの表題を示せば、「はだかと裸体像」、「アポロン」、「ヴィーナス」ⅠおよびⅡ、「力」、「悲劇性」、「陶酔」、「もうひとつの流れ」、「自己目的としての裸体像」となる。このうち、第一章の「はだかと裸体像」は総論であって、著者はまず、「はだか」the nakedと「裸体像」nudeの区別から始め、単なる肉体的自然としての「はだか」と、「再構成された肉体のイメージ」としての「裸体像」とが、明らかに異なるものであることを示す。著者によれば、裸体像とは「理念」であり、「芸術の主題ではなく芸術の一形式」であり、「模倣ではなく完成を望むもの」なのである。
肉体そのものを媒体とした芸術は舞踊(あるいは演劇)であり、舞踊においても、すでに舞台の上の肉体は「再構成されたイメージ」でしかないだろう。私は、フランシス・ベーコンやジョージ・シーガルの奇怪な肉体を考えてみたが、それらもまた、きわめて現代的な要求に基づいた一つの哲学の表明であることは、あまりにも明らかなのである。おそらく、最近のヌード写真のマニエリスティックな発達もまた、つとに自然主義的な模倣の段階を越えていると言えるだろう。
私が面白く思ったのは、古風な個人主義者を自認するクラークが、裸体芸術における必須の要素として、よしんば抽象的なものであるとしても、エロティックな感情を掻き立てるものを強く要求しているということであった。ただし、「芸術作品がエロティックな内容を溶解して収容し得る限界量は非常に大きい」のであり、クラナッハの媚薬的官能芸術に現われる妖女たちは、「水晶細工や七宝焼のように、誰からも欲望とは無関係に鑑賞され得る芸術品であることを決してやめない」(第八章)のである。クラナッハのエロティックな裸体の愛好者である私は、このクラークの見解に大いに満足であった。
第一章および第八章で、古典的裸体像とゴシック的裸体像との区別を、幾何学的・解剖学的に綿密に論証しているところも、私には非常に興味深かったし、教えられる点が多かった。ただ、裸体像とはギリシア人の発明になる芸術形式であると断定し、終始一貫、古典的な肉体表現を優位に置こうとする著者の立場は、ともすると、アポロン的主流に対するディオニュソス的傍系を不当に軽視するという結果になるのではないか、と思われた。たとえば、これもマニエリスムの頂点に位置する画家であろうが、独特の痙攣的な肉体表現を創始したエル・グレコの名が、ついに本文中に一ヵ所も出てこないことに、私はいささか奇異の念をおぼえたのである。第八章「もうひとつの流れ」にも登場せず、著者によって完全に無視された画家には、さらにもう一人、中世の裸の魔女や老婆を好んで描いた北方ルネサンスのハンス・バルドゥンクがある。「陶酔」という項目を設けてはいるけれども、巨大な地下の暗流ともいうべき古代のディオニュソス的・祭儀的伝統や、アレクサンドリア伝来の新プラトン派的神秘主義の流れが、どうやらクラーク卿にはお気に召さないらしいのである。しかし、すでに二ーチェも警告しているように、アポロンに対するディオニュソス、「白いギリシア」に対する「黒いギリシア」が存在するのは私たちの常識であり、この「黒いギリシア」の伝統にもっぱら依拠して、新しいエロティック美術の歴史(『エロスの涙』)を書いているジョルジュ・バタイユのような矯激な思想家もいることを忘れてはなるまい。バタイユのごときは、盛期ルネサンスをほとんど完全に無視して、中世(というよりも北方ルネサンス)から一足跳びにマニエリスムに目を移しているのである。美の規範やエロティシズムに対する考え方の相違であろうが、少なくとも裸体美術が問題である限り、あの甘美なフォンテーヌブロー派を大きく扱うのは当然ではあるまいか。
もっとも、私の言う「黒いギリシア」の伝統の二十世紀における復活は、古典的理想主義者たるクラーク卿の目には、「肉体を受け容れ、これを支配するに足る精神的エネルギーの欠如」(第二章)のように見えるらしいのである。彼は苦々しげに書いている、「十九世紀の初頭に唯物主義の煤煙のなかに消息不明となったアポロンは、今世紀に至って積極的な敵意の対象となった。メキシコから、コンゴから、そしてタルクィニアの墳墓からさえも、D・H・ロレンスがその予言者を買って出た闇の神々が、理性の光を消すためにこの世に招き出された。静けさと秩序との一身への具現は、社会共通の逆上や集団的無意識にとって代えられようとしている」と。
「闇の神々」とは、とりも直さず流血と死のエロティシズムを要求する神々である。これを要するに、クラーク卿はやはり理性の芸術、アポロン的芸術を重視する伝統的な立場を捨てがたいのであろう。
私は第一章と第八章ばかりあげつらったような気がするが、著者の美術史に対する基本的な考え方がいちばん直截に出ているのは、原理論としてのこの二章であって、その中間の六章においては、要するに古典的裸体像の時代によるプロポーションの変化に関する、細かい技術的な考察が進められているだけのように思われたからである。もちろん、その考察は精緻をきわめ、とくにミケランジェロ、ポライウオーロ、シニョレルリの男性像、ボッティチェルリ、ティツィアーノ、ルーベンス、アングル、ルノワールの女性像に関する考察は、単に技術的な面ばかりでなく、これを支配して精神の高みへ導く、メタフィジックな面への考察にまで筆が及んでいる。結局、裸体像とは自己自身の永遠化、神の観念と切り離し得ないものであるということを、著者は私たちに諄々と語りかけてくるのである。その限りにおいて、これらの分析が、きわめて説得力に富んだものであるということは否定しがたいだろう。
この滋味豊かな碩学の名著に、私たちが多くを学ばなければならないのは言うを俟たないが、そのなかでも、とりわけて重要だと思われるのは、この著者の永遠を希求する冷静な目が、今日の美術の概念の末世思想的な救いがたい混乱を、いかに眺めているかということであろう。「裸体は今もなお、物質が形式に変貌する最も完壁な範例であることに変わりはない」と信じている著者に、私は満腔の敬意を表したい。ハンス・ベルメールやポール・デルヴォーを熱愛している私もまた、少しく立場を異にしているとはいえ、この著者とまったく意見を同じくする者だからである。
【新版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする