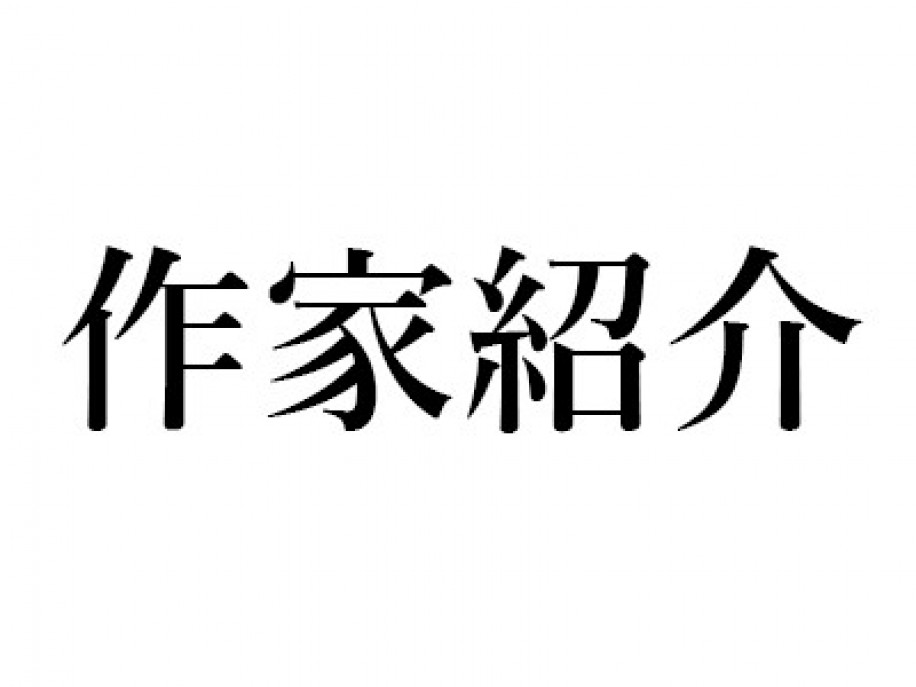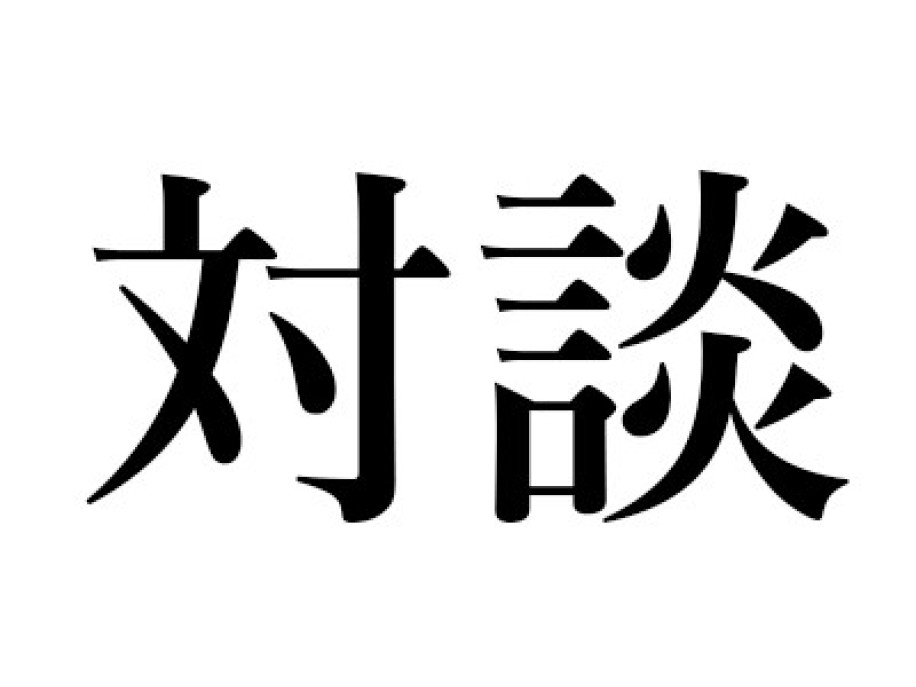書評
『語りかける花』(人文書院)
文学の未来はおばあさんたちのものか
まず『崩れ』(講談社)で、それから『木』(新潮社)、そして『台所のおと』(講談社)に『きもの』(新潮社)とこの順番で幸田文を読み、とうとう「幸田文症候群」(幸田文の作品をもっと読みたくなる病気。症状としては、本屋を探しまわって僅かに残っている単行本や文庫の『闘』や『流れる』を買って読むが、それでも飽きたらず幸田文全集はないかと神田まで出かけてしまうことが多い。ただし、幸田文が見つからない時には父親の幸田露伴で我慢する場合もある)にかかってしまったのはぼくだけじゃないだろう。何年も前に死んだおばあさんとしては異例のもてかただなあ、と思ってたら森茉莉の作品集も売れてるっていうじゃないか。ああ、それに惜しまれつつ亡くなった武田百合子も。きんさんぎんさんじゃないけど、おばあさんたちは元気だし、ボケにくいし、ぼくたちの知らないことをたくさん知っているから(それに比べるとおじいさんは、本の知識はあるけれど、それ以外の知識は乏しいんだな)面白いんじゃないだろうか。とはいっても、おばあさんたちにも欠点はあって、それは余命がやや短いことで、これさえなけりゃ最高なんだがねえ。
とにかく、亡くなったら新作は出ないし(幸田文は例外だけど)、こちらとしても「新しいおばあさん」を発掘しなきゃならない。もちろん、白洲正子はポピュラーだけど、芸術派おばあさんの代表だし、『手縫いの旅』(新潮社)の森南海子みたいな渋い生活派おばあさんもいる。でも、生活と芸術が一致しているのなら志村ふくみということになるだろうか。
志村ふくみは染織家で、重要無形文化財保持者で、しかも筆も立つ。
どんなことを書いているんだろうか。それは読めばわかるんだが、たとえばこの部分なんかは、志村さんのあるエッセンスを書いているように見えるんだな。
最後に西岡さんは薬師寺金堂の復興に際し、木を買わず、山を買うべく、台湾に出向き、原生林に入って、高所に点在する檜を双眼鏡でみると、青々した若葉をつけているものと、枯死寸前というようなのがある。西岡さんは後者を選んだという。現地の人は危ぶんだが、検査してみると前者は中が空洞で使いものにならず、後者は心材がきっちりつまっていたという。心材が腐って空洞化すると木質部を養う必要がなくなり、その分、枝葉に養分がゆきわたり、若々しい葉をつけるという(『語りかける花』、人文書院)
それから、こんなところも。
「さっとやっておけ」とは幸田露伴が娘の文さんにいわれた言葉だそうだが、花をいじくるのがきらいで、正月の花でさえ、水仙を二、三輪、さっとやっておけというのだそうだ。活けようとする花を四、五本、そっとひと握りして下向きにさげてみれば、花はめいめい好きなようにより添ったり、はなれたりして、いい形をつくり一瓶の中におさまる。花の好んでつくる形に従って自分の作意をもとうとするな、と伝授されたと文さんは書いている(同)
ここにも幸田文が出現してしまった。ぼくたちは幸田文を面白いと思うが、志村さんは幸田文を「あっ、わたしと同じだ」と思ってこう書いたのだ。じゃあ『語りかける花』の中には何が書いてあるのかというのは自分で読んで確かめてください。ああ、それから、同じおばあさんでも幸田文や森茉莉と白洲正子や志村ふくみの間にはある微妙な違いがあって、不思議なことに後者の方が「芸術的」なのだけれど、その理由についてはまたいつか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする