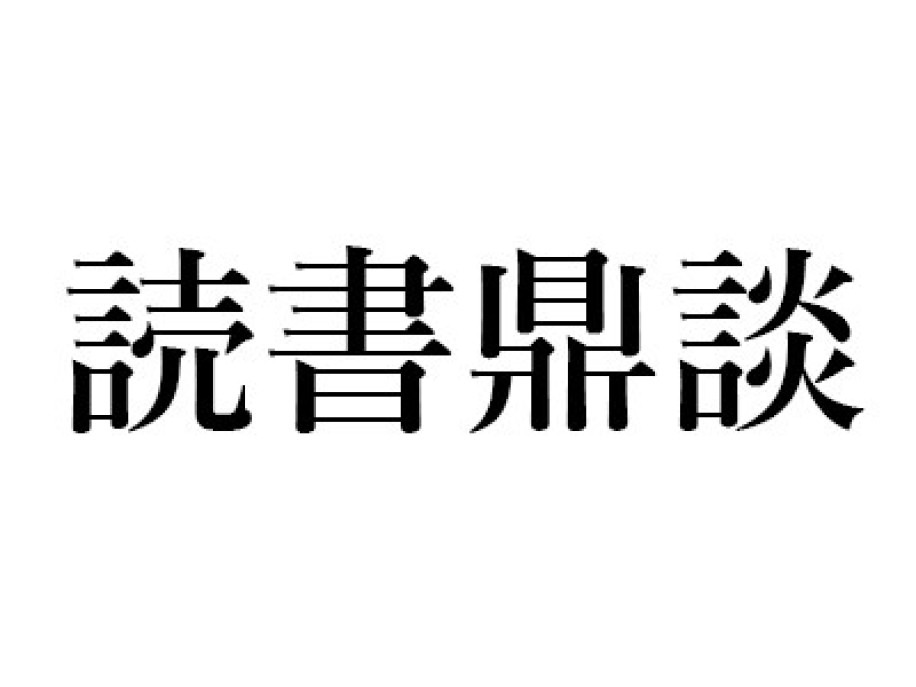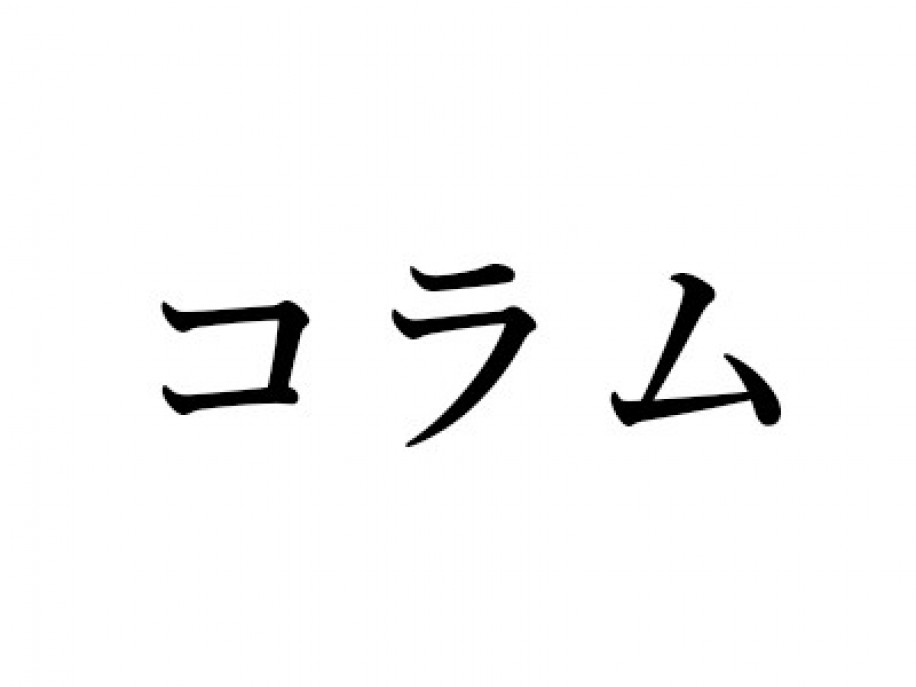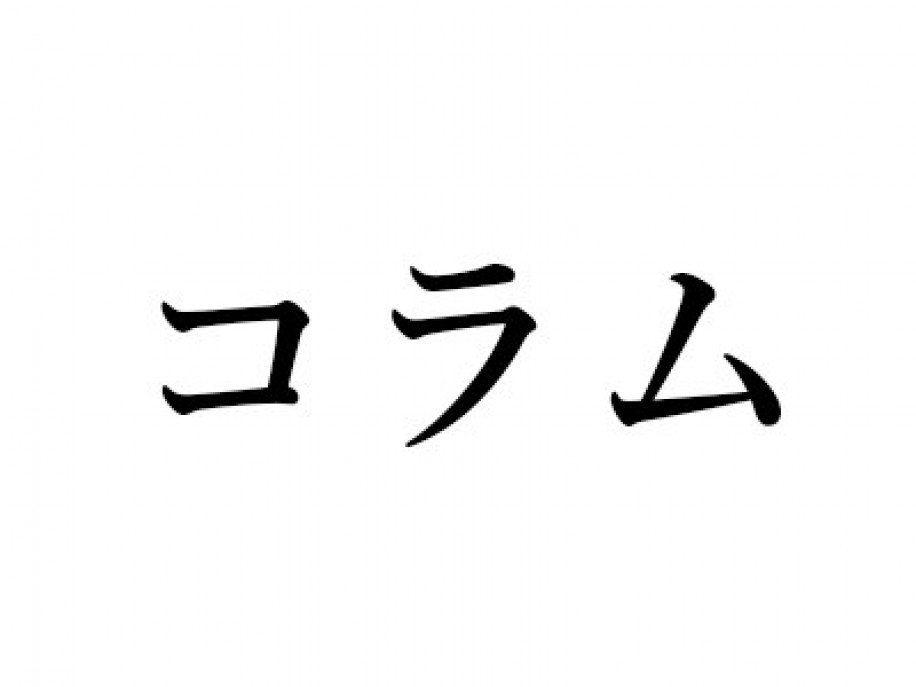書評
『とくとく歌仙』(文藝春秋)
今年の春、生まれて初めて歌仙というものを体験した。五七五の発句に始まり、その後七七、五七五、七七……と句を連ねてゆくのが連句。そのうち三十六句連ねるものを、三十六歌仙にちなんで「歌仙」と呼ぶ。
前の人の句を受け、どう展開させるか。自分の句を次の人が、どう受けてゆくのか。互いの付けかたの微妙な綾を味わいつつ、参加者全員で一つの作品に仕上げてゆく――と、こう書くといかにも楽しそうだが、実際はトンデモナイ。言葉選びに苦しむあまり頭のなかが醱酵して、息もたえだえ、という感じだった。
本書には、山中温泉かよう亭で、四回にわたって巻かれた歌仙(歌仙は「する」とか「作る」とか言わずに「巻く」と言います。なんとも雅びな語感……)と、それぞれの歌仙についての座談会が収められている。
私のような初心者は、歌仙の部分だけを読んだのでは、その味が今ひとつわからない。
なんといってもその後の座談会が、ぞくぞくするほどおもしろかった。
句と句の間では、一時間以上の長考も珍しくない。その途中で考えられたことや、改作の過程、さらにはボツになった句までが披露される。そして、前の句のここを受けて、こんなふうに世界を広げて、ずらして、加味してこうなった――というようなことが、まさに「とくとく」と語られる。
歌仙には、さまざまな決まりがあって、それをクリアするだけでも、結構たいへんだ。
第三句は「て」か「らん」で留めなくてはならない、「月」と「花」の句はここで必ず登場、始めの六句には名所・国・神祇・恋・無情・懐旧などを詠んではだめ、春と秋の句は最低三句続けること、夏と冬は一句で切る、前の句と発想が同じでは困るが対比がきつすぎてもよくない……。細かいことはまだまだあって、その規則のなかで、調和と飛躍とを実現しようというのだから、これはもう言葉のウルトラCの世界なのである。
だからこそ、ぴたっときまった時の快感も大きい。一座を唸らせるような見事な句ができた時の喜びというのは、妙なたとえだが、麻雀をしていて役満であがったような感じではないだろうか。歌仙は、文学であると同時に知的ゲームである。知的ゲームは、規則が複雑で細かいほうが、おもしろい。
その醍醐味を、あますところなく教えてくれる一冊だった。
【この書評が収録されている書籍】
前の人の句を受け、どう展開させるか。自分の句を次の人が、どう受けてゆくのか。互いの付けかたの微妙な綾を味わいつつ、参加者全員で一つの作品に仕上げてゆく――と、こう書くといかにも楽しそうだが、実際はトンデモナイ。言葉選びに苦しむあまり頭のなかが醱酵して、息もたえだえ、という感じだった。
本書には、山中温泉かよう亭で、四回にわたって巻かれた歌仙(歌仙は「する」とか「作る」とか言わずに「巻く」と言います。なんとも雅びな語感……)と、それぞれの歌仙についての座談会が収められている。
私のような初心者は、歌仙の部分だけを読んだのでは、その味が今ひとつわからない。
なんといってもその後の座談会が、ぞくぞくするほどおもしろかった。
句と句の間では、一時間以上の長考も珍しくない。その途中で考えられたことや、改作の過程、さらにはボツになった句までが披露される。そして、前の句のここを受けて、こんなふうに世界を広げて、ずらして、加味してこうなった――というようなことが、まさに「とくとく」と語られる。
歌仙には、さまざまな決まりがあって、それをクリアするだけでも、結構たいへんだ。
第三句は「て」か「らん」で留めなくてはならない、「月」と「花」の句はここで必ず登場、始めの六句には名所・国・神祇・恋・無情・懐旧などを詠んではだめ、春と秋の句は最低三句続けること、夏と冬は一句で切る、前の句と発想が同じでは困るが対比がきつすぎてもよくない……。細かいことはまだまだあって、その規則のなかで、調和と飛躍とを実現しようというのだから、これはもう言葉のウルトラCの世界なのである。
だからこそ、ぴたっときまった時の快感も大きい。一座を唸らせるような見事な句ができた時の喜びというのは、妙なたとえだが、麻雀をしていて役満であがったような感じではないだろうか。歌仙は、文学であると同時に知的ゲームである。知的ゲームは、規則が複雑で細かいほうが、おもしろい。
その醍醐味を、あますところなく教えてくれる一冊だった。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする