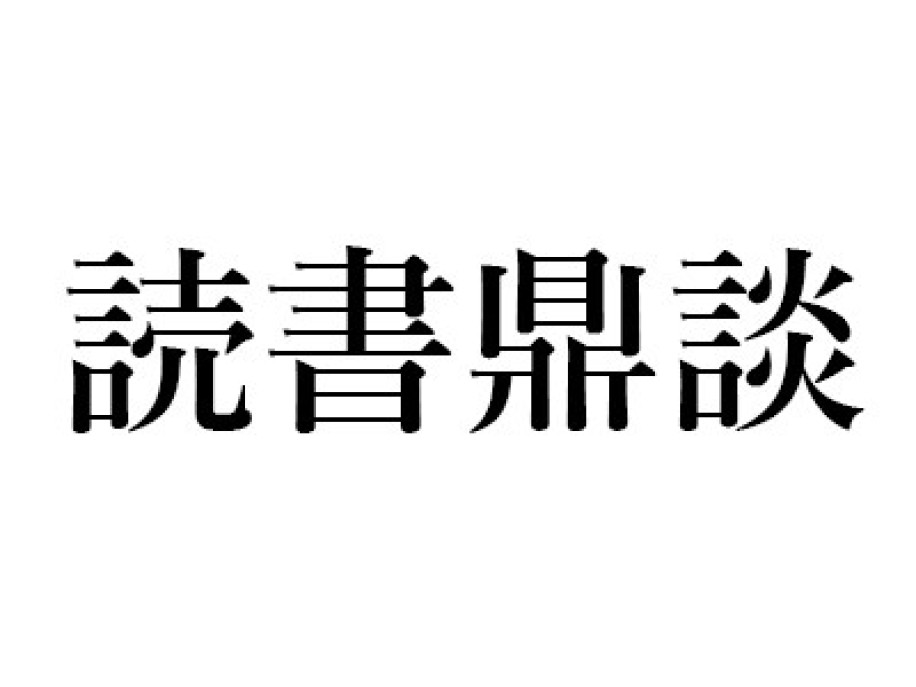書評
『文学としての俳句』(小沢書店)
優れた『目利き』を得た幸せ
文学としての俳句とは、どういうものか。それが具体的な作品によって示される。文学として俳句を読むとは、どういうことか。それが具体的な鑑賞によって示される。タイトルについて著者は「今、文学的ではない俳句が多いところからえらんだまでである」と、さらりと記しているが、現在隆盛を極めているように見える俳壇に対しての、辛口の見解も随所にあって、興味深い。本書には二十三人の俳人が、取り上げられている。正直言って、そのうち九人は、初めて出会う作家だった。出会えてよかった、と思う。
いつの日のひとりしづかの栞ぐさ 木村蕪城
思ふこと風が奪へり蓬萌ゆ 村田脩
朝市や雪に解く荷の蟹生きて 畠山譲二
たとえば、「栞ぐさ」の句には、次のような文章が寄り添う。「人にはよくそうした記憶がある。旅に出た日々の、孤独で自由なひと時、何かの感興にかられて本をよみ、栞をはさむ。その時のことが記憶から遠ざかったある日、右のような仕草(注・何気なく書棚から本をとり出す)から、過ぎた日の心の状態が幻のように蘇ってくるのである。あの日、日常から離れた『私』は何を考えていたのだろう。その思い出が一瞬、今の時をみたし、『私』は現在の外に出る。」
鑑賞に際して引用される作家は、夏目漱石、三好達治、ランボオ、リルケ、ボードレール、プルースト……と、著者の守備範囲の広さを反映して、実に自在だ。しかも、作者の経歴や俳句の作られた背景についての情報は、必要最小限に抑えられている。作者の実人生よりも、俳句から教えられる人生の深さに、スポットが当てられているのだ。「文学としての」心意気が感じられるところだろう。
鑑賞は鑑賞にとどまらず、著者の俳句観があちこちに盛り込まれていて、読む人だけでなく、詠む人にとっても、おおいに参考になる。
中心にあるのは、俳句とは「作るものではなく、生まれるもの」という考えだ。人生を深く生きた人にのみ、深い句は生まれる。「『ひらめき』や一瞬が人生の見える句を生むのは、詠む人間の人生に対する叡智が潜在的に深められているから」という言葉は強烈だ。
俳句界は、このような優れた「目利き」を得て幸せだと思う。いつの日か『文学としての短歌』を、読みたい。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1993年3月14日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする