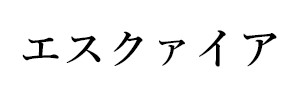書評
『愛の手紙』(図書新聞)
後ろめたい行為
他人の恋愛にかかわる手紙を読むのは、日記を覗くのと同様、後ろめたい行為だ。特定の相手に向けて発せられた言葉を第三者が盗み読む。これはほとんど犯罪にも等しい仕儀である。そしてここにまたひとつ、魅惑的な罪が犯された。ダニエル・ヴォルの編による『愛の手紙』。採取された愛の発信地は、フランスを中心として、ドイツ、イギリス、イタリア、スペイン、スウェーデン、ロシア、アメリカにおよび、消印の跡も十六世紀の昔から二十世紀の今日まで、約五百年という広範囲にわたっている。
愛の当事者たちが、分野のちがいと程度の差こそあれ、みな歴史に名をとどめる人物ばかりであることも、公的暴露本としての本書の罪を確実なものにしている。国王から公爵への危うい付け文もあれば、やんごとない老女から海を隔てた年下の男性への熱烈なラヴコールもあり、詩人から姉への近親相姦的な手紙もある。
だがひとつ奇妙なのは、時代も立場も性も異なる差出人、それもこれだけ個性的な面子を揃えた愛の発信者の声が、「薄暗い君の沢に僕の棒で罰を加え」たいなどというポルノまがいのあけすけな告白を含めて、思いのほか均一で平板に響くことだ。
なるほど愛とは、誰にでも応用可能な、互換性のある口調によってしか伝達されないのかもしれず、逆に言えば、紋切り型を否応なく呼び込んでしまうのが恋文という磁場の面白さであり、また恐ろしさなのだろう。本書の不思議な味わいも、たぶんそこに由来している。
しかし百二十通を超える同工異曲の手紙をこれだけつづけて読まされると、いささかげんなりするのも事実なのだ。そのあげく、原注にまとめられた当事者たちの簡便なプロフィールの方が、手紙そのものより、ずっと雄弁に見えてくる。
これは他人の秘密を覗こうとした罰なのだろうか。それとも単に、愛は結局ひとの気を滅入らせるという教訓なのだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする