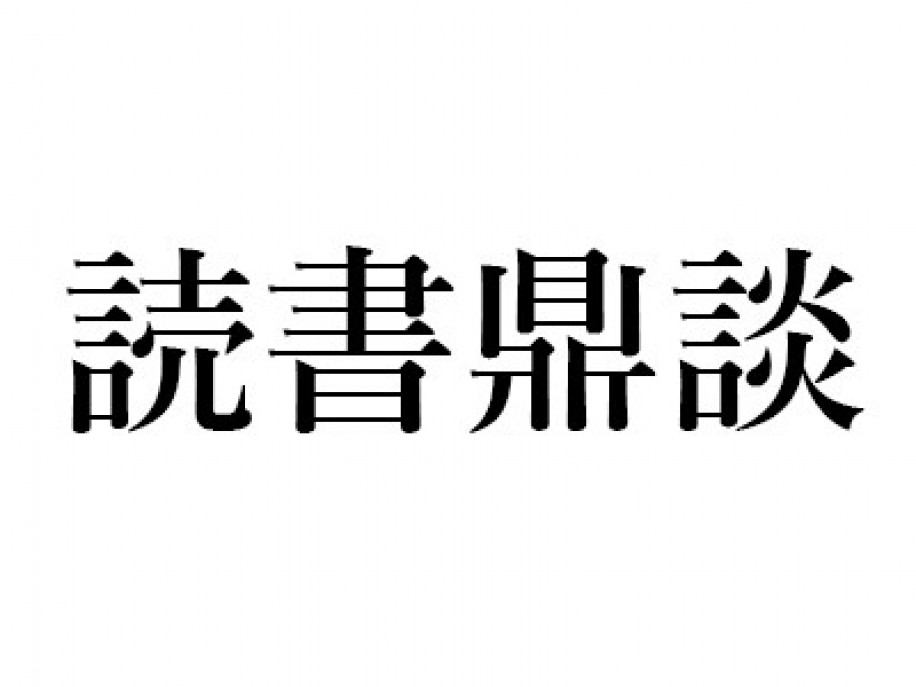書評
『負ける建築』(岩波書店)
建築の「強さ」、とことん検証の評論集
タイトルを見て、安藤忠雄の『連戦連敗』という講義録の二番煎(せん)じかとおもった。いちばん強そうにみえる人が「敗退」の意味をかみしめる、そんな本かなともおもった。ところが読みはじめるとじつは逆さで、「強さ」という、建築に対してだれもが抱いているイメージを建築の現場からとことん検証する、なかなかに強面(こわもて)の評論集なのである。
いちばんあたりまえのこと、もっとも基本的なことから、論を起こすところがいい。建築が並はずれて大きいこと、大量の物質を浪費すること、そして建ったものは取り返しがつかないこと。
阪神・淡路大震災、オウムのテロ、そして九・一一。三つの事件にこの建築家は震撼(しんかん)させられた。地震は「持ち家政策」という、建設事業の根本を揺るがした。サティアンはこれまでのいかなる壮麗な宗教建築とも似ていなかった。九・一一は、高く積み上げたものが脆(もろ)いという、あたりまえの事実を突きつけた。高く積み上げる途とは別の途はないのか。「象徴にも、視覚にも依存せず、私有という欲望にも依存しない」建築とは何か。この問いが、ここ十年、建築家の頭のなかで疼(うず)いていた。
オフィスビルが都市建築の主流となった経緯、透明な建築の流行、市民参加のプロセス導入という理念のいかがわしさ、デジタルな設計プロセスの功罪、セキュリティーという名の空間閉鎖、そしてなによりも「景気のドン底に、もっともお呼びでない超大型建築ができる」というちぐはぐさ、つまりは建築の「遅延」の原因。そんなテーマが、ちょっと立ち止まらせてくれよと言いたくなるくらいに颯爽(さっそう)と論じられる。
批評の人なんだとおもう。戦後建築史における丹下健三(モダニズムの巨匠)と村野籐吾(マルクス読みの数寄屋好み)・内田祥哉(建築の民主主義)という二極性の吟味、銀座四丁目角という都心中の都心にせせこましく立つガラス・ビルの「悲しさ」への問い、ブランドという視点からする安藤忠雄の仕事の解読などに、とくに味がある。
朝日新聞 2004年05月30日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする