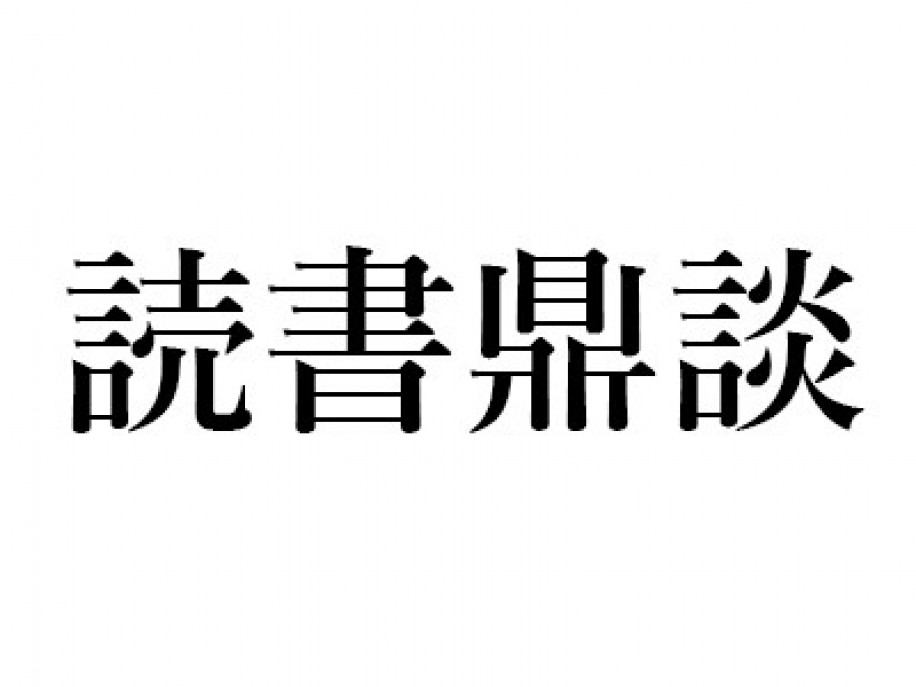書評
『立原道造 風景の建築』(大阪大学出版会)
幻想と現実に揺れる穏やかな風
語と語のあいだに穏やかな風が通るような作品を残した夭折(ようせつ)の詩人立原道造は、気鋭の建築家でもあった。文学と建築がひとりの青年のなかでいかに分かちがたく結びつき、相互に浸透し合っていたのか、本書はそれを、文学作品に偏ることなく、残された図面を通して丁寧に読み解いていく。立原道造は一九一四年(大正三年)、東京の日本橋橘町(現・中央区東日本橋)に生まれた。この年に竣工した東京駅周辺には鉄筋コンクリートのビルが林立し、関東大震災による壊滅と復興がそこに加わる。建築物を観る眼はそうした日本橋界隈の環境と、幼少時から描き続けてきた絵画によって養われた。
中学から一高にかけて、北原白秋の影響下で歌を詠み、明治大正の作家たちを愛読し、海外文学を渉猟して詩作を試みていた立原は、一九三四年、東京帝大の建築学科に入学すると、自ら同人誌を刊行し、第二次「四季」に参加するなど、活発な文学活動を開始した。十四行からなるソネット形式という、構成のしっかりした、かつソナタのように音楽的な詩形に親しむのもこの頃のことだ。
建築の方法を学び、思考を深めるにあたって大きな力になったのは、学科の課題制作だった。模写の正確さ、情景の想像力、図書館や美術館などの公共建築を「純粋造形美術」に等しいとする美学的視点、国内外の建築家の仕事を広く吸収して自分の言葉に転換する能力の高さ。立原道造はすでに周囲から一目置かれる存在だった。
指導教官の岸田日出刀、日本の建築家で最も敬愛していたという村野藤吾、大学一年時に連続講演を聴いたブルーノ・タウト、軽井沢に夏の家を建てたアントニン・レーモンド、ドイツの芸術家村ヴォルプスヴェーデに住んだフリッツ・オーヴァーベック、銅版画に親しんでいたハインリヒ・フォーゲラーらの仕事を通じて、立原は、建築とは合理的な思考だけで成り立つのではなく、人間との関係性を考慮し、歴史と時間を含んだ世界の現れだと考えるようになる。
その思考の集大成が「ひとつの建築的幻想」としての卒業制作、「浅間山麓に位する芸術家コロニイの建築群」だが、さらに深く詩人の内面を照らし出したのは、埼玉県浦和市(現・さいたま市)の別所沼に計画していた、単身者が週末を過ごすための狭小住宅「ヒアシンスハウス」の設計だった。立原はすでに私家版の詩集を風信子(ヒアシンス)叢書(そうしょ)として刊行しており、建築と文学はここでも半身を分け合っている。
この小家の構想が周囲に語られるのは、建築事務所に就職した一九三七年暮れ頃で、当時体調がすぐれなかった立原は、自身の「晩年」を見据えていた。ギリシア神話のヒアキントスに由来するこの花には、死が張り付いている。それはまた、婚約者との未来に、両開きの鎧戸に抜かれた十字の光を当てる再生への祈りでもあった。
卒業制作もヒアシンスハウスもアンビルト、つまり図面上にしか存在しない幻想であり、純粋形態の建築である。現実といったん別れることが、より大きな愛に必要だとするリルケの教えに、若き建築家は忠実だったのかもしれない。そんな別れの身振りこそ詩と建築の本質に近づく道であるという逆説が、抑制の利いた記述から静かに浮かび上がってくる。
ALL REVIEWSをフォローする