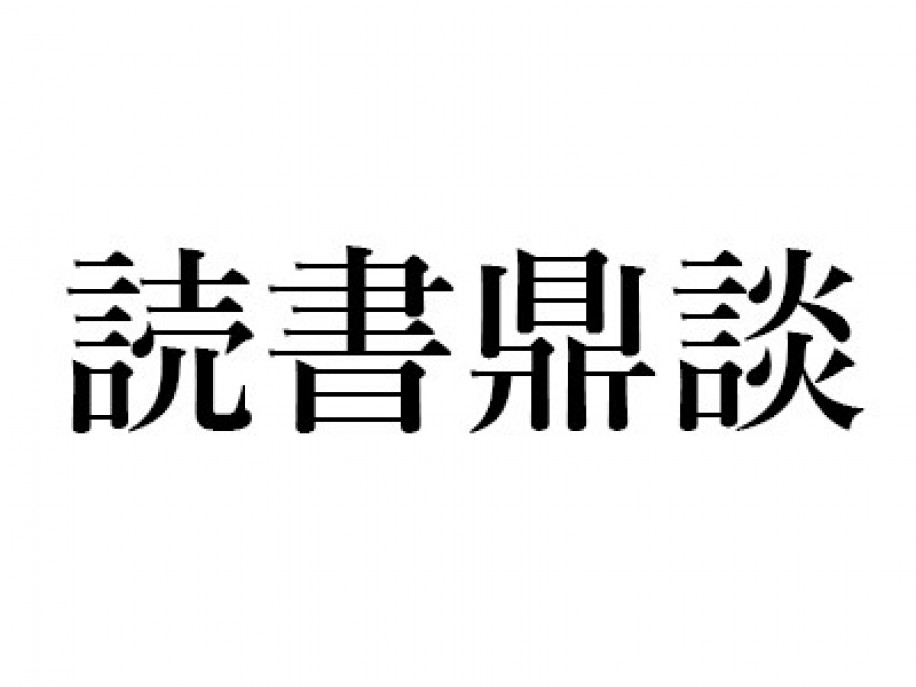書評
『テクストのぶどう畑で』(法政大学出版局)
「読書好き」に贈る「読書」の本
今回のタカハシはマジメである(いつもマジメだけど)。実は、この「退屈な読書」に連載したもの(事務局注:「週刊朝日」連載時のタイトル)を読み返し、いささか反省しちまったのである。自分の書いたものではあるが、どうも「読書って面白いなあ、ほんと楽しいなあ」とばかり言っているような気がするのである(まるで水野晴郎だ)。
世の中いろいろ。「苦しい読書」も「耐える読書」も「義務としての読書」も「営利目的の読書」もあるのである。そこで、本日は初心に戻り、タカハシの好きなイヴァン・イリイチ(レーニンじゃないよ)の傑作読書論『テクストのぶどう畑で』(岡部佳世訳、法政大学出版局)を読んでみることにしたいと思う。
この本の中でイリイチは「読書」という行為が、ある時代に生まれた特殊な行為だということを綿々と述べている。要するに、ある時代までは「読書」というものは存在しなかったのである。読むものがなかったから――というのなら話はわかるけど、いちおう読むものはあった。にもかかわらず、「読書」はなかった。「読書」はある瞬間に「発見」されたのだ。
イリイチは中世の神学者ユーグの『学習論』を引用しながら、まずかつて読書はなにより「身体運動」と「朗読」であったことを説明する。つまり、最初の読書人たちとは修道士だったのである。本とは羊皮紙に書かれた聖書であり、読書とはそれを朗読することだった。
ところが、ユーグが語りかける修道士にとっては、読書は走馬灯のようなものではなく、肉体的な活動の一つなのである。修道士は、一行一行を心拍に合わせて動きながら理解し、そのリズムにのって記憶する。そしてそれを口に含み、かみしめながら思索する。修道院付属学校が、ぶつぶつとつぶやく人ともぐもぐと口を動かす人の住処と表現されていたのも、もっともなことなのである
とまあ、このへんは「へえ」と思うだけかもしれないが、この次のあたりにくるとびっくりする事実が出てくる。
ユーグのもう一つの貢献は、特に黙読という読書形式が存在することを初めて公に文章に記したことにある。……。無論、古代においても時折黙読は試みられていた。しかしそれは、一種の離れ技と考えられていた。……。アウグスティヌスは、師であるアンブロシウスが時折唇を動かすことなく書物を読むことを不思議がっている
ふだんなにげなくやっている「黙読」は革命的な技術だったのである。先人たちが切り開いてきた読書という世界の貴重な手法だったのである。ありがたや。タカハシはイリイチの本を読み、現在の読書の基礎を築いてくれた人たちに深い感謝をささげたいと思った。そしてナボコフの『ロシア美人』を本棚から出そうとして、思わず『嶋田加織写真集』(『青沼ちあさ写真集』の場合もあり)を出してしまう自分を恥ずかしいと思った。でも、イリイチは、
ユーグの説く瞑想は、肉体と精神の高度な集中を要する読書活動であって、単なる無為の人の受け身の感情移入とは違う。この活動は、肉体の動きにたとえて表現される。たとえば行から行へ大股に歩くとか、すでに精通しているページを調べる時は翼をバタバタさせるなどと表現されている。ユーグは読書を、身体運動として体験するのだった
と書いていて、ヌード写真集を見ながら男の子は身体運動に熱中することもあるのだから、それは、始原の読書に近いわけで、恥ずかしく思う必要なんかないかもしれないのだった。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする