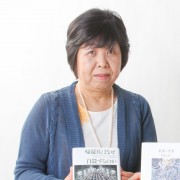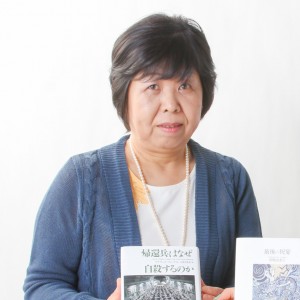書評
『サイダーハウス・ルール』(文藝春秋)
読書の秋である。どうせなら良質の本を読みたい。
大学時代、ある先生がこう言われたのをいまでも覚えている。 「きみたちは若いから、まだまだ時間があると思っているでしょう。しかし、よく考えてごらんなさい。今、二十歳で、あと五十年生きられるとして計算するとね、きみたちに残された日々は一万八千二百五十日ですよ。まあ、簡単に二万日と考えてもいい。するとね、あとどれくらい本が読めると思います? 一日一冊で二万冊。そんなに読めるはずはないから一週間に一冊読むと仮定して計算すると、およそ二千八百冊です。いいですか。二千八百冊しか読めないんですよ。だからぼくはきみたちに言いたい。良書を読みなさい。時間を大事にしなさい」
このときわたしは本当に驚き焦った。この先一日一冊読んでも死ぬまでに二万冊くらいしか読めないとは。これはあくまでも後五十年生きると仮定してのことで、もっと短いかもしれない。そこでわたしはそれから一年間、本当に一日最低でも一冊は読んだ。当時の手帳が残っているので、それをいま見ると、良書ばかりを読んでいたわけではない。時間を無駄にしたと思われるような本もたくさん読んでいる。
しかしそれでよかったのではないか、といまにして思う。というのも、いまなら本当に雑多な本など読みたいとは思わないからだ。若いときにしか、まだ価値観や人生観が固まっていない時期にしか、雑多な本は読めないのである。
さて、今月は長編を紹介しよう。別に秋の夜長にむけて、というわけではないけれど、やはり小説の醍醐味を味わうためには長編小説を読まないといけない。ジョン・アーヴィングの『サイダーハウス・ルール』はアーヴィングの六作目の本である。名前を聞いたことのある人も多いのではないだろうか。日本に初めて紹介されたのはかれこれ十五年ほど前になるが、『ガープの世界』という、特異な作家ガープをめぐる物語だった。アーヴィングの小説はどれもそうだが、とにかく物語の展開がすさまじい。しかもとても視覚的で、映像的である。『ガープの世界』も、それに続く『ホテル・ニューハンプシャー』も映画化されたので、あるいは観た人もいるのではないだろうか。
アーヴィングの描く世界には、アメリカという国が抱えているあらゆる問題(人種問題、性的問題、政治、文化、スポーツ、中絶問題、戦争)、人間のあらゆる局面(幸福、不幸、悲嘆、怒り、嫉妬、歓喜、生、性、死、冒険などなど)が詰め込まれている。どの作品をとっても、とにかく盛りだくさんの小説である。
アーヴィング自身が、ディケンズに影響されている、十九世紀的な世界にどんどん近づいている、と述べているくらいだから、彼には小説というものがどういう形であるべきか、あるいはどういう世界であるべきかというヴィジョンがしっかり確立している。しかし、だからといって古めかしい作品なのではない。 『サイダーハウス・ルール』は、孤児の物語である。アーヴィングという作家は、どういうわけか、普通ではない人を大変な情熱を持って描く。普通ではない、というとおかしな言い方になるけれど、たとえば『ガープの世界』では、性転換をしたフットボール選手が重要な役割を担っているし、レイプされて舌を切られた女性や、事故で片目をなくした子供が登場し、『ホテル・ニューハンプシャー』では、耳の悪い子、背が伸びない病気の子、熊のぬいぐるみを着て暮らす娘などが登場する。本書でとりわけ変わっているのは、エーテル中毒の堕胎医ウィルバー・ラーチ先生だ。
この小説は、アメリカの三〇年代から始まる。ラーチ先生は、臨月になった女性の出産を手伝い、その結果生まれた子を、自分の経営する孤児院に入れるかたわら、図らずも妊娠してしまった女性の堕胎も執り行なっている。前者を「神の業」と呼び、後者を「悪魔の業」と呼びながら。ラーチ先生は、孤児院の子供たちがそれぞれにしかるべき養父母に引き取られるように手を尽くす。彼は克明に日記をつけていて、孤児たちが人生を生き抜くためのルールをそこに書きつけていく。
だが何度養子縁組をさせても孤児院に戻ってきてしまう少年がいて、それが先生の悩みの種になる。それがこの小説の主人公たるホーマー・ウェルズだ。結局唯一の例外として、ラーチ先生はホーマーを孤児院に置くことを決意する。
それからのホーマーの人生が一大叙事詩のように語られていく。ホーマーの生き方の目標は「人の役に立つこと」だった。彼は孤児院をなんとか存続させるために、努力を惜しまずに働く。しかし、やがてはそこを飛び出して、自分の世界を探そうとする。リンゴ園に落ちつき、そこで働くようになったホーマーは、そこで愛することを覚えるが、結局は人妻になる女性との間に子供を持ち、その子を孤児として届け出て、養子として育てることにする。
アーヴィングの小説に出てくる人々は、絶えず自分とは何者なのか、何のために生まれてきたのか、ということを考え続ける。
その結果『ガープの世界』では、ガープの母親はレイプされた女たちのために避難所を設立し、『ホテル・ニューハンプシャー』では夢のようなホテルを作る父親が現われる。人の人生で無駄なものはひとつもない。どんな些細なものでも、生きているうえの意味がある。そういったメッセージを伝えようとするのがアーヴィングの作風でもある。
是非とも一読を。
【この書評が収録されている書籍】
大学時代、ある先生がこう言われたのをいまでも覚えている。 「きみたちは若いから、まだまだ時間があると思っているでしょう。しかし、よく考えてごらんなさい。今、二十歳で、あと五十年生きられるとして計算するとね、きみたちに残された日々は一万八千二百五十日ですよ。まあ、簡単に二万日と考えてもいい。するとね、あとどれくらい本が読めると思います? 一日一冊で二万冊。そんなに読めるはずはないから一週間に一冊読むと仮定して計算すると、およそ二千八百冊です。いいですか。二千八百冊しか読めないんですよ。だからぼくはきみたちに言いたい。良書を読みなさい。時間を大事にしなさい」
このときわたしは本当に驚き焦った。この先一日一冊読んでも死ぬまでに二万冊くらいしか読めないとは。これはあくまでも後五十年生きると仮定してのことで、もっと短いかもしれない。そこでわたしはそれから一年間、本当に一日最低でも一冊は読んだ。当時の手帳が残っているので、それをいま見ると、良書ばかりを読んでいたわけではない。時間を無駄にしたと思われるような本もたくさん読んでいる。
しかしそれでよかったのではないか、といまにして思う。というのも、いまなら本当に雑多な本など読みたいとは思わないからだ。若いときにしか、まだ価値観や人生観が固まっていない時期にしか、雑多な本は読めないのである。
さて、今月は長編を紹介しよう。別に秋の夜長にむけて、というわけではないけれど、やはり小説の醍醐味を味わうためには長編小説を読まないといけない。ジョン・アーヴィングの『サイダーハウス・ルール』はアーヴィングの六作目の本である。名前を聞いたことのある人も多いのではないだろうか。日本に初めて紹介されたのはかれこれ十五年ほど前になるが、『ガープの世界』という、特異な作家ガープをめぐる物語だった。アーヴィングの小説はどれもそうだが、とにかく物語の展開がすさまじい。しかもとても視覚的で、映像的である。『ガープの世界』も、それに続く『ホテル・ニューハンプシャー』も映画化されたので、あるいは観た人もいるのではないだろうか。
アーヴィングの描く世界には、アメリカという国が抱えているあらゆる問題(人種問題、性的問題、政治、文化、スポーツ、中絶問題、戦争)、人間のあらゆる局面(幸福、不幸、悲嘆、怒り、嫉妬、歓喜、生、性、死、冒険などなど)が詰め込まれている。どの作品をとっても、とにかく盛りだくさんの小説である。
アーヴィング自身が、ディケンズに影響されている、十九世紀的な世界にどんどん近づいている、と述べているくらいだから、彼には小説というものがどういう形であるべきか、あるいはどういう世界であるべきかというヴィジョンがしっかり確立している。しかし、だからといって古めかしい作品なのではない。 『サイダーハウス・ルール』は、孤児の物語である。アーヴィングという作家は、どういうわけか、普通ではない人を大変な情熱を持って描く。普通ではない、というとおかしな言い方になるけれど、たとえば『ガープの世界』では、性転換をしたフットボール選手が重要な役割を担っているし、レイプされて舌を切られた女性や、事故で片目をなくした子供が登場し、『ホテル・ニューハンプシャー』では、耳の悪い子、背が伸びない病気の子、熊のぬいぐるみを着て暮らす娘などが登場する。本書でとりわけ変わっているのは、エーテル中毒の堕胎医ウィルバー・ラーチ先生だ。
この小説は、アメリカの三〇年代から始まる。ラーチ先生は、臨月になった女性の出産を手伝い、その結果生まれた子を、自分の経営する孤児院に入れるかたわら、図らずも妊娠してしまった女性の堕胎も執り行なっている。前者を「神の業」と呼び、後者を「悪魔の業」と呼びながら。ラーチ先生は、孤児院の子供たちがそれぞれにしかるべき養父母に引き取られるように手を尽くす。彼は克明に日記をつけていて、孤児たちが人生を生き抜くためのルールをそこに書きつけていく。
だが何度養子縁組をさせても孤児院に戻ってきてしまう少年がいて、それが先生の悩みの種になる。それがこの小説の主人公たるホーマー・ウェルズだ。結局唯一の例外として、ラーチ先生はホーマーを孤児院に置くことを決意する。
それからのホーマーの人生が一大叙事詩のように語られていく。ホーマーの生き方の目標は「人の役に立つこと」だった。彼は孤児院をなんとか存続させるために、努力を惜しまずに働く。しかし、やがてはそこを飛び出して、自分の世界を探そうとする。リンゴ園に落ちつき、そこで働くようになったホーマーは、そこで愛することを覚えるが、結局は人妻になる女性との間に子供を持ち、その子を孤児として届け出て、養子として育てることにする。
アーヴィングの小説に出てくる人々は、絶えず自分とは何者なのか、何のために生まれてきたのか、ということを考え続ける。
その結果『ガープの世界』では、ガープの母親はレイプされた女たちのために避難所を設立し、『ホテル・ニューハンプシャー』では夢のようなホテルを作る父親が現われる。人の人生で無駄なものはひとつもない。どんな些細なものでも、生きているうえの意味がある。そういったメッセージを伝えようとするのがアーヴィングの作風でもある。
是非とも一読を。
【この書評が収録されている書籍】
BURRN!
世界最大の実売部数を誇るヘヴィ・メタル/ハード・ロック専門誌。海外での独占取材を中心に、広いネットワークで収集した情報量の多さと、深く掘り下げた読み応えのある記事の質の高さは、幅広いファン層から熱烈に支持されているのみならず、世界中のミュージシャンからも深い信頼を受けています。
ALL REVIEWSをフォローする