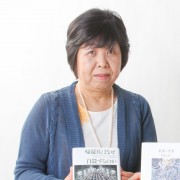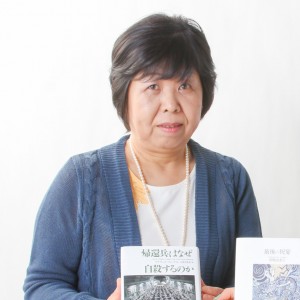書評
『文体練習』(朝日出版社)
レーモン・クノー『文体練習』を、是非とも書店で一度は手にとって眺めてみてほしい。体裁のわりには値段の高い本であるから、無理に買えとは言わない。でもまあ、中を覗けば一驚し、必ず買いたくなるでしょう。
タイトルのとおり、この本のテーマは文体の練習で、ある一つの事象をさまざまな文体で書き分けた、きわめて偏執的な本である。一つの事象というのは、二つの段落で構成されている。帽子を被った首の長い男がバスに乗ってきて、その男が他の乗客とちょっと言い争ってから空席に座るのを書き手が見た、という段落。そしてその男が別の男と話している姿を二時間後にまた見かけた、という段落だ。
その些細な出来事をなんと九十九通りに書き分けるという、サーカスの曲芸師のようなことをやってのけているのである。もちろん翻訳者・朝比奈弘治もかなり偏執的だ。そこがいい。腕がなってしかたがない、といった顔つきで仕事をしている様子が目に浮かんでくる。翻訳を仕事にしている者でなくとも、この本を訳すのにどれほどの苦労があったのか、そしてどれほどの喜びがあったのかが察せられるはずだ。わたしなどはため息をつきつつ読んだ。感嘆と驚愕と羨望とがまじったため息である。翻訳者にとっては、こういった種類の課題は武者震いを起こさせるものなのである。
一つの話をいろいろな文体で表現するというのは、音楽でたとえるならば、変奏曲と言えるかもしれない。ほらモーツァルトだったか、「きらきら星変奏曲」というのがあるでしょう。主題をさまざまな曲想へとつぎつぎに変化させていく。ただ、この本の場合、読者の予想を大幅に裏切ることを、あるいは読者を驚かせたり、唸らせたりすることに命をかけている部分が多々あるので、ゆっくりと耳を傾けているわけにはいかない。文体に参加しているような気になってくる。
「ある日のお昼頃、バスの後部デッキに、ソフト帽をかぶった首の長い男が乗っている」という事実を伝える文章が、どのような変化を遂げていくか。その例をいくつか挙げて紹介しよう。
『音の反復』──身分の区分もなしに余分な文士や文官までふんだんにつめこんでぶんぶん走る文化バスの分離デッキで、首が噴霧器のようにぶん長く、リブンの代わりに紐をぶん巻いた噴飯ものの帽子を被った醜男が、身分の分もわきまえず……、延々と「ブン」の音が続く文体。ちなみにリブンとはリボンですね。
『感嘆符』──あれっ! もうお昼だ! バスに乗らなきゃ! わっ! 満員だ! 満員だ! ひどいな! 何だ、あいつ! 変な奴だな! 何ておかしな顔だ! それに、あの首! 七十五センチはあるぞ! いや、もっとある!
『あのー』──あのー、バスが来たんです。それで、あのー、乗ったんですが、あのー、若い男がいて、気になったんですよ。あのー、首が長くて、そのー、帽子に紐を巻いて、あのー……
『聴覚』──クラクションをパフパフ鳴らし、エンジンをブルンブルンと唸らせて、S系統のバスが町の静寂を乱しながら、キキーッというブレーキ音を響かせて停車した。
『電報』──バ スコム クビ ナガ イワカモノ ヘンナボ ウシノヒモ トナリノキャクニイチャモン……
『古典的』──昼は、バス。満員のころはさらなり、やうやう乗り込んだデッキぎは、人あまたひしめきて、つま先立ちたる客のほそく詰め合ひたる。男は、くび。毛などまばらに生えたるが、いと長う見ゆるは、言ふべきにもあらず。
『聞き違い』──主のお汁ごろ、餌付け糸を伸ばすの甲府鉄器で、わらじは、ほろ苦い苦病した馬鹿殿を磨けた。パンダ、疲労、巻き酢下駄、棒塩かじっている。
『いんちき関西弁』──お昼ごろやったかいなあ、バスのうしろん方にデッキいうもんが付いてまっしゃろ。あこに乗ってましたんや。ほたら、あんた、アホな男はんがいはりますねん。
挙げていったらきりがない。なんせ九十九通りもあるのだから。しかしこうして写しているうちに全部書き出したくなってしまった。つまり、こういうのは面白い遊びと同じで、どんどん深みにはまっていく運命にあるのだ。そして上等な遊びと同じように、読んでいるうちに自分ならではの文体を書きたくなってくるから不思議である。
上記のほかにも面白い文体はわんさとあるのだが、わたしが一番驚いたのは『イギリス人のために』というものである。冒頭だけ記すと、
「R he know off eel gallow, what a she were, bus knee no ream ash-eater. Man in death-eater. Heatly no worker monogamy aim ash-eater. So knock be were totem honor guark,……」という具合。「わたしは」が「what a she were」になっているところで思わず唸ってしまった。なんという大胆不敵な。
こういうものが九十九通りもあるんですぜ。まったくいやになっちまいますよ、旦那。あっしもね、これまでにいろんな本、読んできましたよ。しかしですね、こんな突拍子もない本、お初にお目にかかりやす、って感じでさ。値段ね、値段はちょっとお高い。ですがね、ちょっと気の利いた料理を食べればそのくらいすぐにするもんだ。しかも料理なんてものは、食えばなくなるもんですぜ。どうせなら食べた気になって、この本読んだ方がよっぽどいいって言うお人だっていないとも限らない。こういうご時世ですからねえ。いや、なに、ほんと。
【この書評が収録されている書籍】
タイトルのとおり、この本のテーマは文体の練習で、ある一つの事象をさまざまな文体で書き分けた、きわめて偏執的な本である。一つの事象というのは、二つの段落で構成されている。帽子を被った首の長い男がバスに乗ってきて、その男が他の乗客とちょっと言い争ってから空席に座るのを書き手が見た、という段落。そしてその男が別の男と話している姿を二時間後にまた見かけた、という段落だ。
その些細な出来事をなんと九十九通りに書き分けるという、サーカスの曲芸師のようなことをやってのけているのである。もちろん翻訳者・朝比奈弘治もかなり偏執的だ。そこがいい。腕がなってしかたがない、といった顔つきで仕事をしている様子が目に浮かんでくる。翻訳を仕事にしている者でなくとも、この本を訳すのにどれほどの苦労があったのか、そしてどれほどの喜びがあったのかが察せられるはずだ。わたしなどはため息をつきつつ読んだ。感嘆と驚愕と羨望とがまじったため息である。翻訳者にとっては、こういった種類の課題は武者震いを起こさせるものなのである。
一つの話をいろいろな文体で表現するというのは、音楽でたとえるならば、変奏曲と言えるかもしれない。ほらモーツァルトだったか、「きらきら星変奏曲」というのがあるでしょう。主題をさまざまな曲想へとつぎつぎに変化させていく。ただ、この本の場合、読者の予想を大幅に裏切ることを、あるいは読者を驚かせたり、唸らせたりすることに命をかけている部分が多々あるので、ゆっくりと耳を傾けているわけにはいかない。文体に参加しているような気になってくる。
「ある日のお昼頃、バスの後部デッキに、ソフト帽をかぶった首の長い男が乗っている」という事実を伝える文章が、どのような変化を遂げていくか。その例をいくつか挙げて紹介しよう。
『音の反復』──身分の区分もなしに余分な文士や文官までふんだんにつめこんでぶんぶん走る文化バスの分離デッキで、首が噴霧器のようにぶん長く、リブンの代わりに紐をぶん巻いた噴飯ものの帽子を被った醜男が、身分の分もわきまえず……、延々と「ブン」の音が続く文体。ちなみにリブンとはリボンですね。
『感嘆符』──あれっ! もうお昼だ! バスに乗らなきゃ! わっ! 満員だ! 満員だ! ひどいな! 何だ、あいつ! 変な奴だな! 何ておかしな顔だ! それに、あの首! 七十五センチはあるぞ! いや、もっとある!
『あのー』──あのー、バスが来たんです。それで、あのー、乗ったんですが、あのー、若い男がいて、気になったんですよ。あのー、首が長くて、そのー、帽子に紐を巻いて、あのー……
『聴覚』──クラクションをパフパフ鳴らし、エンジンをブルンブルンと唸らせて、S系統のバスが町の静寂を乱しながら、キキーッというブレーキ音を響かせて停車した。
『電報』──バ スコム クビ ナガ イワカモノ ヘンナボ ウシノヒモ トナリノキャクニイチャモン……
『古典的』──昼は、バス。満員のころはさらなり、やうやう乗り込んだデッキぎは、人あまたひしめきて、つま先立ちたる客のほそく詰め合ひたる。男は、くび。毛などまばらに生えたるが、いと長う見ゆるは、言ふべきにもあらず。
『聞き違い』──主のお汁ごろ、餌付け糸を伸ばすの甲府鉄器で、わらじは、ほろ苦い苦病した馬鹿殿を磨けた。パンダ、疲労、巻き酢下駄、棒塩かじっている。
『いんちき関西弁』──お昼ごろやったかいなあ、バスのうしろん方にデッキいうもんが付いてまっしゃろ。あこに乗ってましたんや。ほたら、あんた、アホな男はんがいはりますねん。
挙げていったらきりがない。なんせ九十九通りもあるのだから。しかしこうして写しているうちに全部書き出したくなってしまった。つまり、こういうのは面白い遊びと同じで、どんどん深みにはまっていく運命にあるのだ。そして上等な遊びと同じように、読んでいるうちに自分ならではの文体を書きたくなってくるから不思議である。
上記のほかにも面白い文体はわんさとあるのだが、わたしが一番驚いたのは『イギリス人のために』というものである。冒頭だけ記すと、
「R he know off eel gallow, what a she were, bus knee no ream ash-eater. Man in death-eater. Heatly no worker monogamy aim ash-eater. So knock be were totem honor guark,……」という具合。「わたしは」が「what a she were」になっているところで思わず唸ってしまった。なんという大胆不敵な。
こういうものが九十九通りもあるんですぜ。まったくいやになっちまいますよ、旦那。あっしもね、これまでにいろんな本、読んできましたよ。しかしですね、こんな突拍子もない本、お初にお目にかかりやす、って感じでさ。値段ね、値段はちょっとお高い。ですがね、ちょっと気の利いた料理を食べればそのくらいすぐにするもんだ。しかも料理なんてものは、食えばなくなるもんですぜ。どうせなら食べた気になって、この本読んだ方がよっぽどいいって言うお人だっていないとも限らない。こういうご時世ですからねえ。いや、なに、ほんと。
【この書評が収録されている書籍】
BURRN! 1997年3月号
世界最大の実売部数を誇るヘヴィ・メタル/ハード・ロック専門誌。海外での独占取材を中心に、広いネットワークで収集した情報量の多さと、深く掘り下げた読み応えのある記事の質の高さは、幅広いファン層から熱烈に支持されているのみならず、世界中のミュージシャンからも深い信頼を受けています。
ALL REVIEWSをフォローする