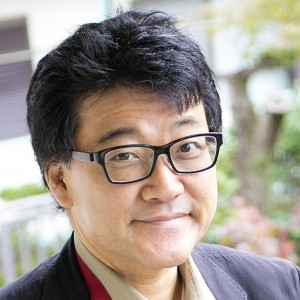書評
『ルビコン・ビーチ』(筑摩書房)
スティーヴ・エリクソン(Steve Erickson 1950- )
アメリカの作家。『彷徨(さまよ)う日々』(1985)でデビュー。空間がよじれたロサンゼルスを描く『ルビコン・ビーチ』(1986)、ヒトラーを扱った歴史改変小説『黒い時計の旅』(1989)など、話題作を次々に発表。最近は大学で創作講座を担当する一方、文芸誌Black Clockの編集でも活躍している。そのほかの著作に『Xのアーチ』(1993)、『アムニジアスコープ』(1996)、ノンフィクション『リープ・イヤー』(1989)などがある。introduction
スティーヴ・エリクソンは現代世界文学のなかでは、日本の読者からの支持もそれなりにあり、また翻訳者にも恵まれて、ほとんどの作品が紹介されている。長いこと待ちのぞんだ『アムニジアスコープ』も、2005年に柴田元幸氏の名訳で読めるようになった。これもロサンゼルスが舞台だが、現実のロサンゼルスではなく、大震災を経て街中にいくつもの違った「タイム・ゾーン」が存在している別な現実が描かれている。ぼくにとって興味ぶかいのは「タイム・ゾーン」が前景化されることなく、あくまでハイウェイや高層ビルとおなじような日常として扱われていることだった。「タイム・ゾーン」が具体的にどういうものなのか、物語のなかで整合性はとれているのか、そういう問いをしてもあまり意味がない。ぼくらが生きている街はそういう曖昧なものだから。▼ ▼ ▼
ジョルジョ・デ・キリコの代表作『街の神秘と憂愁』は、ぼくの大好きな絵画のひとつだ。まず題名がすばらしい。懐かしさと不安とを同時に喚起する、呪文のような響き。絵柄もそれにふさわしい。眩むような遠近法で描かれた夕刻の街角、ひとりの少女が手に持った棒で車輪をまわしながら走りさっていく。
そもそも街が街であるのは、そこに得体の知れないものが潜んでいるからだ。一片の神秘も持たず、わずかばかりの憂愁も匂わない街は、退屈な生活空間かたんなる建造物の集合にすぎない。いや、いかに整然と計画された街でさえ、いつのまにか、機能性とは無縁の袋小路や廃屋を胚胎していくものだ。木の根のように分岐/短絡する路地、打ちすてられた街区のうえを無関心に横ぎるハイウェイ、高層ビルのガラスからの照りかえしを受ける時代おくれの遊廓……。
『ルビコン・ビーチ』のロサンゼルスには音楽が流れている。
街に来てまもまく、あの音楽がそこかしこから聞こえてくるのに気がついた。最初の晩にチャイナタウンから聞こえてきた音楽だ。建物からも聞こえたが、どれも独特な一つ一つ違う調べだった。街ですれ違う連中もよく口ずさんでいた。(略)
音楽が流れてくる場所を聞き回っていたら、そのうち誰かが教えてくれた。海の音楽だ。街に海水が漏れ、地下で泉や川をつくっている音なのだ。空っぽの建物に川の音が響き、通りに流れる音楽になるのだ。昨日までまっすぐ建っていたビルが朝にはつぶれて地面にめりこんでいることもあった。そんなときは石ころの間でシュウシュウ鳴る音楽になった。
奇妙な音楽が響く街。海水が地下を浸す街。観光案内や地誌では紹介されないロサンゼルス。刑務所を仮釈放となったケールという男が、この街にたどりつく。彼は図書館に住みこみで働きはじめるが、人と接触することのない職務で、あいかわらず牢獄にいるようだ。夕方になって外出すると、FBIが尾行してくる。ケール自身、なぜ自分がマークされるかわからない。刑務所にいたとき、たわいないジョークを口走った。そのせいで仲間がひとり絞首刑になった。それがそんなに重要なことなのか。
ある夜、ケールは浜辺で一組の男女を目撃した。女はナイフを振るい、ひざまづいた男の頭を切りおとす。月光は女の瞳まではっきりと照らしていたが、ケールはそのあとのことを覚えていない。警察が来たときには、女の姿も男の死体も消えていた。それから数日後、図書館で殺人がおこる。ケールの目前で、女が男の頭をナイフではねたのだ。浜辺のときとそっくりおなじ。これは夢にちがいないと思うが、床には大量の血が残っている。しかし死体も凶器も見つからない。
ケールの脳裏から謎の女が離れなくなる。「かつて誰かが彼女について書いた詩がたやすく頭に浮かんできた」とまで言う。しかしなぜ、詩で詠われている女が、謎の女とおなじ人物とわかるのか。そして、また殺人事件が繰りかえされる。おなじ女がおなじ男をおなじやり方で殺した。あいかわらず女の正体は不明だが、今度は男の死体が残った。ケールは、男は自分のせいで絞首刑になった監獄仲間に違いないと思いこんでいるのだが、検死の結果、意外なことが判明する。
もちろんこの小説は、ふつうの意味でのミステリではない。謎解きを成立させる合理性どころか、大前提となるリアリズムを逸脱している。たとえば「お前が生まれたのはアメリカ1か? アメリカ2か?」などという科白が、なんの説明もなく挿入されるのだ。
ケールの物語は、三部からなる『ルビコン・ビーチ』の第一部にあたる。
第二部では、南米の迷路のような川で育った娘キャサリンが主人公だ。彼女は川沿いに放浪していたが、妙な経緯でロサンゼルスに迷いこむ。第一部で影のように描かれていた謎の女は、どうやらこのキャサリンらしい。キャサリンに魅せられた男が憑かれたように詩を書く。それが、ケールの頭に浮かんだ「かつて誰かが彼女について書いた詩」なのだろう。しかし、暗合のようなこの関連をたどってみても、謎の女の正体はいっこうにつかめない。彼女は、なぜおなじ男を繰りかえし殺さなければならなかったのか?
第三部では、インディアンの血を引く青年レイクが、イギリスの港町で奇妙な老人と出会う。ふたりはある晩、岬で謎の女を目撃するが、その直後に老人は死んでしまう。レイクはその意志を継いで、謎の女を追って、ふたたび海を越えてアメリカへと戻る。
レイクが出会った老人は、どうやら第一部の主人公ケールのようだ。そして、ここにも謎の女が登場する。しかし、登場人物の消息が詳しく語られることはない。というよりも彼らは普通の意味での人格や個性を持たない。そう、キリコの絵のようなものだ。『街の神秘と憂愁』の少女には表情がなかった。キャサリンと謎の女が同一人物かどうかは問題ではなく、彼女を通じてあらわれる謎や運命こそが主役だ。
謎の女にとり憑かれたケールの心に浮かんだ詩は、キャサリンを謳ったものだった。レイクは幼いころに地面から響いてくる音楽を聞いたというが、それはケールの住むロサンゼルスに満ちていたあの音楽かもしれない。第一部でジェネットと名乗る女が殺人現場を撮影するが、そのピンぼけ写真が第三部ではまったく関係のない部屋の壁にかかっている。
こうした断片的なイメージが作品中を走り、異なる場所と時間、人物を結びつけている。それは、まるで街の狭く入りくんだ路地のようだ。ぼくたち読者は、路地から路地へとめぐり、そこに潜んだ色彩や匂いや響きにふれるばかりだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする