書評
『テクスト世紀末』(ポーラ文化研究所)
作家は誰でも、一つだけ、自分の方法論が、ガラス張りの時計細工のように透けて見える作品を書くものだといったのは、確か三島由紀夫だったと思うが、これは作家に限らず、たいていの物書きについても当てはまる。
あらゆる点から見て、『テクスト世紀末』が、驚異的な学識を誇る高山宏氏の方法論を浮き彫りにするこうした貴重な書物の一つであることはまちがいない。その方法論は、すでにして「テクスト世紀末」というタイトルそれ自体に現れている。それは巻頭におかれたマニフェストを読めば歴然としている。
だが、ここでは「世紀末」にしろ、「テクスト」にしろ、一般的な通念とは多少異なったニュアンスで使われているので、とりあえずはこれらの用語に込められた意味の検討から入っていかなければならない。
まずは「世紀末」。このタームは従来、「《耽美》と《頽廃》の共同幻想のもと」にくくられるラファエル前派やビアズリー、フランス象徴派やクリムトなどを指すのに用いられてきたが、著者はあえてこれを「十九世紀の最後のディケード」と直解することにこだわろうとする。というのも、著者は、このように共時的に時代を輪切りにしてみることで、通時的な思考からは抜け落ちてしまう構造的な相同性が、同時代の、一見なんの関係もないようなファクターの間に浮かび上がってくることを、誰よりもよく承知しているからである(この意味では、辞書、カタログといった、おなじみの高山ガジェットのほかに、もう一つ、ヨーロッパ総合年表というものを付け加えてもいいような気がするのだが)。
そればかりではない。世紀末は、百年という単位で歴史を画する習慣のあるヨーロッパ社会にとって、その世紀を総括する特権的なディケードであるばかりか、ある意味ではその世紀の含んでいたプロブレマティックをより一層鮮明にする傾向をもっているがゆえに、ミシンとこうもり傘を手術台の上でリンクさせてしまうシュルレアリスト的なコツを体得している著者にとっては観念連合の枝を無限に伸ばしていくことのできる、一つの黄金時代と映じているのである。
もっとも著者は、謙虚にも、執筆の動機として、この五年ほどの間に怒濤のように出版されだした、海外の世紀末研究に刺激を受けたことをあげているが、実は、こうしたニュータイプの世紀末研究を拾いあげて次々に読破し、それらを「放埒(ほうらつ)に連環」させていくことができる人間は、結局のところ、日本にはそうは多くない。研究書を一、二冊読んで、紹介することぐらいなら、誰にでもできるかもしれないが(著者によれば、それすらも行われていないという)、かけ離れた要素の間に相同性を見抜く感性を備えると同時にサンクロニックな結合術(アルス・コンビナトリア)を自家薬籠中(じかやくろうちゅう)のものにして、あらゆる研究書の提起する問題を自在に関連させて、そこに独自の問題意識を浮かびあがらせることのできるのは、やはり高山宏氏以外にはいないのである。
ところで今、アルス・コンビナトリアという言葉を使ったが、これこそは、著者がホッケや澁澤龍彦から受け継いだ方法論の一つにほかならない。すなわち、「相反するものの合一」という原理にもとついて、あらゆるものに深層のアナロジーを探り、これを経糸と緯糸で自在に織りあわせ、そこに、今までとはまったく異なる織物を出現させるというこの方法、つまり、テクスチュアリテこそが、ワンダー高山ランドのゲームの規則なのである。とするなら、「テクスト世紀末」という標題は二重の意味で著者の方法論を現しているということになるが、実はこうした方法論は、マクロ・テクストたる高山宏のニューロン回路のみならず、ミクロ・テクストとしての各章、各テーマにも貫徹しているのである。
「テクスト世紀末」のタイトルのもとに、今回、著者が召喚したテーマ群は、以下の通りである。
すなわちギリシャ・ローマ神話を題材にしたアカデミックな画風で、ラファエル前派と同時代に世紀末イギリス画壇を支配していたレイトンやアルマ=タデマなどのオリンピアンの画家たち。印象派と覇を競いながらハーレムの女奴隷をテーマにした数々の絵画を残したジェロームなどのオリエンタリズムの画家。世紀末英仏社交界の風俗を描いて人気を博したティソ。典型的な世紀末の作家であるにも拘らず、なぜかそうは扱われてこなかったプルースト。思いっきりゴテゴテとカーテンや家具で部屋を飾った世紀末インテリア。一八八〇年代に突如アメリカで大流行したアメリカン・トロンプ・ルイユ。さらに、シャーロック・ホームズと顕微鏡。地下鉄とフロイト。デパート。木馬館などなど。
なるほど、世紀末を「十九世紀末の最後のディケード」と解するなら、これらは、すべて視野に入ってくるテーマではある。だが、ビアズリーやクリムト、象徴派や印象派ではなく、あえてこれらを取る理由はなんなのか。
(次ページに続く)
あらゆる点から見て、『テクスト世紀末』が、驚異的な学識を誇る高山宏氏の方法論を浮き彫りにするこうした貴重な書物の一つであることはまちがいない。その方法論は、すでにして「テクスト世紀末」というタイトルそれ自体に現れている。それは巻頭におかれたマニフェストを読めば歴然としている。
十九世紀末をテクストの時代であったと言ってみよう。
だが、ここでは「世紀末」にしろ、「テクスト」にしろ、一般的な通念とは多少異なったニュアンスで使われているので、とりあえずはこれらの用語に込められた意味の検討から入っていかなければならない。
まずは「世紀末」。このタームは従来、「《耽美》と《頽廃》の共同幻想のもと」にくくられるラファエル前派やビアズリー、フランス象徴派やクリムトなどを指すのに用いられてきたが、著者はあえてこれを「十九世紀の最後のディケード」と直解することにこだわろうとする。というのも、著者は、このように共時的に時代を輪切りにしてみることで、通時的な思考からは抜け落ちてしまう構造的な相同性が、同時代の、一見なんの関係もないようなファクターの間に浮かび上がってくることを、誰よりもよく承知しているからである(この意味では、辞書、カタログといった、おなじみの高山ガジェットのほかに、もう一つ、ヨーロッパ総合年表というものを付け加えてもいいような気がするのだが)。
そればかりではない。世紀末は、百年という単位で歴史を画する習慣のあるヨーロッパ社会にとって、その世紀を総括する特権的なディケードであるばかりか、ある意味ではその世紀の含んでいたプロブレマティックをより一層鮮明にする傾向をもっているがゆえに、ミシンとこうもり傘を手術台の上でリンクさせてしまうシュルレアリスト的なコツを体得している著者にとっては観念連合の枝を無限に伸ばしていくことのできる、一つの黄金時代と映じているのである。
もっとも著者は、謙虚にも、執筆の動機として、この五年ほどの間に怒濤のように出版されだした、海外の世紀末研究に刺激を受けたことをあげているが、実は、こうしたニュータイプの世紀末研究を拾いあげて次々に読破し、それらを「放埒(ほうらつ)に連環」させていくことができる人間は、結局のところ、日本にはそうは多くない。研究書を一、二冊読んで、紹介することぐらいなら、誰にでもできるかもしれないが(著者によれば、それすらも行われていないという)、かけ離れた要素の間に相同性を見抜く感性を備えると同時にサンクロニックな結合術(アルス・コンビナトリア)を自家薬籠中(じかやくろうちゅう)のものにして、あらゆる研究書の提起する問題を自在に関連させて、そこに独自の問題意識を浮かびあがらせることのできるのは、やはり高山宏氏以外にはいないのである。
ところで今、アルス・コンビナトリアという言葉を使ったが、これこそは、著者がホッケや澁澤龍彦から受け継いだ方法論の一つにほかならない。すなわち、「相反するものの合一」という原理にもとついて、あらゆるものに深層のアナロジーを探り、これを経糸と緯糸で自在に織りあわせ、そこに、今までとはまったく異なる織物を出現させるというこの方法、つまり、テクスチュアリテこそが、ワンダー高山ランドのゲームの規則なのである。とするなら、「テクスト世紀末」という標題は二重の意味で著者の方法論を現しているということになるが、実はこうした方法論は、マクロ・テクストたる高山宏のニューロン回路のみならず、ミクロ・テクストとしての各章、各テーマにも貫徹しているのである。
「テクスト世紀末」のタイトルのもとに、今回、著者が召喚したテーマ群は、以下の通りである。
すなわちギリシャ・ローマ神話を題材にしたアカデミックな画風で、ラファエル前派と同時代に世紀末イギリス画壇を支配していたレイトンやアルマ=タデマなどのオリンピアンの画家たち。印象派と覇を競いながらハーレムの女奴隷をテーマにした数々の絵画を残したジェロームなどのオリエンタリズムの画家。世紀末英仏社交界の風俗を描いて人気を博したティソ。典型的な世紀末の作家であるにも拘らず、なぜかそうは扱われてこなかったプルースト。思いっきりゴテゴテとカーテンや家具で部屋を飾った世紀末インテリア。一八八〇年代に突如アメリカで大流行したアメリカン・トロンプ・ルイユ。さらに、シャーロック・ホームズと顕微鏡。地下鉄とフロイト。デパート。木馬館などなど。
なるほど、世紀末を「十九世紀末の最後のディケード」と解するなら、これらは、すべて視野に入ってくるテーマではある。だが、ビアズリーやクリムト、象徴派や印象派ではなく、あえてこれらを取る理由はなんなのか。
(次ページに続く)
初出メディア
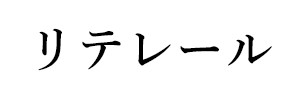
リテレール(終刊) 1993年3月
ALL REVIEWSをフォローする


































