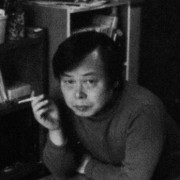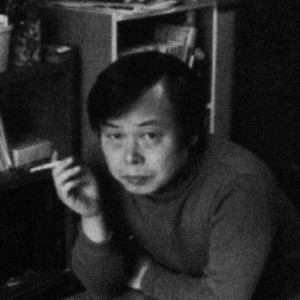書評
『終末のオルガノン』(作品社)
ワット氏の歩み――あるいは高山病症候群のこと
この度は『終末のオルガノン』お送り下さいましてありがとうございました。『魔の王が見る』、『江戸の切り口』と立て続けに月刊「高山」の連打を食らったところへ『終末…』のダメ押し、十年前の『アリス狩り』以来、毎度滅多打ちになってきた小生など、もはやマットに崩れて終末のタオルを待つばかりのていたらくとは相成りました。案ずるに、いまや高山病症候群はいたるところに蔓延しはじめています。いや、いたるところ、各時代に、高山病が蔓延していた消息があらためて発見された、といったほうが実情に適っておりましょう。
強力な高山病原体がかねてより発見されていた十六世紀マニエリスム期はいうに及ばず、十七世紀英国の王立協会ですら高山病の既往症を病んでいた消息が『終末のオルガノン』には活写されております。のみならず『江戸の切口』では、あろうことかわが江戸人にも高山病の既往症があるらしき兆候が見えてきました。この分では中国に飛び火して、明清や宋代の高山病がまもなく医学考古学的に発掘されることでしょう。
おそるべきは高山病です。では、この病気にかかるとどうなるか。身の回りのなにもかもが本になってしまいます。ミダス王が手に触れたものがことごとく金になってしまったように、手に触れるものすべてが本になる。本は食べられませんから、当然飯の食い上げになります。
のみならず高山病は不治の病です。テーブル化する衝動とテーブルから排除されたがる衝動が同時併発して、ダブルバインドの迷宮に深入りせざるをえないので、いつかな出口に到達しません。テーブル化する衝動においては奔馬性の症候を帯びますが、非テーブル化する解体衝動においてはカオス的に渦巻いて、死と硬直に向かう奔馬の脚を遅延せしめます。「ノイズをテクストに変えていく『アリアドネー』の誘惑に耐えよう。『出口』への誘惑に。」
高山病に対するドクター高山の処方は右(事務局注:上)のごとくです。ところがこの場合病人のほうがえてして医者より元気がよく、病みつきになったが最後止めて止まるような玉ではなくて、あれよあれよとばかり超スピードでメールシュトレームの渦に呑み込まれてゆきそう。それでいて、あやうく渦の中心の手前でぷかぷか浮いている。「誘惑に耐えよう。『出口』への誘惑に――。」
病気も治療もそれぞれ猛烈な速度で進行しながら両者の力が伯仲して、当事者は独楽のように回転しながら不動のままと見えるのでしょう。そういえば大兄に一度だけお目に掛かったことがありますが、あとで高橋康也さんに「ワット氏に会いました」と葉書に報告しました。歩きだそうとしてどちらかの足を出すとどちらかの足がそれを邪魔して、結局はぎくしゃくしたオドラデクの歩みになってしまう、あのワット氏の出口なし。どうか高山病症候群を線的にではなく蛇状曲線的に、つまりは気長に病んで下さい。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする