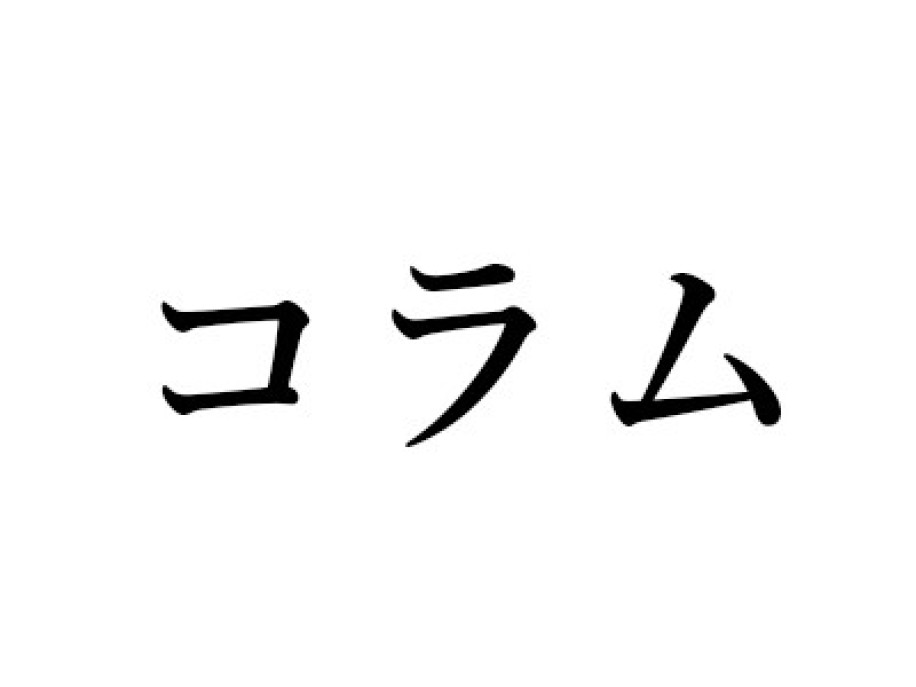書評
『黙約』(新潮社)
解けぬ殺意の謎
国際的名声をもつにも拘(かかわ)らず、日本では比較的知名度が低い作家がいる。ドナ・タートもその一人だろう。四半世紀前に殺人ミステリの本作で鮮烈なデビューを果たし、同書が全米ベストセラーに躍りでた。三作目の『ゴールドフィンチ』でピュリツァー賞フィクション部門を受賞し、第一作にもまさる評価を得ている。ひと言で名状しがたい強烈な魅力をもつ作品だ。衝撃の犯罪シーンがあるわけでもなく、謎解きの鮮やかさを見せつけるわけでもない。いや、それどころか、だれが死ぬのかは、一ページ目の一行目にはっきり書いてある。どんな死に方をしたのかも、最初のページでわかる。主な登場人物は、わずか六、七人。
なにがそんなに読み手を引きつけるのか――。
舞台となるのは、ヴァーモント州の名門リベラル・アーツ・カレッジだ。そこに、カリフォルニア州シリコン・ヴァレーのプレイノーから、貧乏学生リチャードが奨学金を受けてやってくる。世俗の愉(たの)しみにあふれた西海岸から、神秘的な霧につつまれた東部の山中へ。彼は「ハンプデン・カレッジ」の蔦(つた)のからまる寄宿舎や、築百数十年の建築に目を瞠(みは)り、古代ギリシャ語を専攻しようとするが、この担当教授がとんでもない変人。目下、たった五名の生徒しかとっていないという。履修生たちもそろって変わり者である。英国仕立てのスーツにこうもり傘を持って歩くヘンリー、着たきり雀(すずめ)で声のやたら大きなバニー、「学生王子と切り裂きジャックを足して二で割ったような」金持ちのフランシス、フランドル絵画の天使を思わせる瓜二つの男女の双子チャールズとカミラ。リチャードは俗離れした彼らに憧れを抱き、この別世界に飛びこんでいく。
六人は「リュケイオン館」にある教授の部屋で、古代ギリシャ哲学や文学の探求に勤(いそ)しむ。教授に導かれて分け入るその世界には危険な誘惑があり、彼らはやがてバッコス祭における忘我の恍惚(こうこつ)を体験すべく、儀式の行為を模倣し、熱狂を再現しようとする。その最中に――。
一種の倒叙ミステリとしてだけではなく、キャンパスノベルとしての醍醐味(だいごみ)もあるだろう。遺体が発見された後の展開もシリアス一辺倒ではなく、ユーモアとアイロニーがうっすらとまぶされている。だれもかれもが故人の「良き友」になって株を上げようとし、故人を悼んで植樹やコンサートから、曼陀羅(まんだら)織りやら、およそ故人と関係ない飲み会まで、ありとあらゆるイベントが開催される。まさに今米国で大ヒット中のハイティーンを主人公にしたミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」にも通じるテーマ性がある。
某人物の殺害には、明確な理由がひとつある。しかし、それは、漠然とした殺意がついに形をとるきっかけに過ぎなかったのではないか。
死はどんな経緯で引き起こされたのか。「だれが」「何を」という謎ではなく、「なぜ」の部分を追っていくことになる。作中のある箇所に、[質屋のばあさんとその妹のリザベータを斧(おの)で殺し、金を奪ったのはこのおれだ]という一文が唐突に差し挟まれるが、これはドストエフスキーの『罪と罰』からの引用で、不可解な挿入ともいえる。
『罪と罰』で、だれがだれをどのように殺したか、それは上記の一文に明記されている。しかし「なぜ」という謎は最後まで解けない。ここに『黙約』を重ねるなら、同じことが言えるだろう。だからこそ、彼らの精神は崩壊への緩慢な道をたどるのだ。それは急激な破滅よりはるかに残酷なのではないか。(吉浦澄子訳)
ALL REVIEWSをフォローする