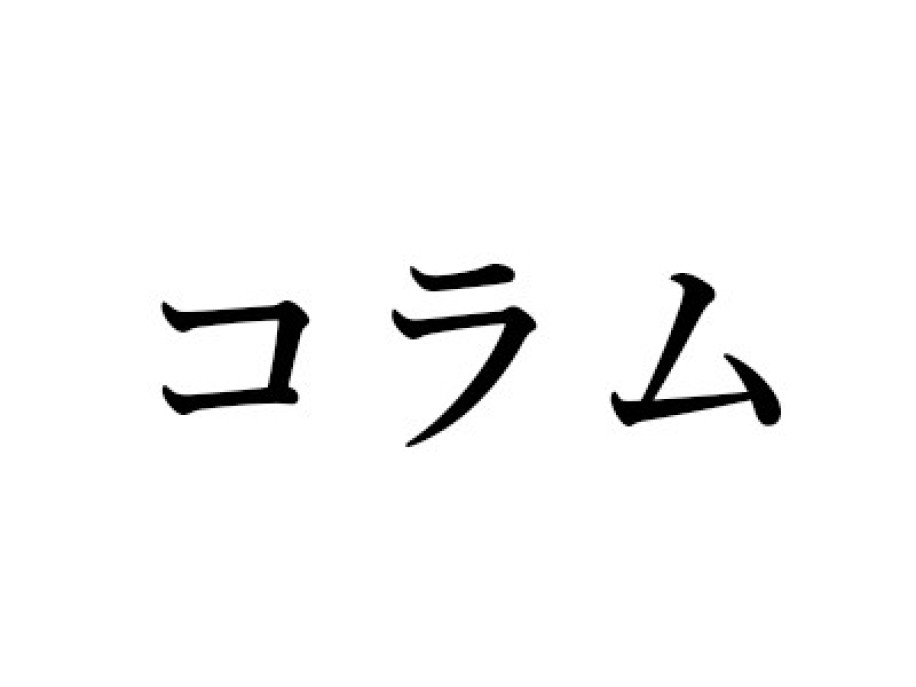書評
『アメリカの小さな町』(晶文社)
カンザスの青い空
たまたまテレビをつけるとクリントン氏の就任演説をやっていた。注目されたくだり、「自分や家族だけでなく、地域社会や国家にももっと責任をもとう」は「コミュニティ・アンド・カントリー」と耳に残った。字幕の訳はいかにもカタい。アメリカでは個人、家族、町、国が、わりと無理なくつながっているのだな、と実感した。そう思ったのは、この本を読んでいたからだろう。トニー・パーカー『アメリカの小さな町』(橋本富郎訳、晶文社)――イギリス人がアメリカのどまんなか、カンザス州の小さな町バードで行なったインタビュー集。百人に多様な人生を語らせ、一つの地域社会を浮かび上がらせる。いわば町のつづれ織り。
あいさつがわりの集会で彼はジョークをとばす。「十年前、灯台の本を書きまして。カンザスにいる間にも灯台をたくさん見たいものですね」。しいんとする。帰り際に誰かがいう。「カンザスには灯台なんか一つもないと申し上げても気を悪くなさらないでね」。町の名〈バード〉はむろん仮名。こんなきまじめで正直な人が住む二千人のコミュニティ。
ぶ厚い本だが、訳も快調、あきずに私はページをめくる。著者はインタビューをだしに何かの主張をしようとはしない。テープを忠実におこし、淡々と語りをつみ重ねる。
教師や聖職者のそつのない答えより、無防備な語りの方が面白い。「あれはラスバーグの奥さんで、こことコロラド州境とのあいだで拝める一番の美人だ」と保安官。「毎日『バーボン』というだけでぜんぜん口をきかない常連がいるの」と酒屋のマダム。「豚を買う五百ドルを貸してという十四歳の子にローンを組んでやった」と銀行家。「生活の質、という意味でなら豊かだよ」と競売人。みんな自前の考えと自前の言葉を持っている。自分のために働き、だれかに時間を盗まれてはいない。
こうして平和で静かでのんきで親切で、ちょっと単調で気持ちよく住める町の全体が見えてくる。いいことだけとはかぎらない。高齢化はすすみ、若者は脱出したがっているし、排他的なところや、偏見もないわけではない。しかし、ここでの暮らしを何かと取りかえたがっている人は、あまりいない。
私の住む東京の小さな町にも、少し似ている。大きく違うのは〈バード〉の人たちにはおおかた離婚経験があること、再婚をおそれないこと、中途で大学へ入り直すこと、養子を持つ人が多いこと。つまり、やり直しがきく。 たとえば三十八歳で三人の子がいて離婚した洋服店の女主人は、四十代半ばで建築技師と再婚、二人で何年もかけて家をしつらえる。「それが最大の絆、世界中どこへいってもこんな台所はふたつとないわ」。自分の選んでつくった人生への誇りと充足が、ありふれた毎日を輝かせる。
地元紙編集者の老女性の言葉も、同じ仕事をもつ私にひびいた。「人びとの私生活上の事柄を活字にしたくない。だれだって、生活していくうえで問題を抱えているんだし、それを自分の心のなかにしまっておく権利をもっている」
何も変わらない町で、人は生まれ、育ち、挫折し、道を選び直して死んでいく。それこそが変化だ。カンザスの広い平原と青い空、変わらないものがあるから、人は安心して変わることができるのかもしれない。
この本には「幸福」という量りきれないものの尺度が多彩に示されている。もう一つのアメリカ紹介、町づくりの参考、結婚・離婚論としても読めるだろう。本を閉じて私は何か落ちつき、愉快になった。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする