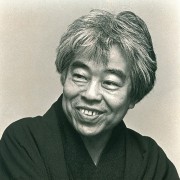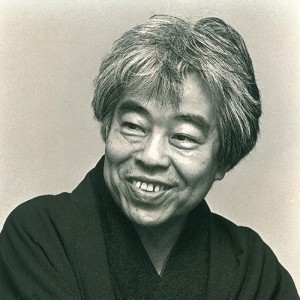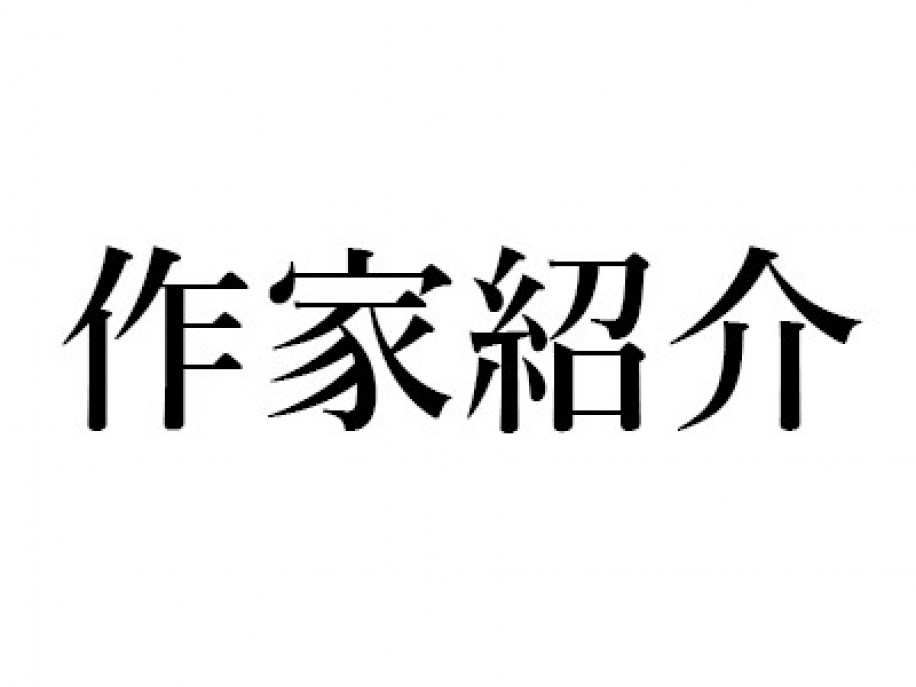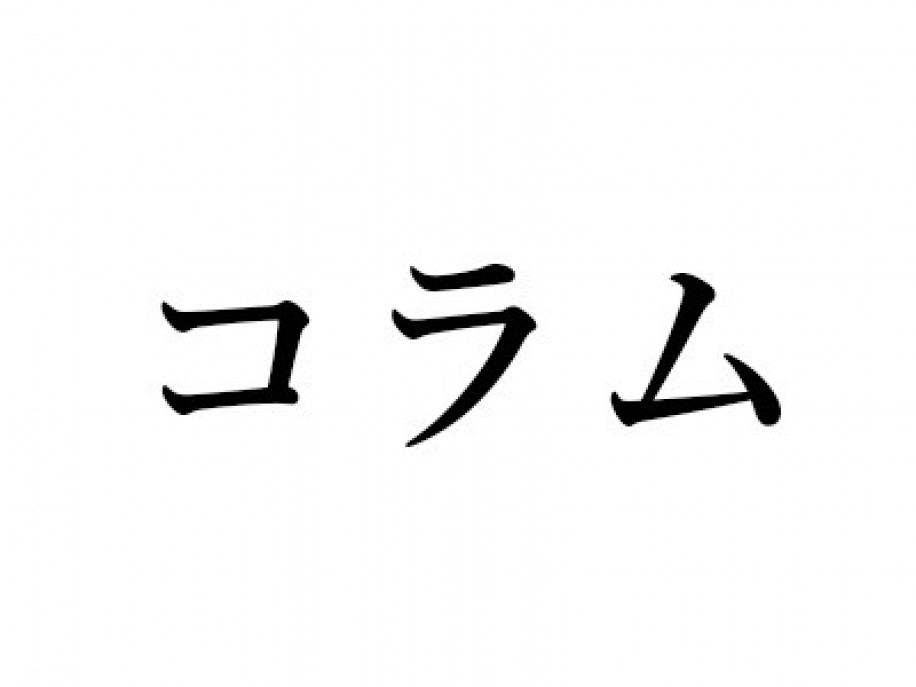書評
『軍旗はためく下に』(中央公論新社)
”聖戦”の傷痕を執拗にえぐる
”売国奴”などという言葉が、そのまま何の疑いもなく通用していた時代があった。そしてその一方では、"聖戦"あるいは"軍国美談"といった言葉もあふれていた。しかし”聖戦”のかげには、多くの傷痕がかくされている。「軍旗はためく下に」は、その傷痕を執拗にえぐった連作からなっている。戦無派の世代には〈敵前逃亡・奔敵〉とか、〈従軍免脱〉などと聞いても、何のことかよくわからないに違いない。〈敵前逃亡・奔敵〉とは、戦場において理由もなく部署をはなれ、投降したり、捕虜になったものをいい、〈従軍免脱〉は従軍を免がれるために病をいつわったり、身体を毀傷したりすることをさす。「軍旗はためく下に」の各章には、これらの陸軍刑法上の罪名がそれぞれつけられているが、このことでも明らかなように、この作品は戦場において投降したり、上官を殺害したり、従軍を免がれるために、わざと負傷したりしたケースをたどっているのだ。
話は毎年二度ずつ浅草のお寺で開いていた戦友会の仲間たちで、回想録をつくろうということになり、勇ましい手柄話や美談だけではなく、軍隊内の犯罪で処刑された戦友の問題までとりあげ、それを「私」が調べてまわる形式になっているが、時期や戦域などは各章によって異り、「私」の存在は一種の語り部的役割に解消されているようだ。
しかし、たとえば〈敵前逃亡・奔敵〉で死刑になった農村出身の小松伍長のケースや、〈従軍免脱〉の罪にとわれた矢部上等兵の場合にしても、彼らの当時の事情を知っているはずの人々の記憶がさながら芥川龍之介の「藪の中」
を思わせるように微妙なくいちがいをみせているのが、かえって真実感をそえる結果になっている。
しかもこういった問題が、過去の古傷であるだけでなく、戦後二十五年たった今日においても(事務局注:本書評執筆時期は1970年)、依然としてその遺族のものや関係者に暗い影を投げていることは、「敵前党与逃亡」の章で、馬淵軍曹のバースランド島ブマイにおけるケースをみるだけで十分だろう。彼は〈敵前党与逃亡〉の理由で敗戦直前に死刑になったが、その証拠は厚生省に保管されている戦没者連名簿に記載されたわずか一行の文句にすぎず、有罪を証明する判決書などはどこにもなく、戦友のひとりは戦死だといい、連隊長は終戦後の事務処理上のあやまりだと語り、軍法会議にたちあった関係者も、馬淵の名前を聞いたことがないという。もっともなかには、それらの証言はいずれも嘘で、上官の肉を食べたために処刑されたなどといいだすものもいたが、調べれば調べるほど、馬淵軍曹の死因は謎の中につつまれてゆく。そして〈敵前党与逃亡〉罪という罪名だけが遺族たちをしばるのだ。
結城昌治は、わずかではあるが戦争の末期に海軍特別幹部練習生だったことがある。また戦後しばらく東京地検で恩赦関係の事務に従い、万をこえる軍法会議の記録を読んだという。そのときの納得できない気持が、この「軍旗はためく下に」に結晶したのであろう。その意味では、彼は敗戦二十五年目の宿題を、ひとつ果したといえる。
著者は推理作家として既に定評のある書き手だが、その守備範囲はひろく、ナンセンスものからハードボイルドまで手がけている才人だ。第六十三回直木賞に選ばれたこの作品は、彼の戦中派らしい意気ごみを感じさせる。
ALL REVIEWSをフォローする